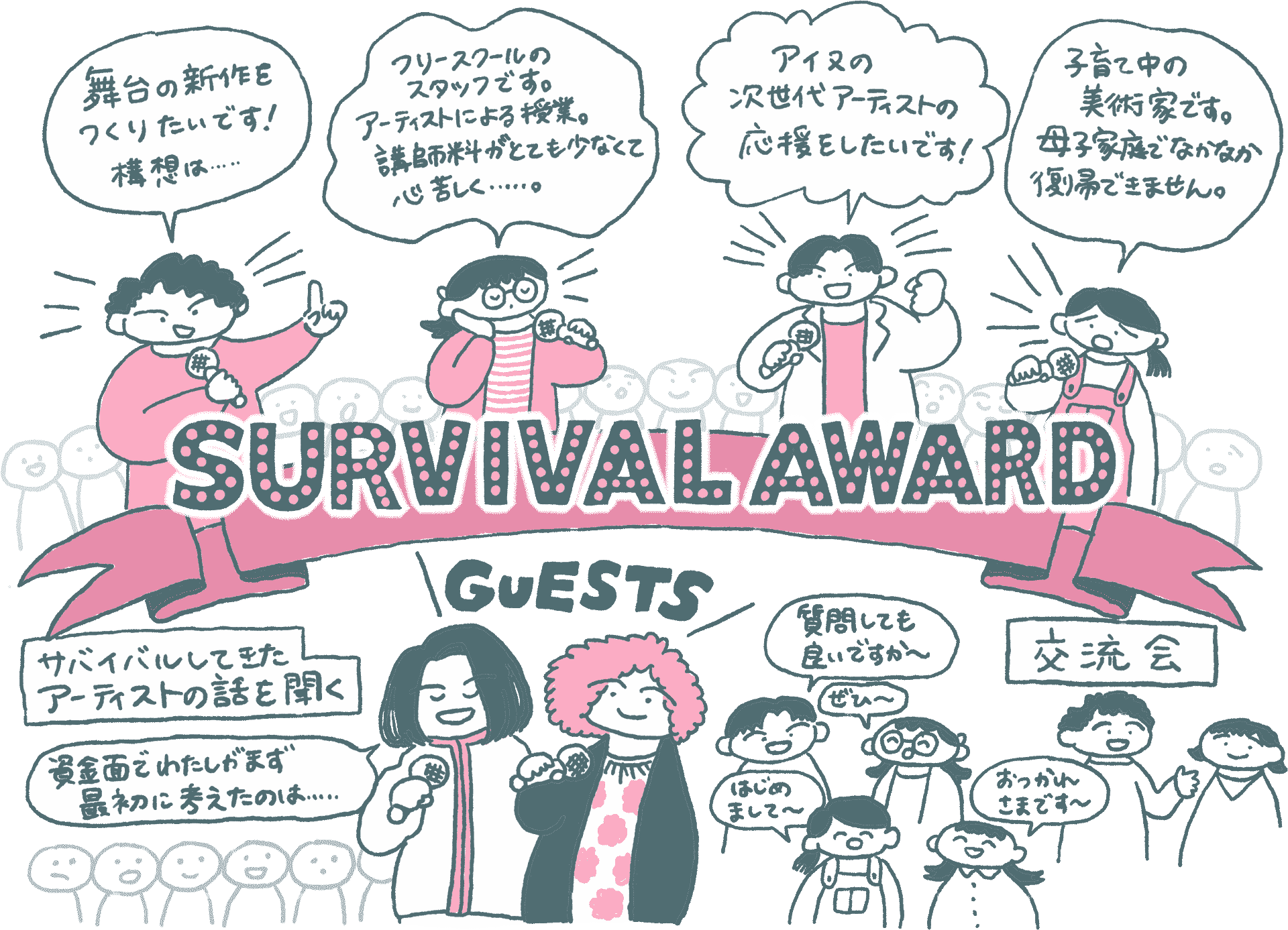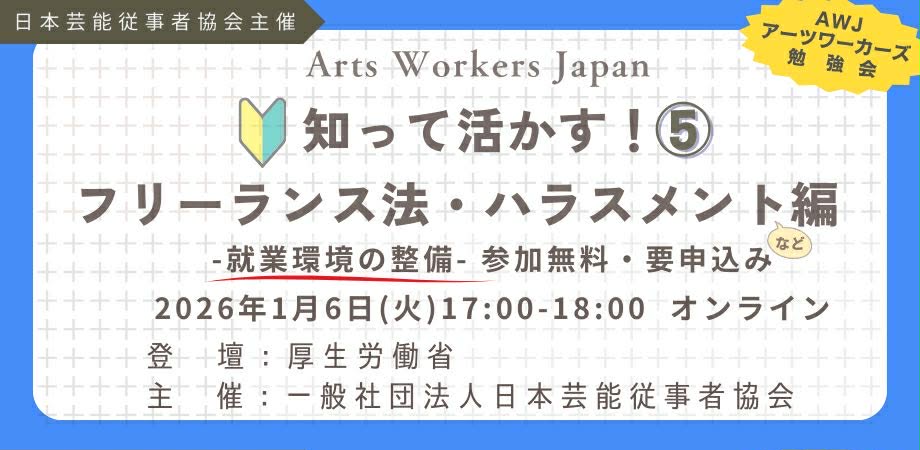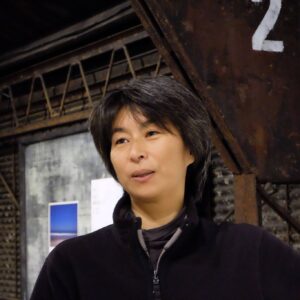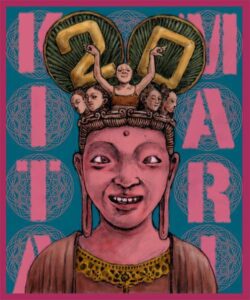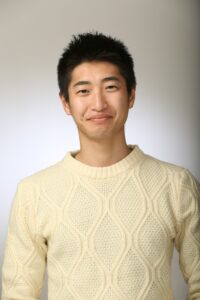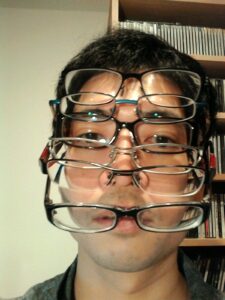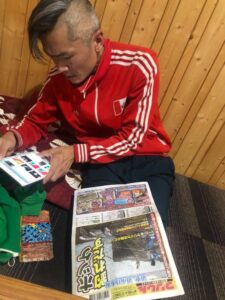HAUSは芸術の中間支援団体
応援が循環する社会の基盤をつくります
Artist Tree 根深夏 声楽、ソプラノ、古楽北海道安平町出身。札幌大谷短期大学音楽科卒業、北海道教育大学大学院修士課程修了。`20年10月「古楽と南米リズムの出会い」を主催し、札幌市主催の「さっぽろアートライブ助成事業」として動画配信(Youtube)。同11月「二人のソプラノで歌うバロックの調べ~いにしえの恋の嘆き(東京オペラシティ近江楽堂)」に出演。`21年11月「根深夏ソプラノリサイタル-モンテヴェルディが描いたギリシャ神話・ローマ帝国」にて令和3年札幌市民劇場 札幌市民芸術祭大賞を受賞。`22年6月1stアルバム「古楽と南米音楽の接点を求める旅」をリリース。`22年11月「タンクレディとクロリンダ~歌・チェンバロ・語りで紡ぐ物語(ザ・ルーテルホール)」にてバロック音楽と寄席、サンドアートによるコラボ公演を企画・出演。声楽を富田とき子、大友ひろ世、陣内麻友美の各氏に師事。古楽を濱田芳通に師事。公演のお知らせ神々の恋物語 ~ソプラノとチェンバロで紡ぐバロックの世界-第1636回札幌市民劇場-■日時 2026年5月9日(土)13:30開場・14:00開演■出演 根深 夏 (ソプラノ)、上羽 剛史(チェンバロ)、磯貝 圭子(ナビゲーター)■会場 SCARTSコート 札幌文化芸術交流センター(札幌市中央区北1条西1丁目・札幌市民交流プラザ1階)地下鉄:札幌市営地下鉄「大通駅」30番出口から西2丁目地下歩道より直結 徒歩約2分/JR:「札幌駅」南口から徒歩約10分■料金 一般3,000円・学生2,000円 (当日券+500円)■チケット取り扱い🎫道新プレイガイド: https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/1424🎫google form: https://x.gd/HDVJC🎫teket: https://teket.jp/6136/64589■ご予約・お問合せ スタジオ・ティンクナ ✉ natsunebu86@gmail.com■公演内容~ギリシャ神話をテーマとしたバロックコンサート東京で活躍するチェンバリスト上羽剛史さんと札幌座の俳優・磯貝圭子さんをナビゲーターに迎えてお送りするバロックコンサート。バロック音楽に馴染みのない方から古楽ファンまで、誰もが楽しめる約90分のプログラム。前半「本当はポップなバロック音楽」-ルネサンスからバロック期の軽やかで魅力的な作品を、解説を交えながらお届けします。後半バロックオペラ「La Calisto(カリスト)」(F.カヴァッリ作曲)抜粋演奏。美しいニンフ・カリストが、処女神ディアーナの侍女として純潔を守る誓いを立てるも、神々の王ジュピターの策略に巻き込まれ、恋と変身のドラマが繰り広げられます。SCARTSコートの美しい響きの中で、チェンバロの繊細な音色とソプラノの歌声をお楽しみください。■主催 札幌市民芸術祭実行委員会・札幌市・(公財)札幌市芸術文化財団■主管 根深夏(スタジオティンクナ)■後援 札幌市教育委員会*****************https://twitter.com/natsunebu【Youtube】https://www.youtube.com/channel/UCq-tQxyP0riLyY0UQznHu-w【FaceBook】https://www.facebook.com/natsu.nebuka【Instagram】https://www.instagram.com/natsunebu/?hl=ja
Artist Tree 成田 真由美(narita mayumi) 文化芸術 民族音楽 現代アート NPO 科学技術コミュニケーション 災害支援 2025年4月から、文化芸術に関わるオープン・コミュニケーターとして活動を本格始動。私が思うコミュニケーターとは「狭間に立ち尽くす者」であり、そこから開いていくことで繋がったり繋がらなかったり好きにすればいいので、時には閉ざしたりもする「開く人」であろうと思った。内に籠る感覚に病むこともあるので、できるだけ能天気でいようと思う。いわゆる無職だけど。 これまでは、NPO中間支援組織の非常勤スタッフだったり、様々な形で災害支援の外郭を担ったり、科学技術コミュニケーションを実践したりしながら、文化芸術の振興に寄与する活動を行っていた。二足の草鞋どころの騒ぎではない。落ち着け、自分。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeNews/お知らせ2025.3.31 北海道芸術文化アーカイヴセンター(ACA)のWEBサイトを公開しました。https://hacac.jp/note始めました。文化芸術に関するイベント参加レポートや所感などを不定期更新。https://note.com/narita_mayumiWorks/ Biography/略歴1969年東北の田舎町に生まれ、自然にまみれた幸せな幼少時代を過ごす。好きな山のおやつは桑子と無花果。中学時代はブラスバンド三昧で、日焼けとは無縁の3年間を過ごす。高校時代はワンダーフォーゲルで山の厳しさを痛感する。以来、食料採取以外の目的で山に入ることはなくなった。東北学院大学文学英文学科ではシェイクスピアを専攻し、東京グローブ座でロイヤル・ナショナル・シアター(Royal National Theatre)の附属劇団とロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(Royal Shakespeare Company)を観劇したことが思い出深い。英語はほぼわからなかったけど気にするな。東京で就職し、営業が天職だと思うに至る。が、スタジオカメラマンのアシスタントやDTPオペレーターやイベント運営のお手伝いなどあれこれ雑多にやってたら、ライセンスビジネス(商標)の管理業務に落ち着いた。いい機会なので、工業所有権の勉強をするが、2年で弁理士資格をとれるほどの奇跡は起こせなかった(当時の合格率3%)。それもこれも、パリ条約の所為。2002年、札幌に移住。途中端折って現在に至る(2025.5)。以下、文中敬称略。<文化芸術関連>広く文化芸術に関わる行動・活動をしています(鑑賞&裏方)。土着(土地の香りや手触りを感じられる、生活に密着した)文化(特に音楽と文様)や、「問い」が含まれていたり、こちらが揺さぶられるような(拡張領域の拡大)芸術が大好き。・2004~ 馬頭琴関係 *一部記憶があいまいな部分があります。確認でき次第修正します。ごめんなさい。のどうたの会(講師:嵯峨治彦)主催の馬頭琴ワークショップに参加し、馬頭琴に惚れる。当時のどうたの会では個人レッスンが行われていなかったため、友人が主催するアヨーシ・バトエルデネ(モンゴル国出身)指導の「さっぽろモリンホールクラブ」の個人レッスンを受け、ボーイングや音階練習など基礎を叩き込まれる(2005~)。いや、曲弾きたいという訴えに、師匠曰く「馬の曲は、ほっといても勝手に弾き始めるでしょ?」とのことで、ホントにその通りだった!そして、モンゴル料理屋「ゴビィージョル」@琴似が開店し、宴会が加速する。レッスンや発表会より先に宴会がセッティングされる不思議(馬頭琴あるある)。生徒はそれぞれの演奏活動を始め、私も2006年頃から「成田ぶらりあんズ」(馬頭琴ディオ)として、いい気になってステージに上がったりもした。しかし、アヨーシ・バトエルデネが自身の演奏活動に注力するために、さっぽろモリンホールクラブでの指導を終了する(2013)。モリンホールクラブ主催・運営協力のコンサート:馬頭琴四重奏(2007@ザ・ルーテルホール、2009@kitara小ホール)、オルティンドー&馬頭琴コンサートとWS(2006,2007@札幌市内各所)、馬頭琴と朗読のコンサート(2010@時計台ホール)、トリオ(馬頭琴、チェロ、ピアノ 2012@kitara小ホール)など。さっぽろモリンホールクラブ発表会(2011@紙ひこうき)のどうたの会でも個人レッスンが開始(2008~)されたので、いそいそとご指導を頂きに参上し、生徒で構成される「ポニーテールズ」にもちゃっかり参加する。のどうたの会が毎年開催する「さっぽろ馬頭琴ナーダム」(2007~)には、必ずなにかしらのカタチで参加している(ポニーテールズ、スタローン・パフォーマンス、馬頭琴WSサポートや受付等スタッフ、参加者、打ち上げなど)。嵯峨治彦ホームページ https://sagaharuhiko.com/・2011「旗ヲ出スベカラズ」 / 2012「シャッポおじさんの写真館」 / 2013「桑の実の色づく頃には」2010年頃からコンカリーニョのボランティアスタッフ「カリット」に参加し、気が付けば住民参加型の音楽劇の制作統括(リーダー)を3年間行う(上記の3作品)。その後は、宮城県人として山形県出身の職員と共謀し、「コンカリ秋祭り」や「懇親会」の名目で芋煮会を強行する。NPO法人コンカリーニョ(アーカイブなし) https://concarino.or.jp/・2013 ダンス×墨絵 即興コラボレーション 3DAYS(2013.12.12,13,14)初めての主催イベント。実行委員長として、岩下徹氏を招へいし、ダンスのワークショップと墨絵師杉吉貢氏とのコラボレーションイベントを開催する。以前開催されていたダンスと墨絵のコラボレーションを観たいがために主催した。右も左もわからない手探り状態だったが、友人知人、協力者に支えられて開催することができた。・2014、2017 札幌国際芸術祭(SIAF)ボランティアセンター勤務(有償スタッフ)あまりにも忙しかったので、よく覚えていない。それでも、作品を観に行く根性はあった。自分、エライ。札幌国際芸術祭 アーカイブ https://siaf.jp/archive/・2014~ アートカフェin資料館・アートカフェ⁺SIAF2014のボランティア有志が始めた「感想を語り合うための場」としてのアートカフェェin資料館をお世話役として引き継ぎ、1日店長制(テーマ募集)として継続。現在まで、通算32回開催している。気楽なおしゃべり会を目指しているので、直接対話できないコロナ禍により一時中断。2025年から開催形態を変更して再始動。・2016 「カザフ刺繍展 草原の民の想いと願い」(2016.11.8-11.19)カザフ刺繍の展覧会、カザフ文化紹介トークイベント、カザフかぎ針刺繍ワークショップをみんたるにて開催。主催は月輪会。・2023 札幌市文化芸術基本計画検討委員(市民公募委員)後ろ盾や所属団体などへの斟酌無用な市民公募委員という立場で、友人知人に助けて貰いながら、言いたいだけ言い放った数か月間。その後、偶然出会った専門職の方から「ああ、あの成田さん」といわれる程度には爪痕を残してしまったようだ…。高校生の頃から、なにも変わっていない自分にびっくり(高校生活2日目に、体育の先生から同じことを言われた)。札幌市文化芸術基本計画(第4期)検討委員会 記録https://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/kihonkeikaku/kentouiinkai4.html・2024~ 北海道芸術文化アーカイヴセンター(ACA)設立 2024.6.19北海道に関連する芸術・文化活動と資料・書籍の情報をアーカイブ(記録・保存)する任意団体。副事務局長として活動中。https://hacac.jp/<科学技術コミュニケーション関連>・2018 CoSTEP本科(ライティング・編集実習班)受講科学技術から一番遠い存在という称号を欲しいままにし、受講生に多大なる影響を及ぼしながら無事終了する。CoSTEP ホームページ https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/・2019-2021 CoSTEP研修科所属 調査テーマ「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー」カリキュラムのない研修科では、自分で設定したテーマについて担当教員からアドバイスを頂きつつ調査研究を行う。私の3年間の成果は、北海道大学学術成果コレクションHUSCAPにて公開。https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/index.jsp・2020~ NPO法人市民と科学技術の仲介者たち 2020年設立メンバーがほぼ理系という中で、感情系という立ち位置を確立し、副代表を務める。現在進行形で活動中。https://mecst.org/<災害支援の外郭>・2015~ シリーズ「福島に生きる」(月輪会)東日本大震災と原発事故に見舞われた「福島」を知るための活動。写真展、講演会、チャリティーコンサートなどを開催。複雑に絡み合う感情と、何が正しいのかわからない科学の狭間で途方に暮れることが多い。https://www.facebook.com/livefukushima・2016-2022 3.11 SAPPORO SYMPO2014年から開催されている、東日本大震災と原発事故からの学びをまちづくりに活かすためのきっかけを作るイベント。私は2016年に実行委員となり、「7年目の3.11」から運営に携わる。主にボランティア活動を担当。毎年、札幌市地下歩行空間(チカホ)で開催していたが、2020年コロナ禍による中止を経て、「12年目の3.11-みる・よむ・立ち止まるー」(2022.3.10-11)をもって活動終了。https://311sapporo-sympo.com/<中間支援>・2014.10-2025.3 北海道立市民活動促進センター(公益財団法人 北海道地域活動振興協会)非常勤受付職として勤務する傍ら、リニューアルした広報誌「しみセン便り」 の企画編集と特集記事vol.68~vol.81(2016年~2020年)、臨時特別号(COVID19)、最終号vol.93を執筆。・2019 -2025.4 北の国災害サポートチーム(きたサポ)2018年北海道胆振東部地震の支援者情報共有会議(北の国会議)の運営支援から、北海道災害中間支援組織であるきたサポ設立にかかわる。幹事団体の一員として、WEBサイトの構築( https://kitasapo.net/ )と北の国会議データベース( https://data.kitasapo.net/ )を作成。2025年幹事会から退会。Contact/連絡先https://www.facebook.com/mayumi.narita.908
Artist Tree もえぎ色 ミュージカル2004年に代表 光燿萌希によって結成されたミュージカル劇団。女性を中心に16人のメンバーが所属し活動しています。ド派手な衣装と完全オリジナル脚本・音楽が特徴。近年は子どもも出演できる演目が増え、親子が楽しく観劇できる作品づくりをしています。 年齢を問わず参加しやすい演目やフレキシブルな練習時間の設定、幅広い目的で入会できるミュージカルスクールの開講など、多くの人にミュージカルの魅力を知ってもらい、誰でも輝ける活躍の場を作りながら、将来的には札幌からミュージカルスターを生み出すことが目標です。「みんなが元気になる、明日への活力になるミュージカルを」女性メインのミュージカル劇団として、派手な衣装とダンス、舞台演出で未就学児から観劇できる明日への活力になるミュージカルを展開しています! 目標は、20周年に札幌ドームで公演を実施すること! さらには自分たちの劇場を作れるくらいのお客さんを呼べるようになり、地方からも声のかかる札幌発のミュージカルカンパニーになっていくことを目標としています。もえぎ色第21回公演『なびいて大正怪盗乱麻』●日時2025年8月9日(土) ①18:00 10日(日) ②11:00/③14:30※開場は開演の30分前●会場札幌市教育文化会館小ホール (札幌市中央区北1条西13丁目)011-271-5821●料金一般 前売3,500円 当日3,800円高校生以下 前売2,500円 当日2,800円未就学児童無料(要予約)脚本 深浦佑太(ディリバレー・ダイバーズ)演出・振付・作曲 光燿萌希音楽 福井岳郎●キャスト加藤明子(中森あんこ/ザラモール)穂井田夕奈(光秀かつら) 左海千優(草川まみ)左海夢依(早野いち) 唯斗(外堀警部)高城月子(草川刑事) 恒本礼透(宮崎刑事)太田有希菜(ザラヴィ・ベル・エポック)光燿萌希(ストッパー) 小川眞樹(ジョッシュ)渡邉宏行(リンジン) 桝谷まい子(スマンサ)根深夏(パピー)蝦名紗友水(尾美ヴィヴィ)野澤麻未(米田黒子)長谷川実優(キド)杉浦木音(ホッケ)邉渡希心(ゴッツ)●アンサンブル黒沼陽子(もえぎ色)桒山廉(桝谷博子バレエスタジオ)小寺青空 立山由佳子 長畑れい子長谷川明穂 春川なしの桝谷春輝(桝谷博子バレエスタジオ)●音楽隊南米民族楽器 福井岳郎ピアノ 太田亜紀子パーカッション 手島慶子●コーラス大平詩織(もえぎ色/ウェイビジョン)国門紋朱(もえぎ色)●チケット購入(事前支払い)道新プレイガイド〒060-0061 札幌市中央区南1条西1条8-2 高桑ビル MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店地下1階https://doshin-playguide.jp/ticket/detail/251札幌市民交流プラザ チケットセンター〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目セイコーマートセコマコード:D25080902ローソンLコード:12444https://l-tike.com/order/?gLcode=12444・パスマーケットhttps://passmarket.yahoo.co.jp/.../detail/02ntjguvek841.html●チケット予約(当日支払) こりっちhttps://ticket.corich.jp/apply/363394/・お問い合わせTEL:080-5583-0560MAIL:moegiiro_info@yahoo.co.jp●スタッフ舞台監督 坂本由希子美術 高村由紀子音響 安達玄(株式会社BLUESTONE)照明 新木拓朗(株式会社アーツ)衣装デザイナー ナカムラタカコ(haNgER)衣装製作 滝法花フライヤーデザイン 穂井田夕奈映像撮影 上田龍成(ウェイビジョン)制作 もえぎ色主催 パフォーマンスプロダクションCOLORE共催 公益財団法人北海道文化財団後援 北海道、札幌市、札幌市教育委員会助成 札幌文化芸術交流センターSCARTS 文化芸術振興助成金交付事業(公益財団法人札幌市芸術文化財団) *******【5/25(日)あけぼの学校祭!】もえぎ色もフリマでの参加と✧ 𝒯𝓌𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒𝒯𝓌𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒 ✧のステージ発表で出演します🎵お待ちしております〜!!!*****『One Dream FESTIVAL 2025』「One Dream FESTIVAL」は、子どもから大人まで、みんなの夢を応援するイベントです。様々なパフォーマンスを楽しめるステージや食を楽しめるエリア、子ども達が参加・体験できるワークショップブース…などなど大和ハウスプレミストドームのアリーナ全面を使い、アートやスポーツ・教育・食など盛りだくさんのエリアを通して「みんなの夢」を「みんなで応援する」空間を作ります。-わくわくドキドキのステージ・ミュージカル劇団「もえぎ色」によるオリジナルミュージカルの上演・アーティスティックマガジンView編集部によるファッションショー…などその他、様々なパフォーマンスを行います。-家族みんなで楽しめるコーナーがいっぱい!・パンコーディネーターの森まゆみさんによる「パンフェス」・ふわふわのエアー遊具によるアトラクション・水に溶けるクレヨン・Kitpasによるアートエリア…などイベント詳細開催日時:2025年8月20日(水) 開場:10:30 / 開演:11:00 / 終了:17:00場所:大和ハウスプレミストドーム(札幌市豊平区羊ケ丘1番地)HP:https://onedreamfestival.com/現在、イベント内での一般出店者・企業の募集、そしてクラウドファンディングを実施しております!是非HPをご覧ください。*******HPミュージカル | ミュージカル劇団「もえぎ色」 | 札幌市 (moegiiro-musical.com)Youtubehttps://www.youtube.com/@user-ep6nf1zt7ihttps://twitter.com/moegiiro560
Artist Tree 河野千晶(Chiaki Kouno) ダンス、ダンサー、振付、振り付け、エンタメ、身体、からだ、体、心、自由、ストレッチ、コンタクト、コンタクト・インプロビゼーション、コミュニティダンス、エントレ、エンタメトレーナー、ワークショップ生きることは踊ること。誰もが一人ひとつずつ持っている、あなただけのUniqueな身体をRhythmicにサポートします。一生付き合っていく身体と仲良くなって、楽に生きられる使い方を一緒に探していくトレーナー。▷北海道札幌市出身。UniqueRhythmic(うにくりずみっく)代表。10歳よりStage Grand-Prixにてジャズダンスを始める。以降、ヒップホップ、バレエ、コンテンポラリーダンスなど多ジャンルを学ぶ。2014年に櫻井ヒロとコンタクト・インプロビゼーション(C.I)ユニットmicelleを結成し、C.Iを軸に活動を展開。国内外のアーティストと公演活動を行う。(令和元年度「札幌市民芸術祭奨励賞」受賞。)▷現在はエンタメートレーナーとしてダンサー、俳優などの表現者へ向け、自分の心と体を理解し自由に動くための身体作りをサポートするほか、高校、大学などでC.Iワークショップを行う。UniqueRhythmic(うにくりずみっく)URLhttps://www.uniquerhythmic.com/https://twitter.com/ChiakiKounohttps://ticket.corich.jp/apply/360389/005/micelle URLhttps://micelle.jimdofree.com
Artist Tree 館 宗武 演劇館 宗武(たて むねたけ) 1974年、函館市生まれ。 高校卒業後、俳優を目指して上京。桐朋学園短期大学部芸術科演劇専攻で舞台演劇を専門に学ぶ。帰郷した後、文化財団職員として函館演劇シーン活性化のために多くの事業や企画の立ち上げや運営に携わる。 2014年に自身の演劇ユニット「41×46」を旗揚げ。以降、様々な作品の脚本・演出を手がけるほか、バーやナイトクラブなどでの公演や、北海道内外への遠征公演など精力的に活動。個人としてもGLAYのMVや短編映画などへの出演のほか、中学校などを訪問しての演劇指導や、大学での講演も行っている。 2023年、41×46の代表を後進に委ね、演劇文化振興の新たな活動に取り組んでいく。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree演劇体験講座 一陣の風2025どこの誰でもない人でいい何も知らない、何もできなくたっていい人と何かをすることが苦手でもいいこの街で生きる自分になるために新しいことを知り、できることを見つけるために一緒に何かをやれる仲間に出会うために「演劇」、はじめよう。演劇体験講座 一陣の風2025【内容】函館市内および近郊の一般市民を対象とした、年齢(中学生以上)・性別・経験の有無など一切不問の演劇体験講座。約9ヶ月間、毎週1回(全36回程度)開催し、最後に参加者全員で取り組む修了公演の上演を目指す。【期間】2025年4月3日(木)~2025年12月7日(日) 基本は毎週木曜日19:30~21:30で、講師や会場の都合などでの変更および公演のための練習などで開催が増える場合あり。 ※修了公演は2025年12月6日(土)・7日(日)の予定【会場】函館市青年センター(函館市千代台町27-5) 会議室など【定員】20名 ※応募者多数の場合には未経験者を優先。【参加料】一般/5,000円 学生/3,000円 (いずれも月額) ※修了公演の出演料および、36回以上開催する場合などでも,追加料金は一切発生いたしません。 ※お支払い方法は分割、月額対応も可能です。【参加条件】演劇や舞台に興味があり、やる気のある中学生以上の方であれば年齢・性別・経験など一切不問。中・高校生のみ、保護者の方の同意が必要。お申込み・お問合せ090-6216-1459(主宰 館たて)butaibaka4416@gmail.comhttps://form.run/embed/@butaibaka-ichijin2025?embed=direct
Artist Tree 大川敬介 木こり、俳優、舞台、芝居、演劇Crack Works主宰 俳優、演出家、映像作家、木こり、THE ICEMANS。 脚本家、秦建日子氏に2年間師事後、様々な劇団やダンス、舞踏作品などジャンルレスに参加。 2021年より、Crack Worksを主宰し、映像作品「undercurrent」をYOUTUBEに発表。演劇という枠に捉われない作品、企画を発表。 2022年より、造形作家、竹中博彦氏(THE ICEMANS主宰)と「Potluk Party」という月1回の持ち寄りピクニックのような集まりの場を開催。 2023年より、自身のアートワーク制作を始める。 第一弾として「木こりのマッチ」の制作を始める。Kicorinoシリーズ自身が森で伐採採集した素材や、インスピレーションを元に、未来の森に還元できる事、を目的としてkicorinoシリーズのアートワーク制作を始める。木こりのマッチ2022年2月24日、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始しました火はあらゆるを燃やしますそれでも私たちの生活には火はなくてはならないものです少し使ったら少し返す、をコンセプトとして手に取った皆さんの生活の中から環境保全に参加できるアートとして売上の一部を環境保全の団体に寄付したいと思っていますとても小さな試みかもしれませんがあなたが手に取った小さなマッチの火がどこかの緑になりいつかの誰かの水に変わるようにと思っています命を奪う大きな火よりも、命を繋ぐ小さな火「木こりのマッチ」Kicorinoシリーズ第一弾「木こりのマッチ」1コ ¥300-2コ ¥500-5コ ¥1,000-ショートムービー「scent」2023年、札幌演劇シーズンの演目の1つとして上演予定だった舞台劇団千年王國「からだの贈りもの」がコロナにより本番直前になり上演中止になりました。上演を楽しみにしてくれていた人達に何かできないかと、スピンオフのような形でショートムービーを製作しました。セリフなし、音楽のみ、の映像作品です。よろしければご覧ください。scent1.{良い}香り、芳香2.{人や動物の}残り香、臭跡、遺臭3.[英]{化粧品の}香水4.嗅覚、臭覚5.{これからの出来事の}直感、直覚6.{これからの出来事の}手がかり、ヒントhttps://www.youtube.com/watch?v=KxBFd7Bw8Mw キャスト: 大森弥子 リンノスケ 大川敬介 THE ICEMANS 竹中博彦 Alidad Kashani 上野かなこ 宮崎亘 宮崎修 馬頭琴:嵯峨治彦 ギター:亀川朗 ICE DOME ART : THE ICEMANS Flower Installation Art : YANASE design.MARUYAMA 撮影:大森弥子 リンノスケ 大川敬介 脚本、編集、音楽編集:大川敬介企画/構成:Crack Works------------------------------- Cast : Yako Omori Rinnosuke Keisuke Okawa and THE ICEMANS :Hirohiko Takenaka Alidad Kashani Kanako Ueno Wataru Miyazaki Shu Miyazaki Morinkhuur : Haruhiko Saga Guitar : Akira Kamekawa Music Edit : Keisuke Okawa ICE DOME ART : THE ICEMANS Flower Installation Art : YANASE design.MARUYAMA Recording : Yako Omori , Rinnosuke , Keisuke Okawa Editting : Keisuke Okawa plan / concept : Crack Works/ THE ICEMANS連絡先Twitter@theatrebook略歴Crack Works代表俳優、演出家、映像作家、木こり、THE ICEMANS。脚本家、秦建日子氏に2年間師事後、様々な劇団やダンス、舞踏作品などジャンルレスに俳優として参加。2021年より、Crack Worksを主宰し、映像作品「undercurrent」をYOUTUBEに発表。演劇という枠に捉われない作品、企画を発表。2022年より、造形作家、竹中博彦氏(THE ICEMANS主宰)と「Potluk Party」という月1回の持ち寄りピクニックのような集まりの場を開催。主な出演作品2021年 指輪ホテル「ポトラッチ」(しらおい創造空間『蔵』)、劇団千年王國「からだの贈りもの」2020年 Sapporo Dance Collective 2020「さっぽろ文庫101巻 『声』」2019年 飴を囓るな。「Have a nice TRIp」2018年 Sapporo Dance Collective 第1作品「HOME」kάmə「愛について」(振付、演出、出演)2017年「Logic of Black and White」、Sparrowwwwww(スズキ拓朗振付)2016年 TOBIU CAMP 「神景/SHINKEI」(山海塾 石井則仁振付)2015年、2014年 dEBoo#1「12人の怒れる男」
Artist Tree ほそやもくめ 演劇 地域 webライター 役者 脚本 演出 制作稚内在住。 役者、演出、脚本、制作、webライター、事業マネージャー、一児の母。2022年 演劇をツールに人と繋がるために『わっか演劇企画』を設立。 元々『わっか』の由来は稚内だったが、地域にこだわらず『演劇で人との繋がりの輪が大きくなったら素敵だなあ』と思う様になる。2024年2月に劇団稚童を立ち上げ。副代表。 2024年4月に劇団fireworksに入団。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 中村裕之 札幌で絵を描いています。連絡先hiroyuki.nakamura.studio@gmail.com略歴1977 浜松 > 1989 Chicago > 1993 Culver > 1996 Phily > 2000 Brooklyn > 2016 札幌 >Drexel UniversityとSchool of Visual Artsで写真を学び、2004年頃から絵を描いています。2006年にAkureyri ( Iceland )のresidencyで行った成果発表展が初めての個展です。詳しくはウェブサイトをご覧ください。https://www.hiroyukinakamura.com/展示・作品例"the sky above : 眩しくて" 展 @ 旧鎌田志ちや in 札幌, 2023年"High West" 2021oil, acrylic on linen, F50号 1,167×910mm"sun geyser" 2024oil, acrylic on linen, F15号 652×530mmアイスランド 2006年
Artist Tree 小林知世 KOBAYASHI Chisei 絵画、アート、美術1994年札幌生まれ 2017年東北芸術工科大学芸術学部美術科洋画コース卒業 油彩やステイニングの技法で風景・日用品・食べ物などを白やグレーを基調とした淡い色彩で描き、環境音を判読不能の文字のようなドローイングで表現する。目に止まることのない光景や音のもつ気配や震えを捉える制作に取り組む。主な活動に2021 個展 doughnut(仙台 galleryTURNAROUND)2020 個展 暗闇で手紙を読む(札幌 salon cojica)2020 グループ展 NEW JAPANESE PAINTING(ドイツ ハンブルグ mikikosato gallery)2018 アーティストインレジデンス End Of Summer2018(アメリカ オレゴン州 ポートランド)など。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeステートメントお知らせ⛲️個展のおしらせ⛲️“桜桃の味”taste of cherry会 期¦2024.05.09-30 11:00-18:00 火水休会 場¦gallery 門馬北海道札幌市中央区旭ケ丘2-3-38地下鉄円山公園駅からJR北海道バスのロープウェイ線(円11/円10)が便利です。VOCA2023(上野の森美術館)に出展した2m超の大きい作品2点と、新作を発表します。私はいつも円山公園駅からギャラリーまで30分ほど歩いています。よい季節なので歩くのもおすすめです🌸🍒お越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。WEB・SNSKOBAYASHI Chisei WEBtwitterinstagram連絡先kobako67●gmail.com ●→@
Artist Tree 北海道テントサウナ団/小林和也 テントサウナ、哲学、詩、批評、絵画、テントサウナアロマ制作活動:北海道の綺麗な水辺でテントサウナをして、人々を詩人にし「風が気持ちいい」などと当たり前のことを言わせる/哲学×テントサウナを介した批評活動『北海道テントサウナ団文庫』制作・文庫vol.2を販売中/絵画制作(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ『北海道テントサウナ団文庫2』発売中!定価:1000円もくじ・NISEU DRY・肝を試す・テントサウナ経 その構築と解体・Dead Chillとは何か・デッドチル文学 あるいは「終わり」研究序説・まんぷく弁当の歌・アップルパインツリーテントサウナアロマ「アップルパインツリー」発売中連絡先TwitterかInstagramのDM略歴2020年2月、コロナ禍における緊急事態宣言下に支笏湖にて、団体としての生を受ける。メインの活動は冒険。北海道の美しい水辺でテントサウナを行い、山水を眺めて詠嘆する/参加者を詩人にすることを行う。また、それらの体験を文章に起こし/哲学や文化との関連で批評を作成し、『北海道テントサウナ団文庫』として編纂する。テンサウ×絵画、テンサウ×音楽などのイベントを通じて、北海道の自然に寄り添うテンサウ文化を涵養する。
Artist Tree 戸島由浦(TOJIMA Yura) アートマネージャー、アートプロデューサー、企画、制作、マネジメント、制作過程、相談支援、兼業、若手アートマネージャー、時々プロデューサー。HAUS (Hokkaido Artists Union Studies)、ひよこアーツの運営メンバーとして主な活動を行う。作品や表現が生まれる過程アーティストの営みそのものを重視して、公演やワークショップの企画を行っている。近年は相談支援に関わりながら、アート関係者のキャリア形成について関心を持っている。 好きな食べ物はぶどうとさつまいも。ニュース●最新情報は以下サイトをご覧ください。https://yuratojima.studio.site/home●苗穂基地4月OPENhttps://www.instagram.com/naebo_base/プロジェクト〇9月10日(日)「筝のおうちにいらっしゃい!~楽器作りから演奏まで~」https://piyopiyoarts.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/activity/koyonouchihttps://youtu.be/w79dCckrWos〇おどる時計台 2023年8月12日13日~参加型パフォーマンスツアー、それと音楽とダンスの詩~https://fb.me/e/4EC0eVQCD〇ひよこアーツアートに関わる若手のキャリアを知ったり広めたりし、社会とつなげ、より多様な人が多様な方法で芸術に関わって生きていく創造環境作りを目指しています。私たち自身が、目指す方向ややるべきことを模索しながら人生を歩むひよこのような存在です。「アートとは何か?」という対象自体にも問を向けながら、イベント企画やインタビュー活動をしています。https://piyopiyoarts.com/路上写真賞https://piyopiyoarts.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/activity/event/アートとキャリアに関する多世代交流会https://www.facebook.com/events/455804993357021/?ref=newsfeedげいじゅつ職レポ隊ぴよぴよBYひよこアーツ美術大学・芸術大学・音楽大学の学生は卒業後、どんな生き方をしているのでしょうか?職レポとして、芸術に関わる方の生き方やキャリアをレポートします。Instagramはこちらhttps://www.instagram.com/piyopiyo_arts/〇HAUS Hokkaido Artists Union Studieshttps://haus.pink/〇のぞいてみよう、でんちゅうさんちの芸術っ子東京谷中の旧平櫛田中邸を舞台に、芸術っ子が手がける表現と、そのプロセスを共に味わっていただく回遊参加型パフォーマンスです。https://www.youtube.com/watch?v=yTBGpHDonk4略歴アートマネージャー、時々プロデューサー。HAUS/ひよこアーツにて主な活動を行う。作品や表現が生まれる過程やアーティストの存在そのものに魅力を見出して企画を行う。近年は相談支援にも関心を抱き、アート専門のキャリアコンサルタント的役割を志す。1998年兵庫県生まれ。幼少よりピアノと絵画に取り組む。高校時代、演劇づくりを体験し、参加者を引き込む企画とは何かを考え始める。2021年東京藝術大学音楽環境創造科を卒業。在学中はアートマネジメントを学び、アーティストが行う子供向けワークショップの展開を研究した。2018年~2020年 「あの曲のなまおと音楽会」と題して東京都足立区内の小学校ででピアノ、筝の音楽会を行う。2021年 旧平櫛田中邸を舞台とした回遊参加型パフォーマンス「のぞいてみよう、でんちゅうさんちの芸術っ子」を企画。2021年 キャリアや生き方に関するアーティストインタビュー「げいじゅつ職レポ隊ぴよぴよ」を始動。2022年 アート企画団体ひよこアーツを立ち上げ、「お隣さんはアーティスト」、「路上写真展」等を開催。その他、他団体との提携ワークショップを開催。現在、札幌市に拠点を置き、Hokkaido Artists Union Studiesメンバーとして活動を行っている。Messageアーティストはなぜアーティストになったのでしょうか。私にとって彼らは、自分のやりたいことを貫き、時に社会の様々なルールやしがらみに柔らかく立ち向かいながらサバイブしてゆく人々です。独自の関心やこだわりをもって作品に向き合う過程はとても魅力的で、しかし様々な困難が伴います。それが可能になる社会なら、きっともっと多くの人が幸せに暮らせると思うのです。連絡先・SNShttps://www.facebook.com/yuuurarinhttps://www.instagram.com/yurarirarirari/yuuurarin■gmail.com(■→@)https://twitter.com/YURARIN95
Artist Tree yama_me(やまメ) ライブペインティング、アクリル絵具、パステル、札幌市在住。|空間から想いを縒り合わせ、精密な線と優しい色使いで描く、静と動の表現者。|イベントでライブペイントしたり、楽器や陶器に絵を描いたり、フライヤーイラストを描いたりしています。|ちゃまめ楽団:アンデス25F演奏(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree略歴札幌大谷短期大学 専攻科 美術専攻 デザインコース 修了・『サッポロシティジャズ2007』 :オフシャルデザイナー・イオンモール札幌発寒 専門店街『ライブペインティング』:壁画制作・[日本古典SF研究会]正会誌 『未来趣味』:表紙イラスト・栃木県さくら市市制10周年オペラ『雨情とひろとお月さま』:舞台背景画・hand to heart 雪華 in 新千歳空港:ライブペインティング・おたるBookArtWeek…などhttps://www.instagram.com/yama_me/https://www.threads.net/@yama_mehttps://www.facebook.com/yamame.arthttps://yama-me-mo.blog.ss-blog.jphttps://www.youtube.com/user/yamamemix
Artist Tree 高田陽子 穴アキ絵画、日本画、沖縄、札幌、北海道、命ぬ芳さ、素材と表現、膠、野良、絵描き札幌市出身。現在は沖縄県で制作活動をしています。 2018年に一度札幌のギャラリー門馬さんで個展を開催しました。毎年北海道平和美術展に参加しています。 今は沖縄での活動が中心ですが、北海道と沖縄、2拠点に発表の場を広げて行きたいと思っています。お知らせ来たる2024年2月5日から29日まで、沖縄県浦添市港川レストランrat&sheepにて8回目になる個展『穴アキ絵画のすゝめ』を開催致します。2022年秋から2024年初頭に制作した作品を展示します。穴アキ、アナアキ、アナーキー??絵画の世界からちょこっと踏み外した作品、展示空間を作り出したいと思います。こちらの展示は沖縄での開催ですが、また札幌で展示会を開くぞ!と、息巻いております。現在友人と画策中ですので進展次第、情報を発信していきます。よろしくお願いします。最近の作品紹介天網恢々(てんもうかいかい) 直径約1100mmキルト綿、ジェスモナイト、岩絵具、金泥部分写真(午前中撮影)森の仔ら(もりのこら)キルト綿、ジェスモナイト、岩絵具展示風景根蔕(こんたい) 直径約1100mmキルト綿、ジェスモナイト、岩絵具部分写真(日中撮影)連絡先takadayoko@nibihi.net略歴1979年 北海道札幌市生まれ2003年3月 東北芸術工科大学 芸術学部美術科 卒業2004年3月 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部研究生卒業2006年3月 沖縄県立芸術大学 大学院 修了現在 沖縄県宜野湾市にて制作活動中 野良絵描き・個展2018年2月 『高田陽子展』芸工大アートウォーク2018 / 銀座K’sギャラリーan2018年5月 『高田陽子展-微晶 ちいさなたからもの-』札幌 ギャラリー門馬ANNEX2018年8月 『高田陽子展-森のひとかけら-』那覇 古書の店 言事堂2019年2月 『高田陽子展-やわらかな森-』 ART-LINKS 2019 / 銀座K’sギャラリー2020年4月 『ぬちわらい-命笑-』 浦添 rat&sheep2021年4月 『微と生きる 微に生きる』 浦添 rat&sheep2022年10月 『モザイクの中を生きる』 浦添 rat&sheep・直近のグループ展2020年12月 『沖縄アジア国際平和芸術祭』キャンプタルガニーアーティステックファーム2021年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2022年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2022年12月 『生きるー次のー50年へ』南城美術館2023年1月 『K’sギャラリーに集う作家たち展』銀座K’sギャラリー2023年5月 『物語の始まり』展 chabitan art space2023年6月 『crossover』 展 香港 アートセンターJCCAC2023年6月 『18人の表現者たち展』銀座K’sギャラリー2023年7月 『カヤート展』長野 萱アートコンペプレイベント2023年11月 『素材と表現」展 キャンプタルガニーアーティステックファーム
Artist Tree 小川しおり 演劇 制作 役者 ケータリング14歳の時にやまびこ座劇★youthに参加し演劇に関わり始め、18歳からは札幌ハムプロジェクトに所属。4年在籍し退団、その後22歳(2014年)の時に米沢さんと出会いfireworksに入団。ハムプロジェクトにいたときの繋がりや経験を活かし、旅公演・制作・音響オペ等担当したりしています。 fireworksでは役者もやります。ハムプロ在籍中、全体興行にて屋台を担当していたので、fireworksに入ってからも屋台やケータリングなどやらせてもらっております。 30人程度のご飯ならさっと作れます。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 平中まみ子(まみこし) イラスト、グラフィックレコーディング、タイポグラフィ、グラフィックデザイン、札幌、1992年生まれ。札幌在住。 まみこしと呼ばれています。 イラストレーター、グラフィックレコーダー、グラフィックデザイナー等々、「絵と文字を描く」ことを主軸に、会社に勤めながら色々な活動をしています。 (2023年1〜9月までは無職の予定です) 2017年から少しづつフリーのお仕事も頂いています。オリジナルグッズの制作、グループ展への参加等もしています。 グラフィックレコーディング、webデザイン、動画編集は勉強中です。主なWORKSHAUS SURVIVAL AWARD 2022公募パンフレット(イラスト、文字、グラフィックレコーディング、表紙デザイン)「ハウス・サバイバル・アワード2022」のパンフレットのイラスト・文字・グラフィックレコーディングを描かせて頂きました👨🏻🎨パンフレット用に描いたイラストやグラフィックレコーディングは、こちらのページにも散りばめられておりますので、よろしければ御覧下さい。https://haus.pink/archive/2022/survivalaward/イラスト・文字|平中まみ子デザイン|草梛 亮文責・編集|HAUS銭湯×グループ作品展「愛と湯展 〜+1℃をまとって〜」(タイトルロゴ、メインビジュアル、DMデザイン、グッズデザイン、作品出展)銭湯を愛する大学の後輩よりお声がけ頂き、銭湯をテーマにしたグループ作品展に参加しました。老若男女様々な方にご来場頂いては、銭湯談義に花が咲き、非常にホカホカとした空間に仕上がりました。Instagram@i_to_yu_tenTwitter@i_to_yu_ten私が出展した作品や、制作したグッズの一覧はこちら自主制作ZINE「えほん」「えっ(そうなの?知らなかった!)」「え〜(ヤダなー)」等々、「え」は一言で様々な感情を表現出来る言葉です。そのあらゆる感情の「え」をひたすらにレタリングで表現し、一冊のZINEにしました。ぜひ声に出して読んでいただきたいです。※2016年にNEVER MIND THE BOOKSにて手刷りで販売したものを2018年に再編集・製本し、 同イベントにて再販しました。2016年に制作したものは、Sapporo Art Directors Club 2016で入選しました。(全24ページ/モノクロ)略歴1992年 北海道札幌生まれ2015年 札幌市立大学デザイン学部卒業2015-2022年 札幌市内でアルバイトや正社員を転々としながら、創作活動に励む2023年 webデザイン・動画編集の勉強に専念するため無職となる。(創作活動は継続中)→目標は10月にwebデザイナーとして転職すること。主な展示・イベント参加歴2012.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「じてん」2012.09 奔別アートプロジェクト20122013.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「へんたい」2013.09 奔別アートプロジェクト20132014.02 札幌国際芸術祭2014トーク&レクチャー3 グラフィックレコーディング2014.04 第3回武邑塾 グラフィックレコーディング2014.05 ほくせんギャラリーivory noumenonグループ展「め」2014.08 そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト20142015.02 品品法邑 上遠野敏と愉快な仲間達展2015.02 石炭博物館再生シンポジウム グラフィックレコーディング2015.03 卒業修了研究展「清水沢階層録」2015.06 JR清水沢駅 個展 「石炭回想録」2015.07 ART-MANgallery Exhibition 夏展2015.09 そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト20152015.09 500m美術館「SAPPORO ART MAP 3」ART-MANgalleryブース2016.07 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2016」出展 (アオタマオ)2016.11 大通美術館 JAGDA HOKKAIDO POSTER EXHIBITION 20162018.09 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2018」出展2021.10 space1-15内 レンタルスペース307 「愛と湯展 〜+1℃をまとって〜」2023.10 札幌テレビ塔「NEVER MIND THE BOOKS 2023」出展
Artist Tree 佐藤みきと(Mikito Sato) 舞台 俳優 ナレーション 演劇 朗読 イラスト イラストレーター 絵本作家 4コマ漫画 グラフィックデザイン 宣伝美術 絵本 映画俳優/イラストレーター/絵本作家/グラフィックデザイナー「座・れら」という札幌の劇団に所属。 イラスト制作や絵本など作っている。イラストはシンプルでユーモアのある可愛らしいに定評がある。 舞台の宣伝美術など、グラフィックデザインもする。 宣伝美術イラスト映像出演https://youtu.be/4CNTrn0yF0Y?si=beKIQS-DvxzZY4jkhttps://youtu.be/3DvFRHpKUQM?si=5m497omZCq2-K3cJお知らせ連絡先 mikito3art@gmail.com略歴埼玉生まれ、北海道育ち。江別市在住。北海道芸術デザイン専門学校産業デザイン学科卒業。2016年座・れら 入団。2018年〜2021年 東京で活動2021年〜 札幌を拠点に活動。専門学校卒業後、数多くの舞台に出演。また、舞台の宣伝美術やイラストの制作など幅広く活動している。受賞歴第7回サンピアザ劇場神谷演劇賞大賞受賞
Artist Tree きたまり ダンス 振付家。 ダンス作品をつくる人。 https://youtu.be/ww4Ewmf8wRohttps://youtu.be/reTM0g-NjPc(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree連絡先https://ki6dance.jimdofree.com/HPのcontactよりご連絡ください。略歴きたまり振付家。1983年岡山県生れ。大阪育ち。2000年頃より舞踏家・由良部正美の元で踊り始めた後、2001年~05年まで千日前青空ダンス倶楽部のダンサー(芸名・すずめ)として6カ国13都市の公演に参加。2002年からソロ活動を開始し、2003 年よりダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI 主宰。2006年京都造形芸術大学 映像・舞台芸術学科卒業。以後、京都を拠点に国内外で多くの作品の上演を行い、「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD2008」“オーディエンス賞”「横浜ダンスコレクションR2010」“未来にはばたく横浜賞”受賞。2013年-15年に総勢100名以上のアーティストがジャンル・バックグラウンド・世代の境界を超えて参加した、作品のクリエイションを通じて、関西のダンスシーンの活性化と、舞台芸術における身体の可能性の探求をめざす実験の場「Dance Fanfare Kyoto」を企画運営。近年は作曲家、グスタフ・マーラー全交響曲を振付するプロジェクト(『TITAN』『夜の歌』2016*「平成28年度文化庁芸術祭賞」関西舞踊部門“新人賞”受賞、『悲劇的』2017、『復活』2019)や、劇作家、太田省吾の戯曲を舞踊化するシリーズ(『老花夜想/ノクターン』2021、『棲家』2022)をはじめるなど、ダンスと他分野の表現を扱いながらジャンルを越境した多岐にわたる創作活動を展開。2022年夏より札幌在住。 ソロダンス『MUSUME-Dojoji』にてTGR2022(札幌劇場祭)"特別賞”受賞。2023 年度よりセゾン文化財団セゾン・フェローⅡ。他、2000-2020年の詳しい素性はhttps://note.com/ki6dance/
Artist Tree 藤原千尋 油絵 肖像画 般若心経ArtStudio Chipper! 江別市在住。 絵を描いたり、立体をつくってますポートレイトプロジェクト: モデルさんに1時間座ってもらって描いています。完成まで(1時間×5回)、音楽を聴いたり、ポツポツとおしゃべりしています。般若心経: 母が亡くなったのをきっかけに描き始めました。日に日に弱っていく母の背後に見えた大きな真っ赤な火柱と、お坊さんのお経。ともだちハウス: 東日本大震災直後から作り始めました。豊かで安全な生活を願っています略歴山形県生まれ 江別在住北海道女子大学人間福祉学部(現北翔大学)卒業。介護福祉士として働く。ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校(アート)卒業。
Artist Tree 池田優香 演劇、舞台芸術、パフォーマンス、歌、鍵盤楽器、執筆、ジャズヒップホップダンス、ヨガ、ドライフラワー、メイクアップ、映像編集96年生れの舞台俳優。 他者の言葉を発語する難しさと日々格闘中。演劇問わずさまざまなジャンルのアーティストとともに、「劇場」から世界をちらっと覗くような作品をつくっていきたいです。歌うことが好きで、毎日おうちで歌っています。街で一緒に歌ったり演奏したりする仲間を探しています。 書くことも好きで、気ままに「劇評」や「戯曲」や「エッセイ」のようなものを書いては、公開したり、しまっておいたりしています。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree連絡先cantabile.ike@gmail.com略歴1996年 札幌市生れ高校生から、札幌の小劇場演劇に客演として出演2015年 東京学芸大学表現教育コース入学ままごと×パルテノン多摩『あたらしい憲法のはなし』に出演するなど、大学外で演劇活動を続けながら、パフォーマンス研究ゼミに所属し、演劇問わずさまざまな舞台芸術とその歴史について学ぶ2018年10〜3月イギリス、マンチェスターへ単身渡英帰国後も演劇活動や短編映画出演を続けながら、卒業論文「札幌の演劇について」を執筆し、卒業2020年 札幌に拠点を移す。ジャンルや形式にとらわれず、そのときにやりたいこと・やるべきことをどのように現象させるのがおもしろいのかを常に考えながら創作を続けています。お知らせ今年の秋ごろに、なにかやろうと目論んでいます。https://www.youtube.com/embed/jrexGToz5Xw
Artist Tree 渡辺たけし 劇作家、演劇、演出家、インタビューアー、インタビュー、数学、教職員、学校、HAUS、蘭越、蘭越演劇実験室後志管内蘭越町在住。 中学校数学教員 劇作家、演出家、インタビューアー(見習い)。 地元蘭越や札幌や白老で作品を作っています。 最近の活動『北海道短編エンゲキ祭’23~明日、あの子が会いに来る~』で短編を上演します。【蘭越演劇実験室上演作品】『くじらのしがい』脚本・演出:渡辺たけし出演:下島綾子 高丸真菜 中西晴菜 中西勇気 松田祥子〈あらすじ〉鯨が死ぬと、死骸の周りには新しい生態系が生まれるのだそうです。そんなことを考えていたら、亡くなった父に、ちょっとした秘密があったことが判明しました。そんなお話しです。【会場】演劇専用小劇場BLOCH(札幌市中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1階)【料金】※いずれも前売り料金 当日券は大人・学生ともに一律下記金額の500円増しです。〈見放題券〉※いつでも、何回でも観劇可能です。前売りのみ大人・学生一律5000円(限定5組)〈1ブロック券〉大人2000円、学生1500円〈2ブロック券〉※日をまたいでの予約が可能です大人3000円、学生2000円〈1日通し券〉※日をまたいでの予約はできません。大人3500円、学生2500円【蘭越演劇実験扱い 予約フォーム】https://www.quartet-online.net/ticket/fireworks2023tanpen?m=0iaeaia【お問合せ】劇団fireworks070-5601-2248ticket.fireworks@gmail-com北海道短編エンゲキ祭23公式ホームページ過去作品2022年に蘭越演劇実験室で上演した「note」の戯曲2021年にトビウ芸術祭上演した「今日も夕げにのろしが上がる」の戯曲ホームページhttps://rankoshidrama.jimdofree.com/連絡先Facebook:facebook.com/takeshi.watanabe.0525Twitter : https://twitter.com/watanabee1Instagram:https://www.instagram.com/pooboo71/e-mail: pooboo71・;・gmail.com(・;・を@に)略歴1971年 北海道小樽生まれ1996年 北海道で中学校教員として勤務し始める あわせて作品づくりも始める主な参加作品2022年 蘭越演劇実験室「note」脚本・演出(札幌bloch、蘭越町)Sapporo DanceCollective「My Foolish Mind 」(札幌、蘭越町)Sapporo DanceCollective「カタパルト」ドラマトゥルク(札幌コンカリーニョ)2021年指輪ホテル 「ポトラッチ」ドラマトゥルク(白老町「蔵」)トビウ芸術祭「今日も夕げにのろしが上がる」脚本(白老町)トビウ芸術祭「シラオイ・ タウンページ・コンピレーション」作品制作(白老町)2020年トビウ芸術祭「白老夜話」脚本・演出(白老町)INDEPENDENT:SPR20「遊泳」脚本・演出(札幌コンカリーニョ)Sapporo DanceCollective「さっぽろ文庫101巻 『声』 」ドラマトゥルク(札幌コンカリーニョ)2019年西区住民参加温故知新音楽劇「新・オシャレな果実」脚本(札幌コンカリーニョ)トビウ芸術祭「雁月☆泡雪」脚本・演出(白老町)トビウ芸術祭「トビウ小7年2組」企画(白老町)蘭越演劇実験室「YUKINOONNA」脚本・演出(札幌コンカリーニョ、蘭越町)蘭越演劇実験室「ゆきおんな」脚本・演出(ニセコ町Ice Village)それより以前の参加作品はかいつまんで・・・2018年NPO法人コンカリーニョ「オールド・ブラック・ジョー」脚本(札幌コンカリーニョ)2017年札幌国際芸術祭2017 市電プロジェクト×指輪ホテル「Rest In Peace, Sapporo~ひかりの街をはしる星屑~」ドラマトゥルク(札幌市)2012年 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2012テスト・サンプル02「キオク REVERSIBLE」出演(新潟県)
Artist Tree 田中春彦 演劇、アクション1989年5月8日生まれ 東京出身、大学から北海道に移住する。北海道大学演劇サークル「劇団しろちゃん」に所属する一方、劇団ひまわり札幌養成所に入団して、演劇活動を始める。2013年から仲間と演劇ユニット「わんわんズ」を結成。 以降、わんわんズでの公演や演劇祭での脚本、演出、出演の他、他劇団への客演も多数。 わんわんズでは、アクションと演技の融合を目指して、身体を使った舞台づくりを行っている。 演劇に触れたことのない人たちに演劇の魅力を知ってもらうため、上演場所は劇場にとどまらず、お祭りや学校にもその範囲を広げている。 オリジナルヒーローショー「もじゃキング」は、大人も子どもも楽しめるヒーローショーとして人気である。 2020年からは、市内の小学校・幼稚園・保育園で、劇仕立ての交通安全ショーも行っている。また、札幌市内のプロダクションや専門学校で、演技講師としての活動も広げている。 わんわんズでは、2023年より「One_class」という教室を開講し、 「演技」や「アクション」の他、「バク転」や「親子対象クラス」なども開講しているしている。【主な活動歴】 〈舞台〉 わんわんズの本公演(第1回~第5回) 教文短編演劇祭(2014年~2016年) など〈客演〉 2010年 ・劇団TPS(現札幌座)『ペール・ギュント』 2012年 ・札幌座『ディヴィッド・コパフィールド』 2013年 ・intro『わたし-THE CASSET TAPE GIRLS DIARY』 ・Water33-39(現、清水企画)『友達』 2014年 ・劇団ひまわり『オズの魔法使い』 2016年 ・さっぽろ雪まつり『さっぽろ 冬物語』 ・風蝕異人街『疫病流行記』 ・札幌座『注文の多い料理店』 2017年 ・BLOCHプロデュース『トキハナ』 など〈テレビドラマ〉 2019年 HTB開局50周年記念ドラマ『チャンネルはそのまま!』〈WEBドラマ〉 2015年 北海道新幹線開業記念『一本木峩朗の事件簿』主演〈他メディア〉 2019年~ 『い〜キタ〜いいべさ北海道』(YouTubeライブ配信、月1回放送) レギュラー出演お知らせhttps://twitter.com/mojya_haru【One_class開講中!】わんわんズでは、楽しく表現を学べる教室を開講しています。クラスは「アクション」「バク転」「演技」「親子」の4種類。各クラス、毎月1回開講です。【お申し込みフォーム】<アクション・バク転・演技>https://forms.gle/f552AqawxApdxmu27<親子>https://forms.gle/PNbj1CLTfSHSVCqP9詳しくは、HPをチェックしてください!わんわんズ - わんわんズ公式WEBサイト (one-ones.com)クラスの様子はこちら!【出演情報】『北海道短編エンゲキ祭’23~明日、あの子が会いに来る~』主催:劇団fireworks【開演日時】※開場は開演30分前です7/15(土)13:00、15:30、18:007/16(日)13:00(わ)、15:30、18:00(わ)7/17(月)12:00、14:30(わ)、17:00※(わ)=わんわんズ上演回【わんわんズ上演作品】『人の命に関わる話』脚本・演出:田中春彦出演:田中春彦、石川哲也、由村鯨太〈あらすじ〉道端に置かれたひとつの箱。なんで、こんなところに置いてあるんだろう?中には何が入っているんだろう?何か、危険な物でも入っているんだろうか?だとすると、あんまり近づかない方がいいんだろうか?そんなことを考え始めると、キリがないんですねえ。【会場】演劇専用小劇場BLOCH(札幌市中央区北3条東5丁目5岩佐ビル1階)【料金】※いずれも前売り料金 当日券は大人・学生ともに一律下記金額の500円増しです。〈見放題券〉※いつでも、何回でも観劇可能です。前売りのみ大人・学生一律5000円(限定5組)〈1ブロック券〉大人2000円、学生1500円〈2ブロック券〉※日をまたいでの予約が可能です大人3000円、学生2000円〈1日通し券〉※日をまたいでの予約はできません。大人3500円、学生2500円【わんわんズ扱い 予約フォーム】https://www.quartet-online.net/ticket/fireworks2023tanpen?m=0egfjfd【お問合せ】劇団fireworks070-5601-2248ticket.fireworks@gmail.com連絡先twitter:@mojya_haruFacebook:田中春彦mail:tanakaharuhiko0508@yahoo.co.jp略歴1989年5月8日生まれ東京出身、大学から北海道に移住する。北海道大学演劇サークル「劇団しろちゃん」に所属する一方、劇団ひまわり札幌養成所に入団して、演劇活動を始める。2013年から仲間と演劇ユニット「わんわんズ」を結成。以降、わんわんズでの公演や演劇祭での脚本、演出、出演の他、他劇団への客演も多数。わんわんズでは、アクションと演技の融合を目指して、身体を使った舞台づくりを行っている。演劇に触れたことのない人たちに演劇の魅力を知ってもらうため、上演場所は劇場にとどまらず、お祭りや学校にもその範囲を広げている。オリジナルヒーローショー「もじゃキング」は、大人も子どもも楽しめるヒーローショーとして人気である。2020年からは、市内の小学校・幼稚園・保育園で、劇仕立ての交通安全ショーも行っている。また、札幌市内のプロダクションや専門学校で、演技講師としての活動も広げている。わんわんズでは、2023年より「One_class」という教室を開講し、「演技」や「アクション」の他、「バク転」や「親子対象クラス」なども開講しているしている。【主な活動歴】〈舞台〉わんわんズの本公演(第1回~第5回)教文短編演劇祭(2014年~2016年)など〈客演〉2010年・劇団TPS(現札幌座)『ペール・ギュント』2012年・札幌座『ディヴィッド・コパフィールド』2013年・intro『わたし-THE CASSET TAPE GIRLS DIARY』・Water33-39(現、清水企画)『友達』2014年・劇団ひまわり『オズの魔法使い』2016年・さっぽろ雪まつり『さっぽろ 冬物語』・風蝕異人街『疫病流行記』・札幌座『注文の多い料理店』2017年・BLOCHプロデュース『トキハナ』など〈テレビドラマ〉2019年HTB開局50周年記念ドラマ『チャンネルはそのまま!』〈WEBドラマ〉2015年北海道新幹線開業記念『一本木峩朗の事件簿』主演〈他メディア〉2019年~『い〜キタ〜いいべさ北海道』(YouTubeライブ配信、月1回放送)レギュラー出演https://twitter.com/mojya_haru
Artist Tree 本谷 裕子 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeVOICEエレクトロポップユニット minikyute 初代ボーカル(rio名義で活動2006年脱退)。2005年アルバム「souvenir」発売。アニメ ヘイ!ヘイ!シュルームのオープニング・エンディングテーマを担当。DANCE2015年より、コンテンポラリーダンスを始める。SapporoDanceCollective 、渡部倫子作品に参加。2023年よりソロ作品制作を開始。
Artist Tree 中塚有里 劇、演劇、芝居、俳優、札幌、散歩劇団清水企画所属。俳優。田舎の高校生だった頃、1997年旗揚げの清水企画(2006年からはWATER33-39として活動、2014年に劇団清水企画へと名称変更)に出会い、演劇部を立ち上げる。1999年より同劇団に所属し、以降全ての本公演に出演。散歩が趣味で、知らない土地を地元住民の振りしてふつうに歩くのが得意。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 玉川健一郎 ジャズ 福居良 SLOWBOAT ヴォーカル レッスン ライブ「玉ちゃんは出会った時から現在(いま)に至るまでボクの遥か先を行く歌い手だ」-近藤房之助 福居良の下で磨かれたジャズスピリット、バリー・ハリスとの出会いから学んだ繊細な歌心を併せ持つと評される。 札幌を拠点に日本各地でライブ活動中。希少な男性ジャズ・シンガーである。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせライヴスケジュール (Gig Schedule)◎6月これからのPick Up Live6/20 札幌『Slowboat』 with the EROS6/21 札幌『JAMUSICA』 with 山下ヤスシ(pf) 柳真也(b) 江藤良人(ds)6/22 旭川『じゃずそば放哉』 with 山下ヤスシ(pf) 柳真也(b) 江藤良人(ds)連絡先jazztama2008@yahoo.co.jp略歴「玉ちゃんは出会った時から現在(いま)に至るまでボクの遥か先を行く歌い手だ」-近藤房之助学生時代、近藤房之助らと出会いブルース、R&Bを歌う。2004年、日本を代表するバップピアニスト福居良との出会いをきっかけにジャズへ傾倒。札幌の"jazz live SLOWBOAT(福居の店)"でジャズ修行をスタートさせた。後、福居を通じ、ジャズ・レジェンド、バリー・ハリスに師事。福居の下で磨かれたジャズスピリット、バリー・ハリスとの出会いから学んだ繊細な歌心を併せ持つと評される。札幌を拠点に日本各地でライブ活動中。希少な男性ジャズ・シンガーである。2018年6月、ファーストCD「ON A SLOWBOAT」を発表。2021年10月、セカンドCD「Sings For You」を発表。また、ジャズ・スタンダードを歌いたい方へのボーカル・レッスンも行っている。
Artist Tree 西脇秀之 舞台、演劇、戯曲、演出、音響、札幌、北海道舞台の仕事してます。 演劇の台本書いたり、演出したり、演劇の講師になったりしてます。音響さんやステージマネージャーもやります。 現在、札幌市東区に在住。息子と奥さんと三人家族。 ___I work in the theater. Writing plays, directing, and teaching theater. I also work as a sound engineer and stage manager. Currently living in Sapporo City. A family of three with my son and wife.Info東区市民劇団オニオン座がお久しぶりの公演を行います。西脇は、演出を仰せつかっております。親子で楽しめる小作品を4つ並べて上演します。「お芝居玉手箱」と題して、コロナの前からずっとやっていたのですが、今回おそらく過去最高に楽しいです。お越し下さいませ。https://twitter.com/onionza2008/status/1660276808770789377* * *コロナ禍になって(おかげで?)、以前よりマイペースに仕事ができるようになりました。今、こっそりnoteを使って、頭の中を整理中です。お暇な時にでも、こっそり覗いてみてください。でも、思うところがあれば、こっそりじゃなくてコメントください。交流したいです。https://note.com/kaikisen/Bioもともとは舞台の音響さん。なりゆきで劇作、演出にも手を出してしまう。1992年より、劇団回帰線主宰。(最近はあまり活動していないです)2004年より、札幌市の劇場、養成所、学校、市民参加の舞台芸術活動、ワーックショップなどの講師を務める。また劇作家、演出として多くの作品を提供。【受賞歴】文化庁舞台芸術創作奨励賞佳作(戯曲『ホーム』)全国児童青少年演劇協議会奨励賞もう少し詳しい略歴は、こちら↓https://note.com/kaikisen/n/nd85ab7e8ea84YouTube活動の経緯、演劇、市民劇についておしゃべりしてます。お暇でしたら、こちら↓どうぞ。https://www.youtube.com/watch?v=592bealsmTo&t=7sBCCKS https://bccks.jp/user/140766これまでにかいた戯曲が何冊か読めます。ほんとは全部オープンにしたいんですけど、なかなか手が回らない。無料です。Works『最後の伝令』シアターZOO原案・榎本健一 脚色・菊谷栄 演出・西脇秀之『うそつきのした』やまびこ座作・演出 西脇秀之『どったんばったん写真館』えぽあホール作・演出 西脇秀之(過去の舞台写真を並べてみましたが、なんだかコメディタッチですね。喜劇ばかりやってるわけじゃないんですが、ぼちぼち増やします)ContactTwitter @kaikisenCompany演劇に限らずいろんな話題を雑食してます。note https://note.com/kaikisen/最近こっそりはじめてみました。演劇や文化について考えをまとめるために。E-mail kaikisen■mac.com(■→@)
Artist Tree 今村育子 わたしは「間(あいだ)」について関心から、明るい部屋から暗い部屋へ滲みでる光、ドアの隙間から漏れる光、ガラスの反射など、相対する関係の間に発生する光のグラデーションをモチーフにし、主にインスタレーションや写真作品を制作しています。文化、宗教、性別、年齢など多くの違いを抱えているわたしたちは、本質的にお互いを理解することは難しい状況に置かれています。その立場にならなければわかることができず、それは簡単に想像できることではありません。例えば子どもを産むことによる、女性の不自由さや社会の不寛容さは、わたしも自身が出産するまで、ぼんやりとしか捉えていなかったことに気づきました。誰もが同じ立場になることが出来ないとすれば、どのように見えないものに向き合い、知ることができるのか?わたしの問いはそこにあります。 光はおのおのの存在に覆い重なる柔らかな現象です。光のグラデーションは相対するものの間に現れる階調であり、相対する存在が歩み寄るなめらかな階段のようです。わずかな光や現象を能動的に知覚し、双方の間にあるグラデーションを丁寧に観察することがこの世界を捉える手がかりになると考えて作品化しています。Reflection room/反射する部屋2022年|インスタレーション|プリント、鏡、ガラス、電球ほか|12mのガラスケース2基に作品を設置https://www.imamuraikuko.com略歴2006年より美術家として国内外で展示を行い、光のグラデーションをモチーフにインスタレーション作品を制作している。主な展覧会に2022年「RIMOKON」Artothek,PLATFORM(ミュンヘン)、「Muroran Art Project」室蘭、2019年「第7回札幌500m美術館賞入選展」500m美術館(札幌)、2018年JRタワー・アートボックス授賞作家展「拡散した光彩たち」プラニスホール/札幌、2017年「家族の肖像」本郷新記念札幌彫刻美術館(札幌)、2016年「ともにいること ともにあること」北海道立近代美術館(札幌)、2014年「札幌国際芸術祭2014」500m美術館(札幌)、「AKARI reflection|ひかりの連鎖」モエレ沼公園 ガラスのピラミッド スペース2(札幌)、2011年「Living Art」札幌芸術の森美術館(札幌)など。2011年より札幌駅前通まちづくり株式会社へ入社し、「シンクスクール」「PARC」「パラレルミュージアム」などの企画やデザインを担当する。Eröffnung der Ausstellung Rimokon, Artothek München|2022むこうの部屋/Room Over There2018年|インスタレーション|木材、壁紙、電球ほか|w1000×h300×d500cmわたしのおうち|2006
Artist Tree 竹原 圭一 演劇、脚本、演出、ヒューマンドラマ、ワークショップ、相互理解、自然、開拓、町おこし、コミュニケーション、学生支援、学生、創作、アウトリーチ劇団RED KING CRAB代表 脚本家 演出家 俳優 ワークショップ講師 文化企画アドバイザー 学園祭や文化祭などの演劇創作アドバイザー 西野中学校演劇部 外部顧問 劇作家協会北海道支部会員 除雪作業員 2023年、何でも屋を開業 お仕事のご依頼、心よりお待ちしております!!問い合わせは下記へお願いします。 2022年12月15日〜18日 RED KING CRAB演劇公演「遭難」@生活支援型文化施設コンカリーニョご来場、誠にありがとうございました!!舞台セット設営までの動画を公開中!https://youtu.be/Yy5TUDHVIQ8お知らせ除雪代行いたします。札幌市内のカーポートやご自宅周辺の除雪を行います。ご要望の方は09070527030までご連絡下さい。ご要望に応じて、ワークショップを行います。ご希望の方は下記にお問い合わせ下さい!ワークショップの一場。この写真は学校の演劇部で行ったワークショップの一場です。中学校、高校、大学はもちろん、人と人とのやり取り、交流にご興味のある方々のご要望にお答えします。ワークショップの一場。身体を使うものや集団創作ならではのもの、シアターゲームなどを用いた体験型のワークショップとなっています。ワークショップの一場。目線を変えること。坐視について伝えている場面です。ワークショップの一場。笑い声が溢れる楽しい時間も。ワークショップの一場。一人では行えない演劇という創作の面白さを体験して頂けるプログラムとなっています。ご依頼お待ちしております!!連絡先twitter:https://mobile.twitter.com/K1TakechanmanFacebook:https://www.facebook.com/keiichi.takeharaホームページ:https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrabメールアドレス:k1.takechanman@gmail.com過去の戯曲:https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrab/galleryコロナ禍に過去に上演された作品の戯曲をホームページに掲載しました。ダウンロードして御覧下さい。ドラマリーディング「鈍行」:https://youtu.be/v0KWee8xHmQ 日本劇作家協会の企画で、コロナ禍で直接会うことがあまり良しとされなかった時期に、リモートで東京・北海道という異なる地域で活躍する俳優達が一同に介し、戯曲を読み、ゲストの方を交えて意見し合う、劇作家の戯曲のブラッシュを目的としたものです。第一線でご活躍されている劇作家鈴木聡さん、瀬古山美咲さんをゲストにお招きし、2020年に執筆した「鈍行」というワンマン列車車内を舞台にした作品のリーディングバージョンです。ラジオドラマの感覚でどうぞお聞き下さい。略歴劇作家・演出家・俳優。RED KING CRAB 代表。1988 年⽣まれ、札幌市出⾝。北海学園⼤学演劇研究会を経て劇団 NOLINE に参加後、2012 年より札幌近郊の居酒屋やバー、⾳楽ライブの幕間、ショーパブで⼀⼈芝居のパフォーマンスを⾏う。2013 年に倉本聰⽒による集団「富良野GROUP」の全国ツアーに照明スタッフとして初参加。同年「RED KING CRAB」を旗揚げ。翌 2014 年にシアターzooにて初の劇場公演を⾏う。主催公演、劇場企画公演を含め、RED KING CRAB の 10 本以上の作品で脚本・演出を務める。役者としては、富良野GROUP の 2016 年『屋根』・2017 年『⾛る』・2020 年『屋根』(公演中⽌) に参加。同 2020 年には、All Sapporo Professional Actorʻs SerecctionVol.1『虹と雪、慟哭のカッコウ〜SAPPRPOʻ72』(ドラマトゥルグ︓斎藤歩/札幌座、脚本・演出︓納⾕真⼤/ELEVEN NINES)や札幌座『フレップの花、咲く頃に』(演出︓斎藤歩、脚本︓⼭⽥百次/ホエイ/劇団野の上)などに出演。2022年、中学校演劇部の外部顧問、劇作家協会札幌支部の活動、西野中学校外部顧問、別団体への戯曲の提供やテレビドラマの脚本執筆、コミュニケーションワークショップの講師を行う傍らで、自己研磨を兼ねた週 6 日のリモートによる朗読批評会、月に数回の演劇ワークショップを開催中。2023年、除雪代行の仕事を開業。活動履歴【RED KING CRAB作品】第○回公演という記載はすべて RED KING CRAB 主催。シアターZOO 企画公演にも RED KING CRAB として参加。注記があるものを除き脚本・演出を行う。過去作品の戯曲の一部をホームページに掲載しています。ご覧下さい。https://redkingcrab.wixsite.com/redkingcrab/gallery2014年 6月 第1回公演『タイマン』: 脚本 / 演出 / 出演第1回公演「タイマン」のチラシあらすじ 真冬の北海道。一人の男が山中で凍死した。そしてその男は自分が亡くなる3日前の出来事を語りだした。旗揚げ公演。この時は、シアターzooさんに全面協力を頂き、舞台セットを完成させました。「タイマン」「我夢捨螺」「遭難」と、タイトルを変えて3度上演することになります。ただこの時は、まさかこの公演を3回やるとは思っていませんでした。俳優は二人。今回の「遭難」に出演して下さった戸澤亮君、再演時に出演して下さった湊谷優君もスタッフで手伝ってくれた最初の劇場公演です。同 11月 第2回公演『おだぶつ』:脚本 / 演出 / 出演 *札幌劇場祭 新人賞第2回公演「おだぶつ」のチラシ(表)第2回公演「おだぶつ」チラシ(裏)あらすじ 2014年秋、親父が太平洋にダイヴした。そして「お葬式」という親父の最後の舞台が始まった。2作目は、前回よりも、殺陣ありダンスありのエンターテイメントを盛り込んで作品を作りました。道東の根室市をモチーフにして作った「終活」に纏わる家族劇です。現代から約30年間の昭和・平成の歳月を経て変わって行く家族の関係を舞台上で表現しました。主要人物である父親はごみ収集作業員。現場を知るために何度もごみ収集の仕事をしていました。2015年 4月 遊戯祭 15~手塚治虫に告ぐ~出展作品『あすなろ』: 脚本 / 演出 / 出演*遊戯祭 15 最優秀賞遊戯祭15 チラシ当時の新聞「手塚治虫」さんがテーマの演劇祭でした。手塚治虫さんのことが知りたくて、当時手塚治虫さんのアシスタント業務をしていて、飲み友達だった方にお話を聞くことが出来ました。僕らと同じ若手だった頃の手塚治虫さんがどのようなことを考えて創作と向き合っていたのか。そんなことを考えて作品を創っていました。授賞式の一場。お話は、東京都椎名町にトキワ荘という漫画家の卵達が共同で生活したアパートがあったのですが、その斜向かいにコワレ荘という同じく漫画家の卵達が暮らしたアパートがあり、トキワ荘の多くは独立して著名な漫画家になった一方で、コワレ荘の住人は自身の夢を諦めて行く。トキワ荘の陰影となった本作。同 11月 第3回公演『(baka)』脚本 / 演出 *札幌劇場祭 2015 企画賞第3回公演「(b'aka)」チラシ(表)第3回公演「(b'aka)」チラシ(裏)あらすじ この物語は最愛の人をなくした とある男の自立の物語。当時の新聞記事舞台セット 派遣会社株式会社アポロ作品を創る時、僕は舞台となる街の地図を作ります。その地図を見ながら役者の皆さんとその街でどんなことがあるかを話合います。RED KING CRABとしては初の具体的なセットのある舞台。生活介護事業の方々や就労支援施設の方々、多くの関係者の皆さんからお話を伺い、「障がい」「バカ」という言葉を真正面から掘り下げて創りました。2016年 6月 シアターZOO 特別公演 『我夢捨螺』脚本 / 演出シアターzoo提携公演「我夢捨螺」チラシ(表)シアターzoo提携公演「我夢捨螺」チラシ(裏)あらすじ 山中で一人の男が凍死した。氷点下何十度の突風が吹き荒れる山中にたった一人取り残された男。そして男は自分が亡くなる3日前の出来事を語り出した。当時の新聞記事舞台となるのは使われていない山小屋。実際に登山をし、現地の様子を取り入れて作品を作り直しました。この再演時にラストシーンが変わりました。ちなみに上演日は真夏です。汗まみれの役者達。ただただ感謝でした。同 11月 第4回公演『カラッポ』脚本 / 演出第4回公演「カラッポ」チラシ(表)第4回公演「カラッポ」チラシ(裏)あらすじ 想像してみて下さい。数十年後の自分の姿を。おじいさん、おばあさんになった貴方は何をしていますか?とある島にあるスナック秋桜が舞台のお話です。お話には、「忙」を象徴する人物と、「忘」を象徴する人物が登場します。若年性アルツハイマーと向き合う人々の交流を描きました。2017年 6月 生活支援型文化施設コンカリーニョ主催ペアプレイパレード出展作品『アスロン』脚本 / 演出アスロン 宣伝チラシ短編作品。人生をトライアスロンに見立てて創作しました。幼少の頃を水泳、青年期を自転車、そして成人期をランニングという3つの象徴的なシーンが登場します。二人登場人物が出てきますが、二人は同一人物という設定でした。サラリーマンが日々走り続けるラストシーンでした。同 12月 シアターZOO 企画公演『ガタタン』脚本 / 演出特別公演「ガタタン」チラシ(表)特別公演「ガタタン」チラシ(裏)舞台は現代の炭鉱町にある銭湯でした。町に残り仕事や婚活を続ける男達。町に戻って結婚をする者達。戻りたいけど戻って来た男。家族とは岩見沢炭鉱の記憶推進事業団の方々をはじめ、多くの炭鉱マンへの取材を重ねて創作しました。人物の履歴を掘り下げて作品を作ります。取材で訪れた赤平炭鉱2018年11月 シアターZOO 企画公演 特別公演 2018『ガラスの動物園 The Glass Menagerie』 (原作:T.ウィリアムズ) :脚色 / 演出 *札幌劇場祭 2018 審査員特別賞特別公演「ガラスの動物園ーThe Glass Menagerieー」チラシ(表)特別公演「ガラスの動物園ーThe Glass Menagerieー」チラシ(裏)舞台の一場。初の既成台本での作品。テネシー・ウィリアムズは世界的に有名な劇作家の一人です。舞台の一場。このお話は、思い出の劇と冒頭で説明するように、回想シーンによって構成されています。舞台の一場。舞台の一場2019年 9月 シアターZOO 企画公演 女と男、座面と境界 出展作品『尋ねもの』脚本 / 演出シアターzoo企画公演「女と男、座面と境界」チラシ(表)シアターzoo企画公演「女と男、座面と境界」チラシ(裏)稽古方法について。稽古を時折、外でやっていました。舞台となる場所に極力近い環境に身を置くことで、五感を通して受け取ることが出来ることを増やして行きます。短編作品。落とし物をした女と落とし物を拾った男の旅の一場を描いたお話です。同 11月 第5回公演『ありあけ』脚本 / 演出*札幌劇場祭 2019 大賞第5回公演「ありあけ」チラシ(表)第5回公演「ありあけ」チラシ(裏)あらすじ 終戦後の創成川東の町工場を舞台に巻き起こる再会と別れの物語。作品の一場。戦後の貧しかった時代、おもちゃを作る町工場を舞台のお話。改革か慣習か、経済か人付き合いかという、仕事をしていく上で何を大切にするのかを観客に問い掛ける作品になりました。創成川東は当時、工場や商店が軒を連ねる「ものづくりの町」でした。職人や商人の流出が相次いだ激動の時代が舞台です。舞台となる創成川東には、かつて新渡戸稲造さんが設立した遠友夜学校がありました。登場人物達は、そこの卒業生という設定です。社訓にはそのことを象徴する「世のため人のため」という文字が書かれています。作品の一場作品の一場戦後の作品を作るに当たり、戦時中のことを調べねばならないと、九州の知覧町、大刀洗町に約一ヶ月間滞在していました。特攻隊で亡くなられた方々の遺書に何が書かれていたのかを自分なりに理解すること、そして出会ったお爺さんに依頼された自身が乗っていた飛行機を見て来ること、亡くなられたご友人の方のことを調べて来ることがミッションの旅でした。そういった創作過程の断片が作品にはあります。授賞式での一場。2020年10月 第6回公演『鈍行』脚本 / 演出第6回公演「鈍行」チラシ(表)第6回公演「鈍行」チラシ(裏)あらすじ 真冬の北海道。とある山間部。廃線間際の路線を走るワンマン列車車内。車内の乗客は皆、思い思いに時間を潰し、目的地への到着を待っている。列車車内を舞台に、遅延によって生じた運転士と乗客の葛藤を描く密室群衆劇。キハ40系の車内を再現した舞台セット。廃線が続く北海道内の路線と列車に感謝と敬意を払い、創作しました。陸別鉄道の皆さんのご協力を得て、実際に鉄道を運転する稽古も行いました。舞台の一場。この作品は、いつかまた再演をしたいと思っています。その為により良い作品とするために劇作家協会のリーディングにも参加しました。2021年 2月 札幌演劇シーズン 2021-冬 参加作品『ありあけ』脚本 / 演出https://fb.watch/ierQE0RqBZ/作品の一場作品の一場2020年3月 INDEPENDENT:SPR出展作品「かさぶた」INDEPENDENT:SPRチラシ稽古の一場。コロナ禍で複数人が出演する芝居が難しいという思いの中で創作した作品です。心の傷について考察を深めて創りました。一人の俳優が開演し舞台に向かうまでの約30分間を描いたお話です。稽古の一場。見えない鏡を見ながらの演技になります。それぞれの化粧を何処に、どのように施すか。「俳優修業」というタイトルにするか悩んだ程、俳優の技量が問われる作品です。稽古の一場。実際にはないもの見えて来る。落語の要素を拝借し、登場人物は一人ですが、実際には複数の人物が登場する劇です。稽古の一場。劇が進むに連れて若かりし女性がお婆ちゃんになって行きます。稽古の一場。稽古方法は様々です。時に小さな会場で行う公演であってもこのような大きなホールで稽古を行うこともあります。同 10月 2021 DUO PROJECT VOL.5 出展作品『ギッチャ』脚本 / 演出短編作品。現役高校生二人による、自転車を盗まれた人と、盗まれた自転車に似た自転車に乗っている人との交流を描いたお話です。コロナ禍の学生達の話をたくさん聞いて創りました。作品を創る時は、よく絵を描いて役者達とイメージを共有します。同 12月 江別演劇プロジェクトWinds公演 『ありあけ』脚本 / 演出江別演劇プロジェクトWinds当時の新聞作品の一場。昭和20年代の札幌創成川東の町工場が舞台の作品です。カーテンコール。念願の地域に出向いての公演を実現しました。各地域担当者の皆様、これから先も公演のご要望がありましたら実施させて頂きます。ご連絡お待ちしております。2022年12月 RED KING CRAB演劇公演『遭難』脚本 / 演出/出演RED KING CRAB演劇公演「遭難」チラシ(表)RED KING CRAB演劇公演「遭難」チラシ(裏)当時の新聞野外稽古の一場。ICEMANSの竹中博彦さんのご協力を得て、アトリエで野外稽古を行いました。稽古の一場。稽古の一場。稽古の一場。稽古の一場。【外部活動】2014年 1月 富良野GROUP公演2014『マロース』:照明スタッフ同 8月 劇団fireworks『新訳 バウンティ』:役者2015年 1月 富良野GROUP公演2015『夜想曲』照明スタッフ同 8月 イレブンナインプレゼンツ dEBoo#1『12人の怒る男』:スタッフ/ 出演2016年 1月 富良野GROUP公演2016『屋根』:役者2017年 1月富良野GROUP公演2017『走る』:役者2018年 2月 富良野GROUPワークショップ公演『富良野警察物語~もしもあなたなら~』:役者同 6月 札幌座第55回公演『フレップの花、咲く頃に』:役者2020年 2月 All Sapporo Professional Actorʻs SerecctionVol.1『虹と雪、慟哭のカッコウ〜SAPPRPOʻ72』∶役者同 3月 富良野GROUP『屋根2020』(公演中⽌) :役者同 7月 札幌演劇シーズン 2020-夏 札幌座『フレップの花、咲く頃に』:役者2021年 6月 札幌北斗高校演劇部学園祭公演『あやかし』:脚本チラシ(表)コロナ禍に一人の学生からの依頼を受けて作った作品です。旧校舎を舞台に、総勢19名のキャストが織り成す群衆劇です。登場人物は学生とお化けしか出てきません。2022年 3月 富良野塾OBユニット公演2022『みずのかけら』:俳優2022年 9月 HTLプロデュース世界演劇名作劇場vol.1 ハロルド・ピンター作『料理昇降機ーThe Dumb Waiterー』:演出・翻訳HTL ハロルド・ピンター作 「料理昇降機ーThe Dumb Waiterー」チラシ(表)HTL ハロルド・ピンター作 「料理昇降機ーThe Dumb Waiterー」チラシ(裏)【メディア情報】2018年 5月 TVCM『ココカラ』:出演2019年 6月 北海道150年記念ドラマ『永遠のニシパ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~』:出演2021年 8月 TVCM ウィズハウス『にぎやかなことがとっても好きな人でした』:出演同 9月 『セイコーマート』 お天気フィラー:出演同 9月 NHK 札幌放送局 制作テレビドラマ 3ROOMS『最期の生配信』:脚本初のテレビドラマの脚本でした。生配信中のチャットルームが舞台のお話でした。主演の女の子が飛び降り自殺をしようとするのをネットの力で何とか止めようとするお話です。プロデューサー・ディレクター・ADの方と二人三脚、いや三人四脚で稽古方法から相談しながら作った作品です。
Artist Tree 小林なるみ 俳優 朗読 ナレーター 舞台 映画 歌 ラジオパーソナリティ ヴォイストレーニング高校卒業後、北海道拓殖銀行に勤務するも芝居をする時間を増やしたく2年で退社 1992年劇団回帰線の立ち上げに参加 現在も在籍先輩ナレーターの方から声をかけていただき 1993年よりAir-GFM北海道「奇想天外PM8」パーソナリティを担当 他、CMナレーション、ドラマ出演など舞台作品の出演と並行して活動する 劇団での活動のほか 新国立劇場芸術監督でもある宮田 慶子氏、 THE ガジラの鐘下辰男氏など 北海道内外問わず様々な演出家の作品に出演北海道で撮影された映画、呉美保監督「そこのみにて光輝く」「きみはいい子」出演 2020年5月NHKさっぽろ放送局制作ドラマ 3ROOMS「座敷笑死テレポート」出演 2021年2月よりLINE NEWS vision「そらぞら」全12話出演 映画「モルエラニの霧の中」「TOCKA〜タスカー」 2023年公開予定「過去負うもの」他切絵作家黒川絵里奈との「影絵と朗読の世界」や白老町で開催のTOBIU CAMPアーティストの一人として朗読 ギターと朗読ユニット"あわい” を結成作品の中に溶け込んで物語に寄り添えるような存在を目指すヴォイストレーナーとして後進の育成にも積極的に取り組んでいる朗読ライブなどの様子はこちらでご覧いただけます↓ "声の空間” https://www.youtube.com/channel/UCxm3chI77qjeXikU91O39yg (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先略歴
Artist Tree 徳山まり奈 喫茶店、カフェ、空間、人間、人文、哲学、演劇、展示、舞台喫茶こん(喫茶店経営) ヒュー妄(所属劇団)(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree自分が感じる重さと明暗しか信じたくないしそれは信じちゃいけないと思っている。消費社会化が進む中で、自らが好きなもの、自分にとっての価値を自分で決められることを取り戻したい。日常の中で心が動かされるものとの繋がりを研究をし、空気として表現。普段は喫茶店を経営をし、たまに舞台に関わる。喫茶店と寮のような存在でありたくて方法を探っている。今の喫茶店の物件が老朽化で使えなくなる可能性があると大家さんに言われているので、いい空間との出会いを探している。喫茶店に加え、寮や倉庫、稽古場や作業場を併設できるようなアクセスしやすい一軒家が理想。連絡先 cafe000con@gmail.com
Artist Tree 高木秀俊 グラフィックデザイン ロゴデザイン 筆文字 抽象画 短歌新潟県長岡市生まれ、札幌市在住。グラフィックデザイナーのかたわら、アート活動 を行う。 1999年に長岡造形大学を卒業、グラフィックデザインを学ぶ。2006年にセツ・モード セミナーを卒業。色や形、画面構成に開眼する。 2015年に個展「深呼吸を数える」を開催。2016年に個展「音は点になり、言葉は線に なる。句はタカチになり、歌は色になる。」、個展「SYSTEMATIC DOLL」を開催。 2022年に個展「Draw the Line」を開催。その他多数のグループ展に参加。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせイラストを担当した道の駅スタンプラリーブックが4月22日から販売されます。OCTOPUS BOY名義で、シーソーブックス様にグッズを置かせていただいております。連絡先Instagram@tacobozu略歴新潟県長岡市生まれ、札幌市在住。グラフィックデザイナーのかたわら、アート活動を行う。1999年に長岡造形大学を卒業、グラフィックデザインを学ぶ。2006年にセツ・モードセミナーを卒業。色や形、画面構成に開眼する。2015年に個展「深呼吸を数える」を開催。2016年に個展「音は点になり、言葉は線になる。句はタカチになり、歌は色になる。」、個展「SYSTEMATIC DOLL」を開催。2022年に個展「Draw the Line」を開催。その他多数のグループ展に参加。
Artist Tree 藤川駿佑 フライヤー、ポケット企画、チラシ、パンフレット、デザイン、宣伝美術、グラフィック、DTP、ピアノ、作曲、劇伴北海道札幌市出身。1999年生まれ。2021年より札幌を拠点とする劇団「ポケット企画」に加入し、劇伴音楽の作曲・演奏やフライヤーのデザインなどに携わっている。Works最近の活動2023年2月 ポケット企画第8回公演『おきて』宣伝美術/音楽/映像配信/制作2022年12月 さまてまぴ『酸いも甘いも全部キモ』宣伝ビジュアル制作2022年8月 ポケット企画『ここにいて、』@RANKOSHI LAB 2022(蘭越町) 作曲/演奏2022年3月 ポケット企画×あづき398共同公演『ゆうむすぶ星』@ アカルスタジオ(大阪府) 制作/音楽/宣伝美術(おうさか学生演劇祭vol.15 審査員特別賞「ベスト演奏賞」受賞)
Artist Tree 福井岳郎 フォルクローレ、南米音楽岐阜県出身。1990年から約2年間、ペルー・ボリビア・エクアドル等に滞在し、南米民俗楽器演奏を学ぶ。帰国後、フォルクローレグループ「ティンクナ」のリーダーとして、南米伝統音楽やオリジナル曲を中心に活動。これまでに自作CD「月の音、聴いている」「ツキノホ」「劇場にて」などアルバム8枚を発売。2005年から、劇団千年王國の音楽担当として、「イザナキとイザナミ」「君しかいない」「狼王ロボ」など7作品の作曲・演奏を行う。最近では、バロック音楽の中に南米リズムを取り入れた演奏や、手作りおもしろ楽器を使ったパフォーマンスが好評を博している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree公演のお知らせ福井岳郎フォルクローレコンサート「風が吹くわけ」日時:2023年5月21日(日)13時30分開場/14時開演会場:江別インターナショナルスクール多目的ホール(江別市野幌代々木町56-8)JR野幌駅から徒歩15分/駐車場あります出演:福井岳郎(チャランゴ、ケーナ、サンポーニャ、ギター、ヴォーカル)手島慶子(パーカッション)チケット:一般1,500円/小学生以下500円*道新プレイガイド(窓口・オンライン)でも取り扱いいたします。ご予約・お問合せ 090-9515-7229/tinkuna1126gakurou@yahoo.co.jp南米民俗楽器奏者・福井岳郎がお送りするフォルクローレ音楽のひととき。共演にパーカッションの手島慶子を迎えて、南米曲からオリジナル曲まで幅広くお届けします。***********「南米民俗楽器×マリンバ「やがて来る夜明け」日時:2023年7月8日(土)13時30分開場/14時開演会場:札幌豊平教会 礼拝堂(札幌市豊平区豊平6条3丁目5-15)地下鉄東豊線「学園前駅」徒歩4分会場の駐車場はご利用出来ません、お近くの有料駐車場をご利用ください。出演:福井岳郎(チャランゴ、ケーナ、サンポーニャ、ギター、ヴォーカル)、手島慶子(マリンバ)チケット:一般2,500円/中学生以下1,000円*道新プレイガイド(窓口・オンライン)でも取り扱い予定です。ご予約・お問合せ 090-9515-7229/tinkuna1126gakurou@yahoo.co.jphttps://twitter.com/tinkunagakurou【facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100006055055864【Youtube】https://www.youtube.com/@user-qc7wh3jz2g
Artist Tree 三木美智代 演劇、芝居、ダンス、モダンダンス、寺山修司、岸田理生、ギリシャ悲劇劇団 風蝕異人街 代表/女優/ダンサー 早稲田大学卒業。青年座研究所卒業後、東京での演劇活動を経て実験演劇集団「風蝕異人街」(現劇団 風蝕異人街)設立に参加。2005年より演出家・鈴木忠志氏による俳優育成プロジェクトに参加し、スズキメソッドを受講。鈴木忠志(SCOT)、宮城 聰(静岡舞台芸術センター)、中島 諒人(鳥の劇場)、ペーター・ゲスナー(うずめ劇場)、カステルッチ作品出演など劇団外でも活動。2012.13年と韓国に招聘され無言劇に出演。高校での講座、一般向けWS開催。ダンサー、振付家としても東京、横浜、大阪等で作品を発表。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 赤坂嘉謙 劇団清水企画所属 俳優(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 川島靖史 俳優 役者 舞台 映像 カルチャー2008年より札幌にて、市民劇団に入り、演劇活動をスタート。札幌には中々いない個性派俳優だと思っている。(自称)(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 三瓶竜大 ポケット企画、劇団清水企画、劇作、演出、俳優、ままならないこと、おせっかい2018年4月劇団清水企画へ俳優として所属。 同年11月ポケット企画を立ち上げ。 劇作家/演出家として活動している。 大学在学中にTGR札幌劇場祭 新人賞 全国学生演劇祭 最優秀賞 おうさか学生演劇祭 最優秀劇団賞 を受賞。お知らせ【札幌の若手演劇人のみなさんへ】札幌で活動するにあたって、若手でいろいろ話してみようの会を弦巻楽団の佐久間くんと開きます。ーここらで交流会しませんか?ーU-29でつながろうぜ!○日時2023.4.8(土)13:00〜18:00※途中入退場可○場所あけぼのアート&コミュニティセンター(予定)発端は、三瓶竜大(ポケット企画/劇団清水企画)と佐久間泉真(弦巻楽団)の雑談でした↓「なにかやるかは別として、演劇に関わることのできるつながりがあるといいなあ」「相談し合える環境がほしいですよねえ」「稽古方法とか運営方法とか共有したら良いのかなあ」「え〜わからん。」「・・・。」とにかく!楽しかったこととか、困っていることとか、続けることとか、ゆる〜く交流しましょう!堅苦しくない、持続可能な会を目指します。5月3日にはレッドベリースタジオでの交流会も予定しております!楽な気持ちでご参加ください。みなさまのご参加お待ちしております!!💮参加申し込みhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet-P_p1_tAVktwPf6dMb6NDSjHeH1hwxlU08PZZIB2viHsXQ/viewformご不明点はどしどしお聞きください!連絡先contact@pocket-kikaku.comtwitter @enngeki0313略歴2000年 3月生まれ。辰年。O型。高校生から演劇を始める。ポケット企画は今年で5年目。応援よろしくお願いします🤲
Artist Tree 桐原直幸 舞台、演劇、役者、俳優大学時代に長年続けたサッカーを辞め、ひょんなことから演劇を始める。 所属する劇団fireworksをはじめ、主催ユニット二度寝で死にたいズでは野外公演なども行う。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 加藤隼平(東京サムライガンズ) 演出、映像、デザイン、劇団、役者、お祭り、プロデューサー北海道函館市出身、1982 年生。高校在学中はバンド活動に力を入れ、道内での音楽活動を経て2003 年に俳優を志指し単身上京。2004年、主演映画デビュー。舞台・TV・CM 出演など役者としての様々な経験を生かし、主宰劇団「東京サムライガンズ」では、脚本・演出・出演・映像編集・音楽・デザインなどを手掛け、その一貫されたデザイン性の高さから初めて演劇を見た人でも見やすく飽きの来ない演出を得意とする。また、北海道文化財団主催舞台創造支援事業「ステージラボ・舞台工房」総合監修や、ロンドンブーツ1号2号の田村亮率いるお笑い芸人劇団「田村亮一座」との競演舞台では脚本・演出・デザイン・出演など、外部公演への参加も積極的に行っている。2022年に東京から函館市に活動拠点を移し、茅部郡森町の神社祭「ナニモシナイヲスルヒ」のプロデューサーとしても活動中。2022年難病ステージ5からの脱出成功!現在はUターンして函館在住。演劇・デザイン・動画編集を生業としています。よろしくお願いいたします♪https://www.youtube.com/watch?v=cQ4nhnMyyH4&t=2sお知らせ・冊子「函劇界」創刊号 発売中・デザイン担当の大沼ビール「HOPSHOWER」が全道のローソン他にて好評販売中連絡先Twitter@jumpeikatohInstagram@jumpeikatoh51略歴【MOVIE】『セカンドバージン』『ラブポリス』ユージ/ 役 『彼岸島』『ガッツ伝説~愛しのピットブル~』他多数【TV】MX『バカヂカラ』 若頭適性審査の仕掛人CX『麗しき鬼』 雨宮/ 役 他多数【CM】『NTTDoCoMo』『日本マクドナルド』『サッポロビール 道産素材』『アクエリアス ビタミンガード』『プレミアムモルツ』『東日本医療専門学校』 他多数【舞台】『多重人格探偵サイコ』島津役 (紀伊国屋サザンシアター)『幻に心もそぞろ狂おしの我ら将門』捨十役(紀伊国屋サザンシアター)『三人姉妹』トゥーゼンバフ役(紀伊国屋サザンシアター)『俺は君のためにこそ死ににいく』田端紘一役(靖国神社遊就館前特設舞台)他多数【声優】ドラマCD『ふたりじめ』 戦国夫婦物語ドラマCD 『残酷な揺り籠』 オーディオ舞台『テラキチ!』【ラジオ】『じゅんぺーの青春! ビッグスマイル!!』(FM 世田谷 2009年10月~)メインパーソナリティ【作・演出・デザイン・映像演出など】東京サムライガンズ1『ポジティブナルシスト』 作・演出・出演 2006年東京サムライガンズ2『LIFEGAME』 作・演出・出演 2009年東京サムライガンズ3『プレイフルネスデイズ』 作・演出・出演 2012 4 月東京サムライガンズ4『プレイフルネスデイズ2』 作・演出・出演 2012 11 月東京サムライガンズ5『さらば愛しきHAPPYEND.』 作・演出・出演 2013 5 月東京サムライガンズ6『嗚呼素晴らしきサラリィ人生』 作・演出・出演 2014 2月演劇ユニット ランニング「SOU-双・相・想-2」みゆき食堂×雨のち晴れ 総合演出東京サムライガンズ7『ART~愛とロマンと哲学と~』 作・演出・出演 2015 12 月ステージラボ2015『劇光カルメン』作・演出・総合監修 2015年 3月田村亮一座×東京サムライガンズコラボ公演『TENSAi』作・演出・出演 2015年6月東京サムライガンズ8『THEFAMILIAR』 作・演出・出演 2015 12 月stevia企画『美しく燃える夜×キャンパスナイトスクープ』作・演出2016年1月隼文学『絡マリ』作・演出2016年6月東京サムライガンズ9『パークザトゥリー』 作・演出・出演 2016 10 月東京サムライガンズ10『スタンドバイウィー』 作・演出・出演 2017 10 月【映像作品】TOKYOBEATMOVIES原宿編『OhMyGod!』監督・脚本・編集(2009)『MONEY』監督・脚本・編集(2013)『進めすだちくん~しぼられたって愛がある編~』(2014)※徳島県庁HPなどで公開中『進めすだちくん~目黒さんま祭り編~』(2014)『うどん県。それだけじゃない香川県おへんろ88ガールズ~逆打ち遍路の旅~』(2015)『日本パーソナルカラー協会 検定講師教育ガイド』監督・編集(2013)「Shikoku Sake Trip(四国“酒”トリップ)」オープニングVTR(2016)他多数【デザイン】他劇団舞台公演フライヤー、ロゴ製作、企業パンフレット、飲食店メニュー、グッズデザイン、パーソナルカード、キャラクター製作、イベント&LIVE企画・演出など多数
Artist Tree 米沢春花 演劇、舞台装置、空間演出札幌を拠点に演劇活動を行う。 劇団fireworks代表。自団体では、脚本・演出・舞台装置手がける。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ 連絡先 略歴
Artist Tree 森本めぐみ 絵画、札幌、北海道、GIFアニメ、育児、パブリクアート、北海道百年記念塔1987年北海道恵庭市出身、札幌市在住。2011年北海道教育大学芸術課程卒業。演劇とクラフトデザインを学んでいた10代後半から、前思春期的な自我を表現したキャラクターの絵画で活動を始める。2013年に福井県へ移住してしばし活動休止。 近年は子の誕生を機に制作を再開し、労働や育児の中で浮かぶイメージを日用品や既存の美術作品を引用しながら、土偶や、パッチワーク、ループアニメーション、ドローイングなど、小さく軽いメディアに仮託して制作している。2008年ターナーアクリルアワード学生の部大賞<主な展覧会> 「とがったいわ」(個展、ギャラリー門馬、2013年)、「生息と制作:北海道に於けるアーティスト、表現・身体・生活から」(新宿眼科画廊、2013年)、「Nameless Landscape」(札幌文化芸術交流センター、2019年)、「竣工50年 北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(小樽文学館、2020年)など。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先Twitter:@mmmegumi略歴1987年北海道恵庭市出身、札幌市在住。2011年北海道教育大学芸術課程卒業。演劇とクラフトデザインを学んでいた10代後半から、前思春期的な自我を表現したキャラクターの絵画で活動を始める。2013年に福井県へ移住してしばし活動休止。 近年は子の誕生を機に制作を再開し、労働や育児の中で浮かぶイメージを日用品や既存の美術作品を引用しながら、土偶や、パッチワーク、ループアニメーション、ドローイングなど、小さく軽いメディアに仮託して制作している。2008年ターナーアクリルアワード学生の部大賞<主な展覧会> 「とがったいわ」(個展、ギャラリー門馬、2013年)、「生息と制作:北海道に於けるアーティスト、表現・身体・生活から」(新宿眼科画廊、2013年)、「Nameless Landscape」(札幌文化芸術交流センター、2019年)、「竣工50年 北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(小樽文学館、2020年)など。
Artist Tree 奥村圭二郎 1982年東京生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業。2005年〜2014年取手アートプロジェクト事務局では、アートプロジェクト全般の運営管理/展覧会・屋外パフォーマンスの企画制作/NPO法人化立ち上げ/資金調達を担当。2015年〜2017年東京藝術大学美術学部(特任研究員)では、東京都美術館と東京藝術大学の連携事業「とびらプロジェクト」のコーディネーターとして、アクセシビリティ/芸術と社会課題/ワークショップメイキング等に関する講座運営を一般から募ったアート・コミュニケータ(通称:とびラー)を対象に実施した。2018年からはフリーランスとして、東京都内で開催されている芸術文化事業のマネジメントに携わっている。これまでの活動2004年4月〜2015年3月 取手アートプロジェクト展覧会やWSの企画からコーディネートまで、出来ることは何でもやった。2007年からは取手に引っ越して生活と仕事を分けない時間を過ごしていたことは、今思うと良い経験だった。色々あり過ぎてとても書ききれないので聞いてください。2015年4月〜2017年3月 とびらプロジェクトお世話になった人から声をかけていただき、東京芸大と東京都美術館の連携事業に携わりました。まさか自分が美術館に勤務することになるなんて思いもしなかったが、美術館という特殊な空間を身を持って経験することが出来た。今、思い返すと、今では一般的になりつつある価値観(インクルーシブ、ダイバーシティ)を先取りしてプログラム化していたことは、とても凄いことなんだなぁ。2017年〜フリーランスとして本格的に活動スタート連絡先e-mail:keijirouokumura・;・gmail.com(・;・を@に)Instagramtwitter
Artist Tree 山本雄基 絵画、美術、現代美術、抽象、札幌、1981年帯広市生。2007年北海道教育大学大学院修了。現在札幌在住。 重層的な透明層の中に、色の円と色をくり抜く円を交錯させた作品を制作。階層をまたいだ色や形の相互関係による絵画空間を複雑に展開させ、対立的な物事のあいだを思考する。 第30回ホルベインスカラシップ奨学生(2015)、第5回大黒屋現代アート公募展 大賞(2010)。 主な展覧会に、Under Current(Powerlong Museum/2022)、山本雄基展(板室温泉大黒屋/2022)、PLACE OF HELLO(Mikiko Sato Gallery/ 2020)、Flatten Image-山本雄基・浦川大志展-(ギャラリー門馬/2019)、VOCA展2014(上野の森美術館/2014)、道東アートファイル2013(帯広美術館/2013)など。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree参考作品:Untitled /2020/162×162cm/ キャンバスにアクリル絵具/撮影:伊藤留美子web:http://yamamotoyuki.comInstagram:@yukiyamamoto_studiostudio:http://www.naebono.com Twitter:@tawagoto_yyhttps://twitter.com/tawagoto_YY
Artist Tree 立川佳吾 人形劇・児童劇・ナレーター北海道教育大学札幌校在学時より 俳優活動を始める。 2012年より、トランク機械シアターを立ち上げ、人形劇作品の製作を始める。劇場だけでなく、保育園・学校・野外でも作品を上演。テレビ番組やラジオドラマにも出演。 ナレーターとしても活躍し、 新生活とともに、声をよく聞くようになる。専門学校などで講師としても活動している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先 kei5wacs3@gmail.comhttp://www.trunktheater.net略歴1981年 2月15日生
Artist Tree 清水友陽 演出家・劇作家。劇団清水企画代表。 北海道演劇財団芸術監督。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ連絡先略歴
Artist Tree 藤谷康晴 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせグループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0連絡先Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink略歴0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)
Artist Tree THE ICEMANS 氷 雪 冬 自然科学 アート 雪育 彫刻 造形THE ICEMANS タケナカヒロヒコ(造形作家・思想家)、Alidad Kashani(芸術家)、上野かな子(デザイナー)、を中心メンバーとして活動。 2006〜2019年 ニセコを中心に冬のアートイベントを企画運営。 2017〜2020年 知床流氷フェスティバル会場にて氷の建造物を制作。 2020年以降コロナ禍では、自然と人間の繋がりに主眼をおき、道内の様々な場所で巨大なバルーンを使った氷のドームを制作。個人宅の庭先に一晩でアートを出現させるプロジェクト、”THE ICEMANSキノコのように降臨”をスタート。 活動を記録した映像作品はYoutubeチャンネルTHE ICEMANS DANCEで公開中。 冬の楽しみを通して自然との調和を提唱している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせアイスマンズの雪育イベント!We Are Nature! が開催されます。2/22-23アイスドーム制作 2/25 一緒に外で遊ぼう。雪と自然の科学を体感しましょう。Linkhttps://instagram.com/theicemans?igshid=YmMyMTA2M2Y=https://www.facebook.com/theicemanshttps://youtube.com/@theicemansdance7070
Artist Tree KIM YOOI サックス、電子音楽NPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作 1994年生まれ北海道千歳市出身、札幌市在住。 北海道教育大学岩見沢校 芸術課程 芸術文化コース アートマネージメント音楽研究室卒業。 吉武裕二(プロデューサー)/KIM YOOI【読み:キム・ユウイ】(ミュージシャン)として活動中。お知らせ連絡先Twitter:@kimyooi0525略歴NPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作1994年生まれ北海道千歳市出身、札幌市在住。北海道教育大学岩見沢校 芸術課程 芸術文化コース アートマネージメント音楽研究室卒業。吉武裕二(プロデューサー)/KIM YOOI【読み:キム・ユウイ】(ミュージシャン)として活動中。プロデューサーとしては、サカナクション主催野外複合カルチャーイベントSAKANATRIBE(2016年)でのエリアプロデュースに携わったことをきっかけに、翌年以降JOIN ALIVEでエリアプロデュースを行う。その後公共ホールでの文化事業プロデューサーを経て2022年8月よりNPO法人コンカリーニョ マネージャー・企画・制作となる。ミュージシャンとしては10代前半からサックスを始め、大学在学中は田野城寿男に師事、2016年に前衛サックス奏者吉田野乃子との出会いにより、前衛音楽・即興演奏に傾倒する。 同時期に北の至宝と呼ばれるミュージシャン KUNIYUKI TAKAHASHIの影響を受け、即興性とエレクトロニクスを組み合わせたマシーンライブを始める。現在北海道を拠点に活動するジャズミュージシャンを中心に構成されたTotal Knock Out Orchestra(立花泰彦、小山彰太、奥野義典 等)にテナーサックス奏者として参加。また近年ではコンテンポラリーダンス・舞踏公演での舞台音楽を多数手掛ける。【これまでの主なプロデュース企画・出演】SAPPORO ART LIVE「SYNCHRONIZATION」(2020年):プロデュース/出演SAPPORO ART LIVE「NEW DISTANCE」(2020年):プロデュース/出演北海道舞踏フェスティバル(2020,2021年):出演Dance Exhibition Sapporo 2021(2021年):出演石井則仁(山海塾所属)舞踏公演「がらんどうの庭」(2022年):出演北海道文化財団 文化芸術活動継続支援事業 「踏刻」(2023年):プロデュース/出演
Artist Tree ウリュウ ユウキ Yuuki URYU 写真 旅 旅行 デザイン 紙媒体 本 雑誌写真作家/図案創案家1976年生まれ 長野県出身祖父から父へと継がれてきたカメラを手に中学校で写真部に入部し写真を始める 2001年東京で初の個展を開催2003年より札幌を拠点とし、作品制作ならびに紙媒体を中心としたデザイン・取材/文筆活動を続けるPhotography Artist / Graphic Designer Born in 1976 at Nagano Pref. In Jr. High School age, I join photography club with camera inherit from my father and grandfather. I held first solo exhibition in Tokyo on 2001. After that move to Sapporo on 2003, since then I make artworks and activities in design for paper-media, writing texts, etc.トピックス●作品集発売中!近年制作を続けている2つのシリーズの作品集をウェブで販売しています。『窓 -Layered Journey-』(頒価3,000円)『春になれば全ては消えてしまうのに』(頒価1,000円)*別途送料詳しくはこちらをご覧ください!https://yuukiuryu.square.site/_______________________作ってきたものごと●展覧会 *主な開催・出展【個展】2001年 初個展『landscape//”sora”scape』(東京・御徒町 cafe K)…以降 ほぼ年に一回の個展をこれまでに20回開催2007年『旅をするフィルム』(富士フイルムフォトサロン・札幌)2013年 『ここから見える景色』(東京・世田谷 commune)2014年3月 『向こうからの続き』(札幌 ギャラリー・ニュースター)7月 『white,and』(札幌 ギャラリー犬養) *札幌国際芸術祭2014 同時期開催事業参加12月 『轍 -layered winter-』(札幌 六花亭福住店喫茶室)2018年 『時速xキロメートルの独り』(東京・吉祥寺 ギャラリーイロ/札幌 ファビュラス)2021年『leave a note -トラムの窓に置き手紙-』(札幌 トラムニストギャラリー*杮落とし展示)【企画展・公募展】2002年 『せんだいアートアニュアル2002』(仙台 せんだいメディアテーク)2008年 『さっぽろアートステージ2008』”500m美術館”メイン作家選出(地下鉄大通駅-バスセンター前駅間コンコース)2012年 『Media Arts Summer Festival 2012 [FINAL CUT]』(札幌 ICC インタークロス・クリエイティブ・センター)2013年・2015年『SAPPORO ART MAP』(札幌 500m美術館)2015年 『宙ニ謳フ』(横浜 Chapter 2)2015~2017年 『アートフェア札幌』(クロスホテル札幌)2017年 『札幌美術展「旅は目的地につくまでがおもしろい。」』(札幌芸術の森美術館)2019年 『はこだてトリエンナーレ2019 ~みなみ北海道を旅する芸術祭~』(函館市地域交流まちづくりセンター/茂辺地北斗星広場)2020年 『北海道151年のヴンダーカンマー』(北海道立近代美術館)【グループ展等】2001年~『小樽・鉄路・写真展』連続出展(小樽 旧国鉄手宮線跡地)2008年~『フィルム一本勝負』(富士フイルムフォトサロン・札幌/小樽 運河プラザ/市立小樽美術館 市民ギャラリー)2017年 『都市標本図鑑』(札幌 OYOYO)2020年・2022年 逢坂憲吾氏との二人展『そこから なにが みえますか』(京都 MEDIA SHOP/札幌 トラムニストギャラリー)●作品使用2005年 書籍『スポーツは果実』(求龍堂) 挿絵作品掲載2015年 雑誌『O.tone』(あるた出版) 札幌市電延伸特集記事作品提供2020年 札幌市交通事業振興公社 市電公式ウェブサイト「電車博物館」写真撮影●デザイン制作2014年 日本歯科技工学会第36回学術大会『匠とサイエンス』ポスター2015年 北海道教育大学岩見沢校 地域連携イベント『あそびプロジェクトvol.5』告知チラシ2015年~ (一財)縄文芸術文化財団 会報インタビュー・構成・撮影・デザイン2017年~ 北海道清里高等学校 学校案内 デザイン●受賞2005年 『さっぽろアートステージ2005』アートトレイン 準グランプリ(地下鉄南北線車内に作品掲出)2013年 『六花ファイル』(六花亭製菓主催)第4期作家収録・作品収蔵●その他の活動2016年 札幌市「札幌文化芸術円卓会議」2016年度(平成28年度)委員2017年 札幌国際芸術祭2017 市電プロジェクト『都市と市電』企画メンバー/「市電放送局JOSIAF」パーソナリティ(札幌 札幌市電車内・沿線)_______________________ウェブサイトhttps://www.yuukiuryu.com/活動情報やポートフォリオをご覧いただけます_______________________SNSTwitter@yuukiuryuhttps://twitter.com/yuukiuryuInstagramhttps://www.instagram.com/yuukiuryu/作品や活動の情報を中心に。https://www.instagram.com/sorami/日常のことを中心に。_______________________ご連絡先hello■yuukiuryu.com (■を@に)
Artist Tree 山崎耕佑 音楽、舞台劇伴つくり、劇団fireworks(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree
Artist Tree 新藤 理 鍵盤ハーモニカ リコーダー 指揮 音遊び(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree「あたらしい民話presents さっぽろの民話 読み語りライブ」に音楽担当として出演します。札幌の人々に聞いた話をもとに構成された、現代の民話の読み語りです。出演者は日替わりで、私の出演は2/25(土)の回です。どの回もそれぞれ異なる物語・朗読・音楽の組み合わせ。その時かぎりの味わいをお楽しみいただけることでしょう。席数が少ないので、ご予約はぜひお早めに!https://sapporo-community-plaza.jp/event_scarts.php?num=2810&fbclid=IwAR0PoOrQY208xtKh-9BdMr28FwT9RJ-dusTBzngelLatj91eXS-1ptwbmdg連絡先osamu036samuel あっとまーく yahoo.co.jp略歴1977年札幌市生まれ。NPO法人フリースクール札幌自由が丘学園スタッフ。長きにわたったクラシック音楽中心の活動を終え、2017年から鍵盤ハーモニカやリコーダーなどを鳴らす音楽家になる。演劇・ダンス公演での演奏活動が中心。https://twitter.com/osamushi036
Artist Tree 小林テルヲ 演劇 俳優 演技 コンテンポラリー コンタクト ダンス 高校演劇 札幌で役者をやりながら 高校教員をしています。 演劇部の顧問でもあり、 積極的に札幌のアーティストに協力を頂いての 作品作りを始めました。 ちなみに石狩支部演劇専門部の運営もしています。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせintroの次回公演(ツイキャス)札幌と大阪をオンラインで繋いでおしゃべりしたり、稽古したり。創作の一部が見られます。連絡先Twitter@kobateru_smz略歴1974年 北海道(道東)生まれ主な出演作品yhs 「しんじゃうおへや」「四谷美談」intro 「わたしCTGD」「こっちにくるとあの景色がみえるわ」など
Artist Tree 牛島有佳子 昭和 昭和歌謡曲 ダンス ダンサー 振付家 演出家 公演 舞台 昭和生まれの女性たちを集めた青春ダンス集団「昭和レディ」の代表。演出振付をつとめる。コミカルな作風が特徴。 いくつになっても輝くのは今!観た方に元気になってもらいたい!をモットーに公演を行う。昭和レディとして自主公演を行うほか、森や美術館、さまざまなアーティストとのコラボレーション・振付、他公演にゲスト出演なども行う。BESJマットピラティスインストラクター資格 JCCAベーシックインストラクター資格 も所持し、身体を見つめる日々…人生、笑いは重要です。昭和レディ自主公演(4/29)●チケット予約https://ticket.corich.jp/apply/225815/Facebookhttps://www.facebook.com/shouwa.ladyInstagramhttps://instagram.com/shouwa.lady?igshid=cjuirgm9hg0vhttps://twitter.com/shouwa_lady
Artist Tree すがの公 演劇、ハムプロ、ワゴン、巡演、全国、縦断興行、ヤキトン、居酒屋、札幌、東京、沖縄札幌ハムプロジェクト脚本演出役者プロデューサー。メンバーとともにヤキトン立ち呑み屋『すわ』を運営。ハムプロにおける全ての作・演出をてがける。北海学園大学演劇研究会から演劇を始め、劇団イナダ組に数年所属。劇団SKグループを9年運営。2004年より札幌ハムプロジェクトを立ち上げワゴンで全国巡演開始。2009年「若手演出家コンクール2008」優秀賞&審査員特別賞受賞。2011年より東京支部を設立し、演劇カンパニー”東京の人”運営、「小さい」演劇祭シリーズを主催。2012年より札幌座ディレクターを兼任する。2016年より沖縄在住。 (サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせグループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0連絡先Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink略歴0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)
Artist Tree 深澤孝史 1984年山梨県生まれ。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ グループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0 連絡先 Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink 略歴 0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)
Artist Tree N.MIKA アクリル画、ミクストメディア、イラスト絵を描くのが好きで、洋服も大好きなおばさんです! 🎨 絵画に関するお問い合わせ、購入に関するお問い合わせは、メールから、どうぞ展覧会N.MIKA 展覧会白老「結」2023.1〜2023.2WEBm-artmuseum.comInstagram:n.mika6621連絡先m6izka_6g [a] yahoo.co.jp[a] を@に変えてください。略歴
Artist Tree 甲斐大輔 演劇 演技指導 舞台 声優 専門学校北海道札幌市出身。俳優や演出をやってます。 現在はヒューマンアカデミー札幌校で担任の先生やりながら、学生や若い俳優たちに演技指導をしてます。 劇団かいを立ち上げて、演劇活動もやってます。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree お知らせ グループ展のお知らせ会期:00年0月0日〜00年0月0日11:00~19:00(××休)会場:〇△〇△ギャラリー〇〇市 〇〇 0-0-0 連絡先 Twitter@HokkaidoAUShello [at] haus.pink 略歴 0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)
Artist Tree リンノスケ 俳優。北海道出身。 札幌市立大学デザイン学部卒。在学時の2015年より俳優・舞踏を始め、2016年に旗揚げしたきっとろんどんを共同主宰。また劇団千年王國に出演した際は「贋作者」では鴈次郎役、「ロミオとジュリエット」ではロミオ役でそれぞれ主演を演じた他、micell、モノクロームサーカス、東野祥子、伊藤千枝、田仲ハル、Sapporo Dance Collectiveなどのダンス・舞踏作品にも出演。2022年からは活動拠点を東京と北海道の2拠点に広げた。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTree
Artist Tree 内田聖良 VR, メディアアート, メディア・アート, コンセプチュアル・アート, 古本, プロジェクト, 余白書店, バーチャル, 供養, 現代アート, コンテンポラリー, アート, アーティスト日常生活に浸透するAmazonやYouTubeなどのサービスも活動の場として取り込み活動するメディアアーティスト。サーキット・ベンディング(Circuit Bending)の手法を物理的な形のないサービスにも応用して、規範的な価値観・物語の存在や、隠された物語の価値を露呈させようとする。 近年は民話や信仰をリサーチしながら、現代的な物語の流通や記憶の共有のあり方について制作・研究している。 主な作品、プロジェクトに、書き込みや日焼けなどがある古書を一点物のコレクター商品として価値づけ、Amazonを利用して再流通させる《余白書店》、3DスキャンとVR技術を利用して、捨てられない物にまつわるエピソードと3Dデータを記録・共有する《バーチャル供養講》など。 お知らせ開催中多層世界とリアリティのよりどころ Viewpoints of Reality in the Multi-layered World会期:2022.12.17(土)—2023.3.5(日)会場:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] ギャラリーA ,ハイパーICC Venue: NTT InterCommunication Center [ICC] Gallery A, Hyper ICCYAU ⇄ サッポロ・パラレル・ミュージアム会期|2023年2月4日㈯- 2月20日㈪場所|YAU STUDIO(東京都千代田区有楽町作家|内田聖良、大橋鉄郎、佐藤壮馬、高橋喜代史開催予定VOCA展2023 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─ The Vision of Contemporary Art 2023上野の森美術館 The Ueno Royal Museum会期 2023.3.16(木) 〜 3.30(木) 会期中無休連絡先 contact: info[AT]sesseee.seウェブサイトCVポートフォリオ(日)portfolio(EN)略歴(詳しくはCVをご覧ください。)武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業(造形 学士)、岐阜県立情報科学芸術大学院大学(IAMAS)メディア表現研究科 修了(メディア表現 修士)。主なグループ展2022 「多層世界とリアリティのよりどころ」NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] /東京2021 「200年をたがやす」展示期間「みせる」:「生活」エリアにて《水山これくしょん》展示 秋田市文化創造館 /秋田2019 「Spiral Independent Creator’s Festival (SICF19)」受賞者展 スパイラルホール /東京2017 「あきたの美術2017」秋田県立美術館/秋田主な個展2021 「バーチャル供養講」 国際芸術センター青森(ACAC)/青森2017 「RAM EXTRA 凡人ユニットのぼんおどり~結婚ってなに?~」秋田公立美術大学 ギャラリーBIYONG POINT/秋田(凡人ユニットとして)2015 「OVER THE IAMAS – イアマスを越えて ♯5 内田聖良 『'余白'の使用法 余白書店と道具』」gallery 16/京都受賞・採択等2022 「NEWVIEW AWARD 2021」 ファイナリスト 作品《バーチャル供養堂》 (NEWVIEW Project: (Psychic VR Lab / PARCO / Loftwork Inc.))2018 平成30年度 文化庁若手メディア芸術クリエイター育成事業 採択(文化庁)2018 Spiral Independent Creator’s Festival 19(SICF19) 金森香賞 (スパイラル/株式会社ワコールアートセンター)2015 WIRED Creative Hack Award 2015 ファイナリスト 作品《余白書店》(WIRED)2014 第18回 文化庁メディア芸術祭 審査委員会推薦作品 作品《余白書店》(文化庁)
Artist Tree 小林大賀 1986年 札幌生まれ木彫からCGまで様々な手法を用いて幻想的なイメージを制作。 近年は、映像、絵本、絵画を制作している。(サンプルが表示されています)「編集」ボタンをクリックして、ArtistTreeのページを作成しましょう!画像や文章を追加して、作品集やCV、協力者の募集、イベントのお知らせなど、目的に合わせて自由にページを作ることができますHAUSメンバーによる確認が完了するとArtist Treeのページに掲載されます(確認の完了は登録いただいたメールアドレスにお知らせします)参考ページみんなのArtistTreeを見てみようすべての Artist Tree を表示CVの書き方の参考に羊屋白玉さんのArtistTree映像作品も紹介できます箱崎慈華さんのArtistTreeお知らせ2月中旬より自作の絵本「謝肉祭」の原画を中心とした個展を開催します。会場にて本の販売もいたします。足元の悪い季節ですが、お越しいただければと思います。会場:TOOV cafe /gallery ト・オン・カフェ / ギャラリー会期:2023年2月14日(火)~2月26日(日)会期中無休。時間:10:30~20:00札幌市中央区南9条西3丁目2-1 マジソンハイツ1階 (地下鉄南北線「中島公園駅」より徒歩2分)TEL 011(299)63802月14,18,19,25,26日は在廊予定です。(18,19日は13時30分~)連絡先taiga.kob@gmail.comwww.taigakobayashi.com略歴1986年 札幌生まれ木彫からCGまで様々な手法を用いて幻想的なイメージを制作。近年は、映像、絵本、絵画を制作。Sapporo Dance Collectiveにて映像制作として関わる。2008 卒業制作として舞台作品「聖ペテロ神輿さま御奉納のための祭典」を上演。2009 レトロスペース坂にて個展を開催。2010 自身のパフォーマンスグループ「円山貴人会」を発足し、活動を開始する。a-lifeでの単独公演「七夕園遊会」、moleでのイベントへの参加の他、赤ヒ部屋(札幌)、Spiritual Lounge(札幌)、青い部屋(渋谷)カレイドスコピック(町田)などに出演。2012 BADO!2012のクラウドファウンディングに企画を応募し、後援を得てアメリカ、バルセロナにてグラフィック作品の制作を行う。2014 親子展「Mi Familia」をOYOYOにて開催。2015 Necco(札幌)にてパフォーマンスイベントに参加。シゲちゃんランドにて「原人祭り」に参加。Zine「Signe」を発行し、エッセイを寄稿する。2018 tumblrにて「往復書簡」を開設。詩人の三角みづ紀と毎日連載を行う。短編映像作品「朝を聞く」を南イタリア、マテーラにて制作。短編映画「秋」主演。監督:Jun Chon (Austria Independent Film Festival 公式出品)2019 短編映像作品「雪が降ってゐる……」、「影の湖」を中也の会大会にて上映(中原中也記念館)。短編映像「風の回廊」を制作。セルビアとハンガリーにて三角みづ紀と滞在制作を行い「スロボダ広場」、「海底を歩く」を制作。2020 第3回マオイの丘ワイナリーエチケットアワード にて「Mi Familia」佳作入選。中原中也生誕祭に三角みづ紀と共同制作の短編映像作品「骨」を出品。EU-JapanFestの配信プログラムKeepgoing TOGETHERにて三角みづ紀との共同制作映像シリーズ「yukue」「雷鳴」「今日の天使」「モビール」を旧作と併せて公開。「yukue」「今日の天使」をThe World After Corona Virusへ出品。Nation's Short Film Festival(オーストリア)にて「風の回廊」を公式上映。2021 アーティスト・イン・スクール「おとどけアート」プログラムに参加。西岡南小学校にて4週間の活動を行う。 Sapporo Dance Collective「My Foolish Mind」「CATAPULT」撮影、映像制作を担当。2022 HAUSサバイバルアワードの支援を受け、アートの心理学的
Artist Tree 櫻井ヒロ 櫻井ヒロ(ダンサー、振付家、放課後児童支援員) コンタクト・インプロビゼーションユニットmicelle主宰、HAUS立ち上げメンバー。 主催公演を中心に、国内外のダンスアーティストと連携しての招聘公演、新進ダンサーとの共同制作、子育て支援センターや高齢者施設等での公演およびWS、地方劇場との協働によるコミュニティダンス事業などを精力的に行っている。 2019年札幌市民芸術祭 奨励賞受賞。 https://micelle.jimdofree.com/ News公演のお知らせ札幌演劇シーズン2023冬 劇団千年王國 公演 「からだの贈りもの」 ■会場/生活支援型文化施設コンカリーニョ ■料金/一般 3000円、学生 1500円 ■息をすること、汗をかくこと、逃げること、涙を流すこと、抱きしめること。 エイズ患者のホームケア・エイドとして働く「私」は、彼らに寄り添い、ひとつ、ひとつの生の手触りのギフトをもらう。 いま生きているからだの贈り物を通して、生と死を見つめる、静謐な短編集。 エイズ患者のホームケア・ワーカーとして働く「私」と患者たちの交流を描き、世界中でベストセラーとなったレベッカ・ブラウンの小説「体の贈り物」を舞台化。 ■公演日時 2/4(土)17:00 2/5(日)14:00 2/6(月)19:00 2/7(火)19:00 2/8(水)14:00 2/9(木)19:00 2/10(金)19:00 2/11(土・祝)14:00 ■出演 大森弥子/リンノスケ/大川敬介/櫻井ヒロ/三瓶竜大/佐藤亜紀子 ■演奏/嵯峨治彦/あらひろこ 札幌演劇シーズン (s-e-season.com) ■チケット取り扱い/ローソンケット(Lコード:18248)、チケットぴあ(Pコード:516-266)、エヌチケ、パスマーケット、道新プレイガイドWorks画像+キャプション画像ブロックや動画(埋め込みブロック)を追加することで、ポートフォリオのように使用することもできます。Contact https://micelle.jimdofree.com/Twitter: @HokkaidoAUSe-mail: hello ・;・ haus.pink(・;・を@に)HAUSはアーティストが出会える場所を作りたいと考えています。ウェブサイトやSNSアカウントへのリンク、メールアドレスなど、公開可能な連絡先を掲載してみましょう。Biography0000年 〇〇生まれ主な出演作品0000年 「〇△〇△」××□□パーク(△△)0000年 「△△△△」〇〇〇〇劇場(××)あなたの活動歴を記載することもできます。
Artist Tree 森嶋 拓 コンテンポラリーダンス、舞踏、舞台芸術、芸術祭CONTE-SAPPORO Dance center プロデューサー舞台芸術のプロデューサーとして人材育成、環境整備、企画公演の主催、稽古場支援、道外アーティストの制作支援などを行っている。主な事業 北海道舞踏フェスティバル、Dance Exhibition Sapporo、飛生芸術祭、TOBIU CAMP、トビウの森と村祭り、サッポロコレオ振付家養成講座、ダンスに没頭する4日間、近代文学演舞「地獄変」などお知らせ北海道と九州を芸術と文化で繋ぐプロジェクトのクラウドファンディング実施中連絡先https://conte-sapporo.comdance [at] conte-sapporo.com略歴CONTE-SAPPORO Dance center プロデューサー16歳でストリートダンスを始め、19歳からプロダンサー、ダンス講師として活動開始。20歳でダンススタジオを設立してピーク時は約20人の講師を抱えるが、26歳の時にダンスの仕事を全て辞めて家業の新規事業立ち上げに関わる。会社員をしながらイベントや公演を主催するようになり2010年にはフリースペースを開店、2012年にはダンスセンターを立ち上げる。2017年には会社の事業を継承して独立。写真家の妻と共に株式会社ラツカを創立し、舞台芸術から撮影、ネットショップ運営まであらゆる仕事を請け負っている。
Artist Tree 箱崎慈華 映像制作をしていますニュース2023年の活動HAUS(Hokkaido Artists Union Studies)のマルチメディア担当として勉強会企画などの技術的支援を行っています。今年は何らか自分主体の作品を作りたい...!作品監督作品https://youtu.be/eeV22mvELjo 2015年「風の刻みゆく」脚本・監督「場所には、ストーリーがある。」をコンセプトとしたプロジェクト Sapporo Movie Sketch にて製作した作品。メインロケーションは、野外に様々な彫刻を展示する札幌芸術の森の砂澤ビッキ 彫刻作「四つの風」の周辺です。企画製作: Inter x cross Creative Center映像配信参加作品https://youtu.be/6M6KilekN-I 2020年「さっぽろ文庫101巻 『声』Sapporobunko Library Vol.101 “Voice Up”」Sapporo Dance Collective配信・撮影・編集“さっぽろ文庫101巻『声」“は、昭和52年9月の初刊行から、平成14年の100巻で休止符を打った、「さっぽろ文庫」を目覚めさせ、復活をテーマにしています。 札幌の風土の中で生まれ育った芸術、文化、社会、自然を広く紹介してきた「さっぽろ文庫」からインスパイアーを受け、2020年101巻目として、現在の「声」をダンス作品化しました。 COVID19の世界的な感染拡大を同時代に体験したものとして、メンバーの身近な人たちへのインタビューや対話の中から「声」を収集。またアンケート調査の回答からも「声」を探しました。札幌市文化芸術公演補助金「さっぽろアートライブ」配信公演Sapporo Dance Collective 公式サイト撮影・編集参加作品https://youtu.be/TM_WFewih9I 2021年 「コンテンポラリーダンス&音楽ライブ公演【present】」撮影・編集trailerと公演本番映像の撮影・編集出演: 河野千晶(踊り) 佐藤夕香(ジャンベ・縄文太鼓) 烏一匹(サックス) 凛子(二胡とうた)https://youtu.be/yyT3Wld7D-k 2022年 「生活史とダンス〜サッポロ、シリベシ、マシケ編」サッポロダンスコレクティヴMy Foolish Mind 〜 Crying from mycelium societyおろかなりわがこころ〜遥かなる菌糸社会からの呼び声撮影・編集(映像作家 小林大賀との共作)コロナ禍、旅をしながら、道内様々な場所で、巨大キノコのような氷のドームを冬の徴(しるし)として作り続けるTHE ICEMANS。 この作品は、2022年冬、わたしたちサッポロダンスコレクティヴがTHE ICEMANSと道内三箇所で地域の方々とともに作品をつくった旅の叙景詩。わたしたちが見たものは、記録的な大雪の中、大雪に添い、大雪に嘆き、大雪を愉しんだ小さな生活の数々。地域における移住者の声、海の叫び、山の眼差し。キノコが地中で菌糸を張り巡らす生態を、人間社会にも置き換え、細くとも無数のつながりが起きてゆくことが、コロナ禍の、国内外の悲劇禍の、ひとびとの営みをささえてゆくことを願って。それはキノコの菌糸社会へのオマージュである。https://youtu.be/ysxmzs481Bw 2022年 「カタパルト/CATAPULT」サッポロダンスコレクティヴ撮影・編集(映像作家 小林大賀との共作)札幌、後志、増毛、道内3地方のリサーチを経て綴られる生活史とダンス。農業、原発、介護、オリンピック、そしてCovid-19… 2022年3月公開の映像作品”My Foolish Mind”に続き、降りしきる現代の課題を踊る。連絡先Twitter: @sobakasuYoshikae-mail: hakozaki ・;・ haus.pink(・;・を@略歴1987年北海道札幌市生まれ。2008年に札幌市立高等専門学校へ入学。デザインの基礎を学んだのち環境デザインコースへ進級。在学中、映画サークルに入ったことをきっかけに自主映画の制作活動を始める。2012年に札幌市立高等専門学校を卒業後、自主映画制作を続ける。2015年より北海道大学オープンエデュケーションセンターで技術職員として勤務し、映像教材制作業務に携わる。2020年の配信公演「さっぽろ文庫101巻 『声』」よりサッポロダンスコレクティヴの活動に映像制作として参加し、HAUSの活動へも関わることとなった。作品上映・配信歴2008年北海道インディペンデント映像フェスティバル(ATTIC)監督・脚本作品「教室の幼生たち」2012年札幌国際短編映画祭 北海道オフシアター(シアターキノ)監督・脚本作品「恋についての短編-失恋-」札幌国際短編映画祭 クワトロDシネマ(札幌プラザ2・5)監督・脚本作品「言葉は行方知れず」2016年Sapporo Movie Sketch(企画 : Inter x cross Creative Center YouTube配信)監督・脚本作品「風の刻みゆく」
ニュース Vol.8 LONG TIME NO SEE DOCUMENT February 2026 #ニュース ニュースVol.8 LONG TIME NO SEE DOCUMENTFebruary 20262026.1.23コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🍡1/26(月) 札幌みらい塾2026ACFアートサロン「これからの自治体文化政策を考える」に中川幾郎さんと本田修さんが登壇です「これからの自治体文化政策を考える」の内容が良くわかるメッセージをどうぞ⬇️「今、「モノの豊かさからココロの豊かさへ」という言葉が空々しく響くのはどうしてでしょうか。現在の私たちは、大してココロが豊かではない。それどころかモノも豊かではなくなってきている。社会ではさまざまな格差が拡大してきて、世相もギスギスしてきています。こんな時に、芸術だの文化だのと語っていてよいのでしょうか?いや、そうではありません。辛いからこそ芸術があり、喜怒哀楽を表出する術を持つからこそ人間なのです。自治体(地方公共団体)の文化政策は、余暇社会を謳歌する人たちの余暇活動支援ではなく、カネ、ヒマ、カラダ、セケンに悩みを持つ人々にこそ必要な「文化的に生きる権利」を保障する、必須不可欠な文化の社会保障政策なのです。」https://sapporoacf.net/event/p392/1/23(金)-2/1(日)佐野和哉さん 東京・清澄白河のdrawCircle Gallery 「録音の肉声 Exhibition」東京展https://x.com/rfv_podcast/status/2009130718363046072🌛1/30金 舞踏家・紅月鴉海さんの出演情報ですhttps://x.com/karasunotobuumi/status/1962168512191021443?s=20☕️フライヤを手にとれる喫茶店情報 まだまだたくさんあるのです〜https://x.com/karasunotobuumi/status/2012429468850151471?s=20https://x.com/karasunotobuumi/status/2012429291347189984?s=20https://x.com/cafe000con/status/2011010825201545415?s=201/31〜2/14 小林知世さんの個展が東京・日本橋で来週末から!https://www.instagram.com/p/DTkFg4HEuIF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==📙2/1日 哲学者小林和也さんが「アートを哲学する」に登壇です〜 旭川です〜https://www.facebook.com/share/p/1FimLMzRRo/?mibextid=wwXIfr🐙2/1日 渡辺たけし×清水友陽×イチノヘミキオ(音楽)さんたちが小樽で上演です(かつて小樽の高校で演劇部の先輩と後輩だった、渡辺たけしと清水友陽。35年以上も経って、初めて二人で、初めて小樽で、二人芝居を作ってみます。)だそうです〜https://www.facebook.com/photo/?fbid=122247150200085978&set=a.1220967697040859782/7(土)33歳人生行き止まり日記Remixes発売記念 トークイベントhttps://www.instagram.com/p/DTr_2uREkHo/2/15(日)西脇秀之さん 演劇の歩き方 第4回イギリス編その2 満席追加開講に向けてアンケート実施中https://x.com/actingsteps/status/2011388165337329819🐻2/21-23三瓶竜大さん 「さっぽろチェホフ祭」で「熊」を上演します。(演出)https://x.com/pocket_kikaku/status/2000143936975945802👊2月予定 わんわんズさん「演技・アクション素手・殺陣」わんクラhttps://one-ones.com/2026/01/06/one-class2月予定!-3/❄️Mona Watanabe 楽曲のMVを公開 やめた / POLhttps://youtu.be/de1wDDuux8w?si=lPymv8azwZtGzNYX
ニュース 🔰知って活かす!⑤ フリーランス法【ハラスメント等編】オンライン勉強会 #2 #ニュース 一般社団法人日本芸能従事者協会が主催する勉強会のお知らせです。HAUSの羊屋白玉がコメンテーターとして登壇します。申し込み・詳細はこちらをご覧ください。【開催概要】■ 日時:2026年1月6日(火)17:00〜18:00■ 形式:オンライン■ 参加費:無料・要予約■ 申込方法:このPeatix ページよりお申し込みください。【ご説明者】厚生労働省 雇用環境・均等局参事官(雇用環境政策担当)山口了子【第1部:解説(厚労省執行の4項目)】■ 第12条:募集情報の的確表示求人・募集時の情報を正しく伝える義務。仕事内容・報酬・期間などを誤解が生じないよう明確にすることが求められる。■ 第13条:育児・介護等への配慮継続的な取引関係で(6ヶ月以上など)、妊娠・出産・子育て・介護等で困難が生じた際に、スケジュール調整など合理的な範囲での配慮を行う義務。■ 第14条:ハラスメント対策(相談体制の整備)フリーランスに対するハラスメントを防止するための配慮義務。事業者は相談窓口の設置など、適切な対応体制の整備が求められる。■ 第16条:中途解除の事前予告・理由の開示6ヶ月以上の業務委託の場合、30日前までの予告をしなければならない。【第2部:質疑応答】参加者から事前にいただいたご質問およびび当日のチャット質問にお答えします。【ファシリテーター】森崎めぐみ(俳優/日本芸能従事者協会)【コメンテーター】 深田晃司(映画監督/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険副理事長)、羊屋白玉(演出家/全国芸能従事者労災保険センター・フリーランス安心ネット労災保険安全衛生委員/Hokkaido Artist Union Studies(HAUS))/一般社団法人日本モデルエージェンシー協会/協同組合日本シナリオ作家協会
ニュース Vol.7 LONG TIME NO SEE DOCUMENT January 2026 #ニュース ニュースVol.7 LONG TIME NO SEE DOCUMENTJanuary 20262025.12.19コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🦀12/20-21 竹原圭一さん舞台 HLT 近代美術館「北緯43から見た二つの椅子」ゴッホとゴーギャン🪑https://x.com/htl202203/status/1985542599986594053?s=46&t=9jgJUTzBfzveEWvWkR0UHg🎒12/19-23 西脇秀之さん 「演劇の歩き方」第2回 北海道編②を開催します。https://note.com/kaikisen/n/ne003cb81f40f💡12/6-26 風間天心さん、今村育子さん「集まりの口実 2025」眺望ギャラリー「テラス計画」にてhttps://www.instagram.com/p/DR3N0jGkpNO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==風間天心さんがゲストで登場した吐き出し喫茶のレポートも出来ましたよhttps://hakidashi.studio.site/posts/251018🍹1/6 一般社団法人日本芸能従事者協会が主催するフリーランス法に関する勉強会のお知らせです。HAUSの羊屋白玉がコメンテーターとして登壇します。https://haus.pink/2025/12/17/news_1218/🦔1/7-8 ハリーとAllyの会 しみさぽマルシェ参加イオンモール札幌平岡https://www.shimin.sl-plaza.jp/event_post/【しみさぽマルシェ#5へぜひお越しください】/🎒1/12(月・祝)13:30〜16:30「演劇の歩き方 第3回イギリス編〜演劇をはじめる人、つづける人の学びの場。講師は西脇秀之さん。https://x.com/actingsteps/status/2001590402454032434?s=20🐟1/17-18 「畳の上のシーラカンス」fireworksのツアー金沢、札幌、そして函館公演です。札幌お土産あるんですって🎁https://x.com/__fireworks__/status/1995827367454147001?s=20👊1月予定 わんわんズさん「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 近日公開?https://one-ones.com🥁1/31 LOST BACK’ POINT 「Medicine's release tour」の FINALです!@Vypasshttps://x.com/LostBackPoint/status/2000164722784739815?s=20🐻2/21-23三瓶竜大さん 「さっぽろチェホフ祭」で「熊」を上演します。(演出)HAUSの櫻井ヒロもダンス×音楽「煙草の害について」で出演します。https://x.com/pocket_kikaku/status/2000143936975945802🎤佐野和哉さん 「録音の肉声 - アートとテクノロジーのポッドキャスト」更新中https://www.youtube.com/@rfv_podcast✎佐藤遥さん TURN記事執筆「THE 30 BEST ALBUMS OF 2025 2025年ベスト・アルバム」https://turntokyo.com/features/the-30-best-albums-of-2025/__________________🍡編集後記☕️《11/30のこと》札幌の老舗の喫茶店「余舎」さんが11/30惜しまれながらも閉店してしまいました。純喫茶ヒッピーさんのxをどうぞ🍞https://x.com/JunKissaHippie/status/2000865079592673537?s=20https://www.japan-cafe.com/🍏先日、12/13-14上演されたこちら↓https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=4493なんとなくゆるく観た人たちが集まって作品について語り合いました。🍎こちらの甲斐大輔さんのXに誘われて〜↓『わかろうとはおもっているけど』「対話」が見事な演劇も素晴らしいけど観終わった後に「対話」が生まれる演劇が僕は好きですこの演劇を観た後は誰かと喋りたくなります全然違う感じ方をしてるかもしれないけどすり合わせる努力をしたくなりますhttps://x.com/theater_D_KAI/status/1999837122782708029?s=20お話の内容はテキストにしたくおもってます〜。お楽しみに🍊トップ画像のチーズはHAUSの戸島由浦が関わっている苗穂基地の忘年会。もうすぐ2周年です~。https://www.instagram.com/naebo_base/
ニュース Vol.6 LONG TIME NO SEE DOCUMENT December 2025 #ニュース ニュースVol.6 LONG TIME NO SEE DOCUMENT December 20252025.11.17コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🍎アンケートの回答は12/7までです。【札幌演劇創作活動におけるハラスメント実態把握アンケート】有志の方達が立ち上げました。演劇活動におけるハラスメントの現状を知り、安全な創作環境を目指すための調査です。https://x.com/pocket_kikaku/status/1987475274771091511?s=20アンケートURLhttps://forms.gle/nzD3EdAJSahbAfz86お問い合わせ先 pipsapporo2024@gmail.com🍌本調査の実施にあたって⬇️https://x.com/pocket_kikaku/status/1989321331532591470?s=20🍇第三者相談窓口としてHAUSも協力しております。まとまってなくても大丈夫です〜こちら連絡先です〜🐼▶️ hello@haus.pink 🐳https://haus.pink/🦚11/18 19:30〜21:00 Sapporo Culture Knot Week実行委員会代表の山田大揮さんが聞き手となって「文化の現場の安全のために」をテーマに、ゲストを迎えての鼎談です。http://docs.google.com/document/d/17m8k1sRpiXKR9McTb8AVuxq2NV8gzb0Kxs72Q4DdCpg/edit?fbclid=IwY2xjawOH2yBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwb2R0cVV2ZDRxeHd5VlZwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MghjYWxsc2l0ZQEyAAEeA45ZYvrhw6twzXKsKIxOigPQ0B34dCltH0edyjUd5R7TGsxg35U243NHvZg_aem_qQMwduaIGvPwwiAhsI1fFg&tab=t.0🧃11/18 22:30~。久しぶりの雑談窓口。Xのスペースにて。札幌のポケット企画の三瓶竜太さんと。「アート界隈のハラスメントについて」話します〜🍹 こちらに集まってね〜▶️https://x.com/haus_hokkaido/status/1990370746691203552?s=20✌鼓代弥生さん。展示中〜。11/21までです。https://x.com/Yayoi_Codai/status/1989999196720816609?s=20🌕11/21(金)紅月鴉海さん 朗読と舞踏 岩本珈琲さんにてhttps://x.com/karasunotobuumi/status/1990347403241955365?s=20🎤11/23(日)20:00- art for allが主催する「フェアカルチャー憲章」日本語訳公開記念|美術分野の報酬問題を考えるラウンドテーブル 芸術家のお金の話など。HAUSも登壇します。https://afa-fairculture.peatix.com/🥾11/24(月・祝)西脇秀之さんワークショップ 「演劇の歩き方」1席空いているようです。https://x.com/actingsteps/status/1990043819539308642?s=20👒11/24 14:00- きたまりさんが大阪の梅田でYOSETE UMEKITA vol.11に出演します。無料です〜。詳しくはこちら〜。https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uc1kqxvXUw174VEHsduU8rRnUnGm2TS14zfT6o4cdV8wzxKdzWsrYepFFZVsfSMhl&id=100023856932693♻️佐野和哉さん「33歳人生行き止まり日記 Remixes」11/23(日)文学フリマ東京41にて頒布https://www.instagram.com/p/DRGP81zAYNY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==🌞11/24(月)-29(土) 風間天心さん銀座で開催されるグループ展に出品https://www.facebook.com/Tengshing.Kazama/posts/pfbid02h244BLGvG25s9w7Aji2cfZDkMC3T19iQ6gReLMsJFMtN5tNdQy2FhPdyRW4mBgDml🌺米沢春花さん パゥピーポォズ;×優美花×劇団fireworks『畳の上のシーラカンス』同時上演『まな板の上にアロワナ』11月25日(火)・26日(水)https://x.com/yonezaw14266933/status/1990354229412909095?s=20👊わんわんズさん 「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 12月予定!https://one-ones.com/2025/11/05/one-class12%e6%9c%88%e4%ba%88%e5%ae%9a%ef%bc%81-2/🍎小林知世さん参加する「time-lapsed memoir, 磯部真也と画家と音楽家たち」が12/13に東京のPOOL Sakuradaiにて開催されますhttps://www.instagram.com/p/DQyxS9QCXfZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==🎸12/14 LOST BACK’ POINTがKASHI ROCK FESTIVAL 2025に参加です。苫小牧ELLCUBE.https://x.com/LostBackPoint/status/1986051581859729883?s=20🦀竹原圭一さん舞台 HLT 12/14 砂川公演 12/20-21 近美公演「北緯43から見た二つの椅子」ゴッホとゴーギャン🪑https://x.com/HTL202203/status/1988553602680442990?s=20🦔ハリーさん 12/15「ハリーと来年を考える会」開催予定です。https://sites.google.com/view/harryandally/home📗テントサウナ団小林和也さん 丸善ジュンク堂で選書されたそうです📕いま「からだ」を読み直すhttps://www.facebook.com/kazuya.kobayashi.777/posts/pfbid0VRKW8tNH6UXGV33DSpSaWDGHXtN1L4RfA3PTMBy4FHJ3ChkTJVKkcWw8as1db4ERlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー🏖️アーティストの活動環境に関わるようなお知らせ🌊🧡12/11 厚生労働省委託時事業「職場におけるハラスメント対策研修(事業主向け13:30~と相談窓口担当者向け14:45~)」zoomです。無料で参加できます〜。https://www.tokio-dr.jp/seminar/2025/2025harassment1.html🚪札幌市市民文化局文化部「さっぽろの文化芸術がひらく『つぎのとびら』」ーみんなで考える文化芸術支援ー12/1(月)17:30-20:30
ニュース Vol.5 LONG TIME NO SEE DOCUMENT NOVEMBER 2025 #ニュース ニュースVol.5 LONG TIME NO SEE DOCUMENTNOVEMBER 20252025.10.27コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。☕高田陽子さん2人展 10/31~ 絵本とcafeゴルディロックスにてhttps://www.instagram.com/p/DPs9np4ks77/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==🌰11/3『演劇の歩き方』演出家西脇秀之さんのワークショップ! なのですが、11/3が満員御礼でして月末に追加ws予定してます〜なのですが、11/3が満員御礼でして月末に追加ws予定してます〜https://x.com/actingsteps/status/1980222160720597071👂佐野和哉さん 録音の肉声 - アートとテクノロジーのポッドキャスト 配信中「Delta of Creativity -創造のΔ-」https://open.spotify.com/episode/6qfmRHcWcP38l4mcCQCZjc?si=33k4pui6RYCujqZMPgE-5Q🌳鼓代弥生さん11/8-12『北海道のアーティスト50人展-2025 vol.2「特別展」」に参加です〜https://x.com/Yayoi_Codai/status/1981318917596627010🐾リンノスケさん DANCE MARATHON EXPRESS フランス国内ツアー全日程終了!https://www.instagram.com/p/DQElgWkisa2HxTe1fYQoKpyPRwyGn02l-PEkaw0/👊わんわんズさん 「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 11月予定!https://one-ones.com/2025/10/16/one-class11%e6%9c%88%e4%ba%88%e5%ae%9a%ef%bc%81-3/🎤リンノスケさん きっとろんどん東京第2回公演『首2』(11/27-)https://www.instagram.com/p/DODKEx6E4Nz/?img_index=1🦔ハリーさん 12/15「ハリーと来年を考える会」を開催します!https://sites.google.com/view/harryandally/home❄️アイスマンズさん 冬の活動を応援するチャリティーライブが開催されました!https://www.instagram.com/theicemans/🐙OCTOPUS BOYさん 長岡市でのデザイン新作。ロゴや年賀状。https://www.instagram.com/tacobozu/🍁内田聖良さん 富川岳「シシになる」書評 各紙に掲載されています。https://www.instagram.com/p/DQBafa0DjTW/?utm_source=ig_web_copy_link🧢【労災加入24h 受付中】芸能従事者も、副業のピアノやダンスの講師もフリーランスとして美術家、作家、マンガ家、スポーツ家、演技コーチ、研究者、ジャーナリスト、手話通訳士…等々。hartsworkers.jp/geinourousai/加入のお手続きはこちらからhttps://x.com/ArtsWorkersJpn/status/1979537855971221997🐝わからないことありましたらハウスが相談うけたまわります。hello@haus.pink👙羊屋白玉レコメンデーション!👃ニューヨークの演出家アヤ・オガワ「鼻血〜The Nosebleed」東京の新国立劇場に〜。11月20日~24日🐏羊屋も観にゆきます〜。おすすめです〜。https://www.nntt.jac.go.jp/play/the-nosebleed/
ニュース Vol.4 LONG TIME NO SEE DOCUMENT OCTOBER 2025 #ニュース ニュースVol.4 LONG TIME NO SEE DOCUMENTOCTOBER 20252025.9.29コロナ禍頃からハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🦀竹原圭一さん HTL第3回公演 『北緯43度から見た二つの椅子』 砂川公演決定 !詳細coming soon!🐡https://x.com/K1Takechanman/status/1972628673619738797🎶佐藤遥さん PARKGOLF『FOLK JUMP』レビュー。「想像してみて」https://x.com/turntokyo/status/1964252942393094648📕江本純子さん 第一回永井荷風文学賞ノミネート『真夜中に寂しくなったときに観たい演劇』の戯曲が【三田文學】に掲載されます。読みましょ🌜https://x.com/emotojunko/status/1967922743086858340🎸LOST BACK’ POINT 東京と名古屋でライブです お近くの方ぜひ〜🎤Lost Back'Point Medicine's release tour "HOME CALL”10/13 名古屋 上前津Club Zion"https://x.com/LostBackPoint/status/195739898858557075510/15 東京 SHIBUYA THE GAMEhttps://x.com/SHIBUYATHEGAME/status/1966725406708691411🧃喫茶こん 10月の予定です 早いんもんでもう10月🧁https://x.com/cafe000con/status/1972229134056411567🌈成田真由美さん主催「アートカフェ⁺さっぽろレインボープライドで『多様な性のあり方』を考えてみる」無事閉幕のご挨拶⛱️https://www.facebook.com/share/p/1VfDCbPQhB/?mibextid=wwXIfr🐈昨日のMIKAさんの絵 毎日更新 癒されます〜🐸https://www.instagram.com/p/DPJ4w1Fkqmu/🔥佐野和哉さんが開く場所「takibi」のオープニングイベントがありました(9/27)https://takibi.torch-inc.jp/🎤リンノスケさん きっとろんどん東京第2回公演『首2』(11/27-)https://www.instagram.com/p/DODKEx6E4Nz/?img_index=1👀今村育子さん CAIで展示中「アパートⅡ -3人の住人たち-」(-11/2)https://cai-net.jp/exhibition/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e2%85%b1-3%e4%ba%ba%e3%81%ae%e4%bd%8f%e4%ba%ba%e3%81%9f%e3%81%a1/🌟風間天心さん Muroran Art Project「鉄と光の芸術祭2025」https://www.instagram.com/p/DPJII3Mj88Q/?img_index=110/18は吐き出し喫茶のゲストに登場🥛鷲尾幸輝さんの個展「milk」を巡って書かれた文章たちMasayuki Saitohhttps://note.com/masayukisaitoh/n/ned7e3d09205amegumimorimotohttps://note.com/megumimorimoto/n/n2ee374650e25北海道美術ネット新館https://h-art.hatenablog.com/entry/2025/09/11/104906?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadDqdijqnX6VLZ9mflZ-cuh6eRD-U2VWPv-PqJzj3ImtnTgIpsKddRKqq6zFg_aem_lD6FG6n2_zatzVsR4d-E0w🧑🎨藤谷康晴さん個展◆さんかく「TASOGARE」2025年10月21日(火)〜10月26日(日)https://www.f-y-drawing.com/🥁紅月鴉海さん 舞踏×ドラムのコラボ公演(2026/1/30)https://ws.formzu.net/sfgen/S881148539/🐾菊澤好紀さん 韓国で踊ります。https://www.thehouseconcert.com/sub/concert/schedule_view.php?idx=1276👊わんわんズさん 「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 10月お申し込み!https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8iX7OK71czJQhwPI8ZbBiMywuTBMygBK4lzKV_SeTEwm2-w/viewform☕高田陽子さん2人展 絵本とcafeゴルディロックスにて(10/31~)https://dogin-bunkazaidan.org/newsdetail.html?id=287
ハウスサバイバルアワード EZO PUNKS! 画家・藤谷康晴さんと伴走#1 #ハウスサバイバルアワード 藤谷康晴さんと伴走#1EZO PUNKS!展示会場探しで札幌放浪2022.10.10text 櫻井ヒロ(HAUS)ハウスの支援とサバイバル・アワードについて詳しく知りたい人はこちら作品展示場所探しで札幌放浪HAUSサバイバルアワード個別編にて、画家の藤谷康晴さんから相談を受けました。藤谷さんはハイパードローイングという過剰な線描と色彩で絵を描く手法で作品を作っていて、今回は彼が8年かけて作り上げた江戸の大首絵をベースにして作られた作品シリーズ「EZOパンクスの肖像」全32点(作品のサイズは123×88cm、96×69cm)を長期間展示(1カ月くらい)できる会場(既存の場所ではなくラジカルなロケーションが望ましい)を探したい、ということでした。2022年10月10日に※¹なえぼのアートスタジオで待ち合わせをしました。一階のギャラリーで海外のアーティストさんの展示も開催しており、会場候補の下見も兼ねて。その後車の中でミーティングをしました。コロナ禍でパブリックな場での長時間の話し合いが難しくなり、車の中などで話す機会も増えました。窓を開けて全員が同じ方向を向いて話せるというのが良いです。藤谷さんはが画家業と共に高齢者介護の仕事もされていて、施設の感染状況によっては打ち合わせを延期せざるを得ない事もありました。藤谷康晴さん作品「EZOパンクスの肖像」の一枚果たして個展は開催できるのか!?車内では「※²PROJECTAさんの美術家支援プログラム『※³サッポロアートインデックス』に申請するのはどうか?」という話になりました。申請の〆切が迫ってましたが、作品全部を展示できる大きな会場、かつ長期展示したい、という藤谷さんのこだわりを鑑み、今回は申請を辞退することに。驚きました。ダメ元でも申請して通れば、数万円~多ければ数十万円かかる個展の為の資金が手に入るのに…。また助成事業に採択されると、開催期限があるので嫌でも背中を押してもらえる、そういう良さもあるのです。うーむ…信じられない、これが「EZOパンクス」ということなのだろうか…。本当に個展は開催できるのでしょうか。伴走者である私の頭の中は予想外の出来事がおき、エラーが起きています。この感じ、子育てとよく似ています。自分のフレームの外に連れていかれる感じ。はい、嫌いじゃないです。口が開き力が抜けます。個展開催のめどは立っていませんが、そもそも私の仕事は個展を開催することなのだろうか…あぁ、ぐるぐるしてきた…。今日はもうこの辺にしておきましょう。とにかく、近頃アート不感症気味の私には、気づきの多い第一回目のミーティングとなったことは間違いありません(笑)。今後、この展示の顛末はこのホームページでリポートしていきたいと思います。藤谷康晴さん作品「EZOパンクスの肖像」の一枚※¹ 元缶詰工場を改装し、札幌を活動拠点とするアーティストが中心となって運営、管理を行っているアートスタジオ。10組以上のアーティスト制作スタジオ群をはじめ、日本で最も古くから続いているアーティスト・イン・レジデンス、写真スタジオ、不動産店、いくつかの企画ギャラリーなどが入居している。naebono なえぼのアートスタジオ※² 一般社団法人PROJECTA(プロジェクタ)—展覧会の企画、公共空間でのアートプロジェクトの企画運営、まちづくり活動、コミュニティスペースの運営、アートスクールの企画運営など、現代美術を軸に「社会を柔らかくする」活動を続けている。 一般社団法人PROJECTA※³ 「アーティストの普段の活動」を支援することを目的に、PROJECTAが実施した芸術家支援プログラム。 令和4年度 札幌市文化芸術創造活動支援事業。Sapporo Art Index藤谷康晴1981年3月11日生まれ。北海道在住。ハイパードローイングという技法を用いて、「異形の存在」をテーマに、ドローイング作品を制作している。藤谷康晴/YASUHARU FUJIYA WEBSITE
ニュース Vol.3 LONG TIME NO SEE DOCUMENT AUGUST 2025 #ニュース ニュースVol.3 LONG TIME NO SEE DOCUMENTAUGUST 20252025.8.25コロナ禍頃から、ハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🍡HAUSの雑談窓口 8/29 20時〜@Xのスペースにて ゲストは成田真由美さんアーティストの自治もままならぬのにオーディエンスの自治について動き始めちゃったオープン・コミュニケーターの成田真由美さんをお迎えします〜https://x.com/haus_Hokkaido/status/1957443127301857609🧃喫茶こん店主の徳山まり奈さん出演中 札幌演劇シーズン2025 ヒュー妄 8/30まで@演劇専用小劇場BLOCH https://x.com/humowa_bot/status/1944620781020807672?s=46🍹喫茶こんの9月の営業スケジュールhttps://x.com/cafe000con/status/1957362164001640688🐟劇団ファイヤーワークスさん代表作『畳の上のシーラカンス』を、石川県金沢市にて上演します(11/1〜2)geimura.com/drama/krt2025/👚小林知世さん PARCO50周年のタイアップTシャツを描きました。8/23〜9/7 Sapporo PARCO 50th anniversary T-shirts Exhibitionhttps://www.instagram.com/p/DNQTKT8S5sf/🎨藤谷康晴さん ハイパードローイングパフォーマンスを実施しました。2025.8.25 YASUHARU FUJIYA hyper drawing [-de]monsterhttps://x.com/sanotae/status/1954144617567293882?s=46🌕紅月鴉海さん 中秋の名月に何かあるかもしれません。https://x.com/karasunotobuumi/status/1955581203479932932?s=46🌟菊澤好紀さん 石山キャンドルナイトに出演します。https://www.instagram.com/p/DNF4RLTzrVP/?img_index=2&igsh=MXBwODlmM2JtOG91cg==🥛鷲尾幸輝さん salon cojikaで個展「milk」を開催中。https://www.instagram.com/p/DM0MrNUhfRK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aTl3dmd6cmt5cWN5📚佐野和哉さん 8/24(日)、文学フリマ札幌に出展しました。https://www.instagram.com/p/DNnubV0zdE2/?img_index=1👊わんわんズさん 「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 9月予定!https://one-ones.com/2025/08/25/one-class9%e6%9c%88%e4%ba%88%e5%ae%9a%ef%bc%81-3/🖼️小林和也さん 初の個展開催!8/30-31は整理整頓展も🧹https://www.instagram.com/xiaolinxiaolinheye?igsh=aGFvMXpkYjQxc2w4🌈成田真由美さん レインボーパレードを一緒に歩きませんか?https://www.facebook.com/share/p/1YgWPoYpu6/🦔ハリー司さん 複合マイノリティ当事者との対話の会(10/15)https://sites.google.com/view/harryandally/home🌌monaさん 8/30-31整理整頓展🧹 in ポン ピイェ ハウスhttps://www.instagram.com/mona_watanabe/🏖️きたまりさん 吐き出し喫茶に登場9/27土 きたまり (コレオグラファー) 場所:イートアライブ 13:00-17:00https://hakidashi.piyopiyoarts.com/20250709-2/📅札幌市文化芸術創造活動支援事業 イベントカレンダーhttps://timetreeapp.com/public_calendars/sozokatsudo【募集中】サッポロアートインデックス(参加アーティスト募集)【募集中】吐き出し喫茶(プロボノ募集)【募集中】スパークプラグ・アライアンス(2次募集)👒フリーランス法スタディーズ 9/12 16:00-17:30 フリーランス法にまつわるアートの現場の事例を知っておこう〜 日本芸能従事者協会×公正取引委員会https://33awj.peatix.com
ニュース Vol.2 LONG TIME NO SEE DOCUMENT JULY 2025 #ニュース ニュースVol.2 LONG TIME NO SEE DOCUMENTJULY 20252025.7.22コロナ禍頃から、ハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🦀ハウスの雑談窓口始まります。 7/25 21時からXのスペースで話します。雑に話しましょう〜🐳001「中学校の演劇部って誰のためにあるの?」🐝 VOICE:竹原圭一さん ❄THE ICEMANSひらめきを形にするまでのスケッチとして、ライブ配信をしました💃SHINOHARA KENSAKUさんパフォーマンスをしました@カリフォルニア🎵小林知世さん絵画と楽曲活動。「川で偶然居合わせた人間とヒバリ、そのさえずり飛翔」🖌藤谷康晴さんライブドローイングのお知らせ。8月9日(土)チカホにて。🎶🎶菊澤好紀さん2025〜2026スペインツアーがあります。良い旅を〜。🌺リンノスケさんKAAT×TJP『#ダンスマラソンエクスプレス(横浜⇔花巻)』日本公演終演!次は10月のフランス国内ツアー。🐙OCTOPUS BOYロゴ制作など継続中🏠内田聖良さん アーティストインタビュー「Katsurao AIR(カツラオエアー)福島県葛尾村に滞在中です。7月24日〜27日オープンスタジオ形式の活動報告会もあり⭐️👊わんわんズさん 「演技・アクション素手・殺陣」わんクラ 8月予定!https://one-ones.com/2025/07/08/one-class8月予定!-3/🦔ハリー司さん 複合マイノリティ当事者の勉強会(8/15)https://forms.gle/c7r2wQFz5KAC6ocf8🏕️北海道テントサウナ団 小林和也さん🪐株式会社TETSUGAKU 設立https://tetsugaku-inc.com/☕成田真由美さん アートカフェ⁺ 🪕民族音楽(7/23)https://www.facebook.com/share/p/1C62VdmzCQ/☕成田真由美さん アートカフェ⁺ 🌈さっぽろレインボープライド(9/25)https://www.sprrainbowpride.com/event2025/artcafe2025🏖️プレイバックゆう 発表会@白老(8/9)ハウスメンバーも勉強中の集団精神療法のひとつ、プレイバックシアターの発表会があります。☕吐き出し喫茶 7月26日は小林大賀さんゲストです。喫茶店の形を借りて、夢や愚痴を吐き出すあそびのようなもの。様々な分野のアーティストたちが、ゲストや店員として待ってます。https://hakidashi.piyopiyoarts.com/20250709-2/🦖鐘下辰男氏による演技の基本を考えるワークショップ @zoo(8/26&27)演劇企画集団THE・ガジラ主催の鐘下辰男氏を講師としてシアターZOOに招聘して演劇の基本を考えるためのワークショップを開催します。7月の初日楽しかったです。是非!🍡成田真由美さんのFBから引用。アーティストの公募や文化芸術を支える人材育成や一般参加のプログラムがあります。(7/25)令和7年度札幌市文化芸術創造活動支援事業~合同説明会
ニュース Vol.1 LONG TIME NO SEE DOCUMENT JUNE 2025 #ニュース ニュースVol.1 LONG TIME NO SEE DOCUMENT JUNE 20252025.6.23コロナ禍頃から、ハウスと一緒にサバイバルしたアーティストたちの「こっから」を、勝手に紹介ドキュメント。多分マンスリー。🐰LOST BACK POINTさん ライブのお知らせhttps://t.livepocket.jp/e/lostinwanderlands🍮純喫茶ヒッピーさん レトロな純喫茶を日々紹介https://x.com/JunKissaHippie🌈櫻井幸絵さん 公演のお知らせhttps://www.facebook.com/yukie.hashiguchi.75/posts/pfbid0Twj4RV6Ywe3E8CdXzeih7iajLEGtuPuqfw2mNsFnFeuQvyzE3TeKPCj6qouP6x8Rl?rdid=UYV2kx8S0GwoybHs#🐝江本純子さん 上映情報と文学賞最終候補に!https://x.com/kegawazoku2000/status/1934525334453731518https://x.com/ainochaban/status/1936987331216695539❄️mona この数ヶ月の近況https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nxs5SCvVyS5jetnsGcmGaicY2UWfJKhT7dv526dRk4z1nvYey7TjMA7abAyD5J69l&id=100010034880167&rdid=zSRIXQYqn4VbyAL2#🍹喫茶こん あと一週間だけど6月の喫茶予定https://x.com/cafe000con/status/1926519853847822639🌺山田大揮さん 起業しましたhttps://note.com/ayamelab/n/n33006eda9b79?sub_rt=share_pb&fbclid=IwY2xjawLGJGRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPMzREVlhPTjY2ZEQ2NVdtAR7r-sjKbmuV5LSbIcv1bCk_dbB5OIFDO4eBUGEtfWAWuoF4DUV5da-SEZMsMA_aem_K1-K79EGqVZeVjZbquw3kQ🐈N.MIKA MIKA展おつかれさまでしたhttps://www.instagram.com/n.mika6621/🌸リンノスケさん 『ダンスマラソンエクスプレス(横浜⇔花巻)』始まるよ!https://www.instagram.com/p/DLKZCkmRvgg/?img_index=1🎤佐野和哉さん ポッドキャストやってます。「録音の肉声」 - アートとテクノロジーのポッドキャストhttps://www.youtube.com/@rfv_podcast🐘風間天心さんの展示予定8月末に築地本願寺で予定している「MONK ART GUDO 展」の実現に向けたクラウドファンディングhttps://camp-fire.jp/projects/830612/view?list=art_popular&fbclid=IwY2xjawLGGRBleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETF0UnBid2RiUjF3eFZ2YkNYAR5QU6AogaaoVUVYiQ7DYZe8rapduhcsMh_qhzKB1ngdaN-VcyitUMkbp3o8Cw_aem_dWBLK2O1FZXy0Jf4umrCNg展示情報https://www.facebook.com/share/p/191v7YF1jt/ワークショップ等https://www.facebook.com/share/p/18k5CvLhCZ/☕成田真由美さん アートカフェ⁺のお知らせhttps://www.facebook.com/mayumi.narita.908/posts/pfbid0jJzMVTVHNEnj8pmnki4UJKTwctnYq4axXqgmBHoq7k7qSTdZ6aTwTv9juv9vqUjxl?rdid=TOr5Kb759MqcSSnr#👊わんわんズさん 「演技」「アクション素手」「アクション殺陣」教室 わんクラ7月予定!https://one-ones.com/2025/06/11/one-class7月予定!-3/🦔ハリー司さん 複合マイノリティ当事者の勉強会(8/15)https://forms.gle/c7r2wQFz5KAC6ocf8🏕️北海道テントサウナ団 サウナと哲学活動🌿https://x.com/hokkaidotensau🍎日本芸能従事者協会さんから、フリーランス法勉強会のお誘いレターですhttps://x.com/ArtsWorkersJpn/status/1934837054657212521
ニュース 「美術をめぐる脱中心の実践・報告・集会 2025」に参加します #ニュース ニュース「美術をめぐる脱中心の実践・報告・集会 2025」に参加します2025.3.24北海道、秋田、鹿児島、広島、沖縄から、アートに関わる人々の権利向上や制作環境改善の取り組みの実践の報告・意見交換各地で見られるアートに関する主体的な権利向上や制作環境改善の取り組み。2023年に「美術に関わる脱中心の実践・2023・報告」で集まった各団体は、その後どのように活動しているのでしょうか。それぞれの地域の事情などを持ち寄り、共有するためのシンポジウムにHAUSも参加します。対面の会場は沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)です。オンライン配信もありますので、皆さま是非ご参加ください。「美術をめぐる脱中心の実践・報告・集会 2025 第2回活動報告集会」2025年3月30日10〜12時(9時50分開場)場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館実習室参加団体:ヨルベ trunk HAUS(Hokkaido Artists Union Studies)、かわるあいだの美術実行委員会 サゴリに集うひろしま有志の会、art for all アーティスツユニオン司会:小田原のどか、山本浩貴定員:30名 要予約 参加無料助成:小笠原敏晶記念財団協力:ヨルベ、アーティスツユニオン(プレカリアートユニオンアーティスト支部)▶参加申し込みhttps://forms.gle/cbsxcr75oShhAxDV7<2023年のイベントレポート>https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/de-centered-practice-on-art-report-202407https://bijutsutecho.com/magazine/insight/28468
ニュース 「もうひとつの声」HAUSが演劇(みみつぼ)をやってみる #ニュース ニュース「もうひとつの声」HAUSが演劇(みみつぼ)をやってみる2025.1.15「もうひとつの声」HAUSが演劇(みみつぼ)をやってみるを開催します🍄2019年、北海道のアーティストの働き方とそのプライドに関しての勉強会が、HAUSの始まりでした。やがて「なんだか困ってる」と声をかけられ、以来、60人ほどのアーティストの相談や苦労話を聞き、より快適な方向へ近づくために、その人だけの一品料理をこさえてゆくような支援活動をしています。そんなHAUSが、活動のレポートでは掬えきれない日々の光景を、演劇を通して視聴嗅覚触の五感化というか、直感も含め立体化を試みようということで、さあさあ、お立ち会いです。<公演情報>🐙申し込みURL:https://the-other-voices-haus.peatix.com/2月15日(土) 16時開演2月16日(日) 16時開演🐘両日とも開場は15時40分となります。会場:三〇一会館(札幌市東区北20条東1丁目2-41前田ビル301号室)チケット:2500円※生活保護の方は無料です。申し込む際に、チケット種別からお選びください。または、 hello[a]haus.pink へご連絡ください(メールアドレスの「[a]」は、「@」に置き換えて送信してください)。出演:HAUSとDJ倒木イラスト・ロゴ:OCTOPUS BOY主催:一般社団法人 WHO CARES助成:生活クラブ福祉基金🍭ご参加頂くにあたり、身体的・心理的な不安を感じられる方がいらっしゃいましたら個別に対応しますので、気軽にお問い合わせください。<HAUSについて>北海道のあらゆるアーティストの活動環境問題にただただ心を痛めている場合ではないと、2019年秋に設立。アーティストの自律を駆り立てる芸術的社会的な基盤を目指す中間支援団体です。以来、創造の現場における様々な”声”を掬い取り、舞台作品上演や、現場のハラスメント実態からつくられたリーディングなど”声”の可視化に取り組んでいます。(メンバー:奥村圭二郎、櫻井ヒロ、戸島由浦、箱崎慈華、羊屋白玉、渡辺たけし)
ニュース シンポジウム「放たれた対話と未来」開催 #ニュース シンポジウム「放たれた対話と未来」シンポジウム「放たれた対話と未来」を開催します2024.11.24シンポジウム「放たれた対話と未来」を開催します🐬こんにちは。ハウスです。令和4年に全国でもユニークな文化事業が札幌市で行われました。4つの芸術文化支援団体がアーティストと行政の仲介役となり、直接支援を行いました。当時の彼らの東奔西走の日々を経て、これからどこへ向かってゆくのか。観客の方々といっしょに話してゆきたい6時間です。ぜひ、お集まりください〜🍄シンポジウム「放たれた対話と未来」🐰日時:2024年12月12日(木)14:00~20:00🦋会場:札幌市教育文化会館(札幌市中央区北1条西13丁目7)4階 403研修室🌲参加費:無料🍭ご参加頂くにあたり、身体的・心理的な不安を感じられる方がいらっしゃいましたら個別にご対応しますので、 hello[a]haus.pink へ、気軽にお問い合わせください(メールアドレスの「[a]」は、「@」に置き換えて送信してください)。🐘参加方法: 会場参加・オンライン参加申し込みURL:https://hello-haus-pink-20241212.peatix.com*アーカイブ配信については検討中です。🦞登壇団体: HAUS (発起人) AISプランニング PROJECTA 北海道演劇財団🐏司会:本田修🐯タイムテーブル:14:00 第一部 [クロストーク]「何があったのか?今どうしてる?これからどうしたい?」札幌市文化芸術創造活動支援事業18:00 第二部 [フィードバックとこの先へ]「この日の話し合ったことを、演劇の手法を使って振り返り、未来を想像してみよう〜」20:00 おしまい🌹この活動は(一社)AISプランニングが札幌市文化芸術創造活動支援事業の助成のもとで実施するコーディネーター育成事業の一環として行っています。
インタビュー アーティストインタビューを掲載しています #インタビュー インタビューアーティストインタビューを掲載しています2022.8~2023.1HAUSでは、北海道・札幌を中心に活動するアーティストへインタビューを行っています。芸術活動と別の仕事を持つ「兼業アーティスト」や、アート一本で生活する「専業アーティスト」、これからブレイクを待つ「若手アーティスト」や、すでにリタイアして伝説化している「レジェンドアーティスト」。さらには、育児で少しの間活動を控えめにしているアーティストなどもいらっしゃいます。北海道・札幌の、さまざまなジャンルのアーティストに、広くお話しを聞いていきたいと思っています。2022年8月~2023年1月までのインタビュー第一期では、6人のアーティストにインタビューを行いました。少しずつアップロードしていきたいと思っています。#1 大川敬介さんインタビュー演技と生活をリンクする日々を見つめて「深化」する俳優#2 森本めぐみさんインタビュー生活とfloatする美術家子育てで変遷する制作スタイル#3 鈴木喜三夫さんインタビュー札幌で初の専門劇団をつくる戦後北海道と歩んだ演出家#4 きたまりさんインタビュー「働く」ことの仁義について北海道・京都2拠点で創作する振付家
報告 アーティスト支援の記録 2022〜43の困りごとと伴走内容と分析〜 #報告 報告アーティスト支援の記録 2022〜43の困りごとと伴走内容と分析〜2022年にHAUSが行った40組の伴走支援の内容とその数です。アドバイザ、専門家を紹介したり、アーティスト同士が出会う場所を作ることで、解決を模索した例が多数ありました。生活と制作と心身の悩み・バイト先の未払い、不当解雇へ交渉や同伴:2件 ・出演や出展の契約書の作り方と交渉や同伴:3件 ・精神疾患を携えながらの生活と制作へ見守りやアドバイス:5件 (相談を受けるにつけ、仕事先や、集団創作環境や、家族間に共通する、年代や、ポジションが上の人たちからのパワーハラスメントや、想像の欠如や、無理解によるものではないかと、それぞれの要因が透けて見え始めてきています。)ネットワーク1(アドバイザなど専門家を紹介 )・契約書の作り方と交渉を弁護士と:3件 ・バイト先の未払い交渉を弁護士と:2件 ・知人の企業からバイトの募集があり紹介し就職:1件・アートスペース探しのため不動産屋さん紹介:2件 ・税理の相談から税理士の紹介:1件 ・移住して間もない方への後方支援:2件 (助成採択前に移住してきた為、何もネットワークが無かったので、広報や制作支援のような人的な支援を行いました。)ネットワーク2(アーティスト同士をつなぐ )・世代や分野を越えて会話する場の生成:4件 (舞台制作について似たような課題意識を持っている若手演劇人や、子育てをしながら作品づくりを続けるアーティストが懇談する機会があり、急遽、ファミリーサポートとしてご飯を作りにゆくグループも立ち上がりました。)・人が集まる場所づくりをしている同士の交流:3件 (今回の助成をきっかけとして立ち上がったアートギャラリーや、既存のアートスペースでもアーティスト同士の意見交換がありました。)・アーティスト同士の作業手伝いを通した連携:5件 (異ジャンルのアーティスト同士が、お互いの活動への興味関心から、作品制作の作業の手伝いやアドバイスを受け合う連携がありました。)各種製作への資金支援✳︎2022年度は、札幌市文化芸術創造支援事業に採択されたので、資金支援を行いました。・ミュージックビデオ製作:2件 (2件とも初めてのミュージックビデオ製作でした。特に、若い世代のミュージシャンには、活動を広げるための大事な取り組みなのだそうです。) ・初めてのワークショップ:2件 ・コロナ禍の作品発表で赤字を抱えた:1件 ・制作に入る前のリサーチに特化して深く行いたい:3件 (作品制作の一環としてリサーチや研究の支援を要望、リサーチを対象にした助成制度の公募の数はまだまだ少ないことがわかりました。)
ニュース 「アートに何ができるのか?」 山出淳也さんをゲストに開催 #ニュース 「アートに何ができるのか?」開催2023.12.3text 渡辺たけし(HAUS)「アートに何ができるのか?」ゲスト:山出淳也さん(アーティスト/Yamaide Art Office株式会社 代表取締役/BEPPU PROJECTファウンダー)大分県別府市で多様な主体と連携・協働し、様々なアートイベント等を仕掛けてきた山出淳也さんを札幌にお招きし、シンポジウムとラウンドテーブルを開催されます。HAUSも少しだけお手伝いしています。山出さんの著者「BEPPU PROJECT 2005-2018」も読みました。地方で行われるアートプロジェクトと地域おこしの原点が書かれている名著です。今回のイベントにも、ジャンル問わずたくさんの方が参加いただけるといいなと思っています。◆日時2023年12月16日(土)11:00~13:00<シンポジウム>「アートがひらく地域の可能性 〜別府のアートプロジェクトの取り組みから〜」2023年12月16日15:00~17:00<ラウンドテーブル>「アートをこえて、アートにたつ。」◆会場北海道教育大学札幌駅前サテライト 教室1(札幌市中央区北5条西5丁目7 sapporo 55 紀伊國屋書店 札幌本店ビル4階)◆参加費無料(事前申込要)<シンポジウム>●プログラム 【基調講演】山出淳也さん 「アートがひらく地域の可能性 〜別府のアートプロジェクトの取り組みから〜」誰からも頼まれることなく一人のアーティストが始めた多様な取り組みが、文化の枠を超え地域の課題解決や新たな価値の創出につながっています。時に無謀と言われながらも実現してきた企画の数々を6つのカテゴリ=事業ドメインに分けて紹介します。国内最大規模に成長したアートNPOが何を目指してきたのか、そして、地域の持続的な活性化には何が必要になるのかを語ります。【パネルディスカッション】登壇者(順不同・敬称略) ‣山出淳也(アーティスト/Yamaide Art Office株式会社 代表取締役/BEPPU PROJECTファウンダー) ‣大西洋(北海道教育大学岩見沢校美術文化専攻 イラストレーション研究室 准教授) ‣閔鎭京(同上 芸術・スポーツビジネス専攻 芸術文化政策研究室 准教授) ‣モデレーター 酒井秀治(同上 美術文化専攻 まちづくりデザイン研究室 准教授)<ラウンドテーブル>「アートをこえて、アートにたつ。」●進行:森嶋拓さん(CONTE-SAPPORO Dance Center)◆参加申込共通フォームhttps://forms.gle/kNSfwRiJmDygfrKp9*〆切:2023年12月16日(土)11時◆問合せ閔 min.jinkyung@i.hokkyodai.ac.jp◆主催北海道教育大学岩見沢校イラストレーション研究室/まちづくりデザイン研究室/芸術文化政策研究室、北海道×九州文化芸術交流
ニュース 「美術に関わる脱中心の実践2023・報告」に参加します #ニュース ニュース「美術に関わる脱中心の実践・2023・報告」に参加します。2023.12.10text 戸島由浦(HAUS)12月11日(月) 各地の、アートに関する主体的な権利向上や制作環境改善の取り組みとの意見交換アーティスツ・ユニオンが主催する「美術に関わる脱中心の実践・2023・報告」に参加いたします。近年、各地でアートに関する主体的な権利向上や制作環境改善の取り組みが見られます。地域に合わせた形でそれぞれの取り組みがありつつ、つながって連携していくと良いのではないか、そのためにまずはお互いを知ろうと、10月頃から話し合いが始まっていました。今回の参加団体以外にも、意識を共にできる団体は恐らくたくさんあると思います。どのように繋がっていくか、ということ自体が課題でもあります。事前に参加団体と話す機会がありました。活動形態や内容はそれぞれ異なりますが、それぞれの実践を知っていくことで、活用できる事例が見つかったり、自分たちの活動を客観的に考察できたりするのではないでしょうか。HAUSや札幌における芸術活動環境についても改めてご紹介します。平日ですが、お時間の合う方は是非ご参加ください。以下概要を掲載いたします。「美術に関わる脱中心の実践・2023・報告」開催のお知らせこの度、長年にわたり「ジェンダー×植民地主義×広島」についての実践を重ねてきた「ひろしま女性学研究所」が運営母体となり、「加納実紀代資料室サゴリ」が広島市内に開設されました。「銃後史」「脱植民地主義」「反天皇制」「ジェンダー」「平和表象」「ウーマン・リブ/フェミニズム」「朝鮮・アジア」など多様な角度から言論活動に取り組んだ加納実紀代さんの遺志を引き継ぐ「サゴリ」を拠点に、「美術に関わる脱中心の実践・2023・報告」を開催いたします。近年、各地でアートに関する主体的な権利向上や制作環境改善の取り組みが見られます。2023年9月には鹿児島で「かわるあいだの美術2023」(企画:かわるあいだの美術実行委員会)が開催され、11月には沖縄で「なはーとカンファレンス2023」(企画:「アーティストの条件」企画チーム)が、また同月には秋田で「例えば(天気の話をするように痛みについて話せれば)」(企画:trunk)が開催されました。このたびの会では、それらの展覧会やカンファレンスを主催した団体のみなさんに取り組みのご報告をいただきます。「加納実紀代資料室サゴリ」の「サゴリ」とはコリア語で「交差点」を意味します。このミーティングがその名の通り交差点として機能し、ハラスメントをなくすことや労働環境の改善などに取り組む各団体の、今後の活動をいっそう豊かにする一助となることを願っています。アーティスツ・ユニオン・ジャパン オブザーバー小田原のどか(彫刻家・評論家)▶詳細[開催日時]2023年12月11日(月)14時〜18時[開催場所]現地(加納実紀代資料室サゴリ・広島)+オンライン[参加費]無料[主催]アーティスツ・ユニオン(プレカリアートユニオンアーティスト支部 問い合わせ担当:小田原のどか)[プログラム]各団体の取り組み紹介、意見交換、励まし合い[ファシリテーター]小田原のどか(彫刻家・評論家)、山本浩貴(アーティスト・文化研究)▶サゴリについて:ポリタスTVhttps://www.youtube.com/watch?v=Vu51mJc64Ds▶参加予定団体[沖縄]「アーティストの条件」企画チームhttps://www.nahart.jp/course/1696499152/[北海道]HAUS | Hokkaido Artists Union Studieshttps://haus.pink/[秋田]trunkhttps://sylvester-shifu.com/[広島]サゴリに集うひろしま有志の会[鹿児島]かわるあいだの美術実行委員会https://kawaruaidanobijyut.wixsite.com/aidaアーティスツ・ユニオンhttp://artistsunion.jp/▶申込申し込みフォーム https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8X_zfXndQ-lq_lpx9swNUSqeXIdQ5heuXMDsgikViN2ELg/viewform?usp=sf_link▶この件に関する問い合わせ先小田原のどか support■artistsunion.jp(■→@)
インタビュー 「働く」ことの仁義について 北海道・京都2拠点で創作する振付家 インタビューその4 振付家きたまりさん #インタビュー インタビューその4振付家きたまりさん「働く」ことの仁義について北海道・京都2拠点で創作する振付家Text : 渡辺たけし、奥村圭二郎(HAUS)Photograph : 長尾さや香Place : きたまりさんのお宅(札幌市)2022.12.18HAUSアーティストインタビューは、札幌で活動するアーティストを、たくさんの人に知ってもらいたいという思いからスタートしました。第1期は2022年夏から2023年春に取材したさまざまな分野のアーティストを順次掲載します。2022年に、突然京都から北海道に移住して来たきたまりさん。日本のみならず、世界中を制作の場として活躍するきたまりさんが、京都と北海道の2ヶ所を活動場所に選んだ理由などお聞きしてみました。それから、いくつかの拠点で活動する時の意外なメリット、デメリットも教えて頂きました。そのほか、きたまりさんの興味深い「労働感」についてもお話しいただきました。北海道を移住先に選んだ本当の理由?(2022年にきたまりさんは京都から札幌に引っ越してきました。お話しは「北海道で暮らすには車は必需品ですかね?」「北海道では馬を見たいです!」などの雑談からスタート。そして本題に入りました。)ーHAUSでは、アートと労働を考えるるというインタビューをさせていただいています。ぼく自身もインタビューは素人なので、気軽な気持ちで答えてくださいね。わかりました。インタビューにまとめるのって大変ですよね?ーそうですね。苦労しています(笑)。わかります。ー生まれはどちらですか?生まれは岡山なんですけれど、育ちは大阪なんです。ー何年生まれですか?1983年生まれで1982年生まれが同期です。宇多田ヒカルと一緒です(笑)。ー天才や鬼才が多い世代ですね(笑)。ー京都で長い間創作を続け、2022年から北海道に移住されました。京都と北海道2拠点で活動をされていますが、北海道を選んだ理由はなんだったんですか?元々、母方が北海道なんです。ー北海道のどこですか?黒松内町なんです。※黒松内町=北海道後志(しりべし)管内南端にある町。ブナ北限の地として知られている。畜産が盛んで牛肉、チーズが格別。一度食べに来てほしい。ー今も親戚はいるんですか?います。母方の親戚はみんな北海道の人なんで、ちっちゃい頃から話を聞いてたし、遊びに行ったこともあるし。ー縁や憧れみたいなものがあったんですね。そうですね。でも、やっぱり、コロナの影響が大きかったっていうのもあります。コロナ前に最後にレジデンスで行ったところが中国雲南省でした、本当に何て言うの・・・「草」!ー「草」ですか。草原が印象的でした。標高2400mに町があって、綺麗で、すぐ停電になる。何もなくて広いところでした・・・。そんな雲南滞在の後に、広いところで暮らしてみたい気持ちがじわじわでてきてて。長く暮らしていた京都って、やっぱりすごく狭いんです。ー確かに京都は小ぢんまりしている印象ですね。コロナの自粛期間、京都以外の場所に出かけることが減って、ただただ広いところに行くことで何かがリセットされてる気になるから、そんな欲求がつのって。ー自然が好きなんですか?自然が好きなんだと思います。人が多いのは駄目なんですよ。タッパがちっちゃいっていうのもあるんですけど。それから、京都って、でっかい建物がないですよね。やっぱり、常に見晴らしがいい方が圧迫感がないので、その方が生きやすいっていうのがあって。ー新しいところに来たら高いところに登るのがいいと『ゴールデンカムイ』にも書いていましたね。身を守るという意味でも。※『ゴールデンカムイ』=野田サトルの漫画。明治末期の北海道・樺太を舞台にしたアクション漫画。アイヌの娘アシリパと日露戦争からの帰還兵「不死身の杉本」がバディとなり冒険の旅を続ける物語。高いところに登ると町の地形がわかるんですよね。わたしも新しい場所に行った時は、とりあえずその町にある山に登るか、高いところに上がってみますね。本題の「なぜ北海道を選んだか?」という話は少し長くなりますが、いいですか?ーぜひ、お聞きしたいです。コロナになって最初の頃は、やることがないから京都市内を散歩ばっかりしていたんです。その時に、ものすごく理想的な墓を見つけたのね。ー墓?ロケーションが良くて、「ここ入りたい!」っていう憧れの墓みたいなのを見つけたんです。奥にある木の感じが良くて、霊山がほどよい場所にあって・・・という感じの理想的な墓場だったんです。家に帰って早速調べて資料請求したら、墓石代なしで300万!ー高い!京都市内の墓は高いんだな・・・ってなって。石代とか供養費など合わせると500万ぐらいかかるっていうことがわかって。そのときに「今、私は、500万を私が死んだ後のために一生懸命工面しようとしてる?」って思ったんです。それで500万あれば出来そうなことを、墓以外にちょっと考えるようになりました。ーはい。例えば500万円あれば田舎で中古物件を買えるなとか。ーそうですね。死んだ後のこと、生きてる間のこと、いろいろ何か考えてた矢先に、母親が亡くなったということもあって、それで、実際、墓のことを考えなきゃいけないっていうこともあったし、気持ちが落ち込んでどうしようもなかったので、気分転換に1回引っ越してみようと考えました。最初、憧れの地ということで、北海道の他に長崎や佐渡島も候補地に考えたんだけど。2021年に、ちょうど「RE/PLAY Dance Edit:札幌」という企画で札幌に来る機会があったんです。10何年ぶりに札幌に来たら「水が合うな」と。「RE/PLAY Dance Edit:札幌」(2021年) photo by yixtape※「RE/PLAY Dance Edit:札幌」=オリジナルは、多田淳之介率いる東京デスロックが2011年に発表した『再/生』。2012年にきたまりがプログラムディレクターを務めた「WeDance京都2012」で俳優を振付家・ダンサーに置き換えて、リ・クリエーションしたダンスバージョンが初演され、その後は国内外で4カ国7都市で上演。札幌でのクリエイションは2021年にコンカリーニョで行われた。(2023年現在)ー北海道が肌に合ったんですかね?ですね。山も見えるし、札幌の天気の変わり方って、街なのに山みたいでいいなぁと思ったり。「北海道に住むのはいいんじゃないかな」と思ったんです。ー山が見えないと駄目な人、海が見えないと駄目な人、両方いますよね。私は、山が見えないと駄目なんですよ。2拠点で創作することのメリット・デメリットーアーティスト専業で稼ごうと考えると、北海道在住の場合「東京や大阪に行かなきゃいけない」っていうふうに考える人が、今までは多かった気がします。でも、最近は複数に拠点を置いて活動している人も増えてきています。そうですね。でも、私は拠点が1箇所であることにこだわるのは好きだったんです。墓を買おうと思ったくらいでしたから(笑)。ーなるほど(笑)ただ、思考が狭くなる危うさもあると思う。あとは、その地域の人たちの関係性が全部わかっちゃうのも良くないなって思う。ー「あそこのあの人は、ああいうことを考えてるな」など透けて見えちゃう?なんか、わかった気になっちゃう感じがして。ーなるほどずっと同じ場所にいると、なんだか不自由になっていく感じがして、そろそろ違う場所がいいなとも思っていました。ーこれから複数の拠点で活動する人も増えていくんじゃないでしょうか。その気になれば、本州には簡単に行けるわけですしね。2拠点になることによって、やりづらいこともありますか?引っ越してきてまだ半年だから、わからないことは多いんですけど。ただ、いつも一緒に創作してるスタッフはみんな関西にいます。長い付き合いだから、安心してオンラインで打ち合わせをしていますが、伝わってるだろう思ったら、意図があまり伝わってなかったことなどはありますね。やっぱり、舞台の打ち合わせは全部オンラインだと、フォローできない部分はあるなと思いました。でも、結構、京都にちょくちょく帰ってるんで、今のところ2拠点だから特別困ることはないです。ーオンラインで打ち合わせできるっていうのは、2拠点での活動を後押ししていますよね。オンラインがあることでだいぶ変わりましたね。それから、札幌で生活するようになって、やらなければいけないことがあるのに外出しても、京都のように街中で関係者にばったり会うっていうことがなくなりました。創作中に外出することへの後ろめたさがなくなりましたね(一同爆笑)。今は、創作途中でも、堂々と外に遊びに行くことができるようになりました。ー気分転換に堂々と遊びに行けるマインドもあったほうが健全ですよね。京都では、人に会いすぎるっていうのが負担だったのかもしれない。ー長く活動しているとそうなりますよね。1箇所に長くいることで、いいこともあるんだけど、全てが筒抜けすぎて。京都は小さいですから。そして、今後も知り合いはさらに増えていくわけで。ー年齢とともに。ちょっと不安になるわけですよ。ーわかります。2拠点で活動することで、そういう不安が減るということですかね。そうですね。なんだか健全になりますね。知り合いが周りに多いと、いろんな情報も入ってくるから、周りの意見に流される部分もあるじゃないですか。立地的に距離を置くことで、自分で考える時間がちゃんと持てるようになるかもしれませんね。そういう時間を欲していたんだと思います。専業で働くこと、兼業で働くことーHAUSでは、今まで兼業、専業両方のアーティストにインタビューをして来ました。きたまりさんは、現在は専業アーティストとしてお仕事をされていますよね。専業といえば専業ですね。昔はアーティスト以外のいろんなバイトもしていました。ーどんなふうに活動をして来たのか教えてください。30代のときは公演で赤字が出て、「もう大変っ!」ていう状態もあったけど、逆に20代のころは金銭的には結構恵まれてたと思います。ーなぜ、20代の頃は恵まれていたんですか?幸せな時代だったんですよあのときは(笑)。ダンスのショーケースがすごく多かったんです。大学在学中からショーケースに出ていたので、リスクを背負わず作品を上演できる機会があって、結構、恵まれてたんですよね。それでも、バイトはしてたかな。朝食とかやってたかな。ー朝食?京都はホテルが多いですからね。主にホテルの朝食の配膳のバイトをやってましたね。朝バイトに行って、その後稽古してました。朝のバイトだと、稽古時間を削られることはないんですよね。稽古終わりに飲み屋でバイトしてる時期もありましたけど。でも、歳をとってからは、朝も夜も働くのは駄目になったという感じですね(笑)。一時期はいろいろやりましたね。いろいろあった、いろいろあった。でも、それは言い難い。ーそういうのは言わなくていいです(笑)美術モデルもしてましたね。でも、稽古時間をちゃんと確保できるバイトしかやったことないです。ー生活のためのアルバイトをしなくて良くなった時期はいつからですか?ここ5~6年かな。現場1回あたりの単価が、いつのまにか上がったというのもありますね。経験とか年齢的なものでしょうね。若いときは、ちっちゃい企画っていうか・・・どういったらいいかな。ー単価が安い企画ですか?そうですね。若い頃は、ギャラも安い代わりに拘束時間も短い企画が多かったのですが、今は劇場などからの依頼が増えました。そうすると、逆に現場の回数は減りましたが、単価が上がりました。いつのまにかですけれど。それから、自主公演でも予算管理をしてくれる制作者をちゃんと付けるようになりました。劇場から依頼を受けた時も、私と劇場の間に制作者をマネージメント的な役割として挟むようになったら、不自由ない創作の予算の交渉をしてくれるようになったというのが大きいかもしれないですね。ー北海道や札幌で、創作活動にマネージメントが関わることは少ない印象です。長く札幌で芸術活動に従事されている方でも、企画がスタート時に自分のギャラがわからないという人が多いです。それは、私もわからないことが多いですね。ーそういうものなんですかね。なかなか直接言えないですよね。自分も雇用される側になることもあるし、雇用する側になることもありますもん。ーどちらの立場もわかりますもんね。金額を言えないっていうことは「そういう状況なんだな」っていうふうに察しちゃいます。相手がどういう劇場、団体、個人か、どれぐらいの助成金を取ってるか、どれぐらいの予算規模かで、ギャラの金額は大体予測できるようになりました。ーHAUSでは、契約書やワークルールなどの勉強会もしていきたいと思っています。参考に聞きたいんですが、きたまりさんは、今まで、契約についてはどうして来ましたか?カンパニーとダンサーっていう場合もあると思うし、カンパニーと劇場という場合などいろいろパターンがあると思うんですけども。劇場との契約の時は書面で交わします。戯曲を原作に使ってるときなどは、もちろん用意されてるので、著作権を管理している方と契約は取り交わしますね。ただ、私が主催で創作する時には、スタッフや出演者と契約書を取り交わすということは行っていません。ごめんなさい。ー契約を書面にしなくても、気にしていることなどはありますか?最近は私がダンサー等にオファーする段階では、できるだけ出演料とスケジュール、拘束日程などは先に提示するようにしています。口だけで言っちゃうと自分も相手も忘れちゃうから、残るようにメールでですね。ーあんまり「契約書」と強く言っても、お互いに大変なところもありますよね。企画がスタートした時点では、金額が確定できないっていうのもありますよね。そういう余白もある上で契約書はあった方がいいんだろうなと思います。どうサバイブをしてきたのか?「KIKIKIKIKIKI」についてもーきたまりさんがどんなふうにサバイブしながら仕事をして来たのか教えていただけますか?でも、私のやり方は古いと思いますよ。私はずっと京都という地方都市でやってきました。だから、とにかくまず、首都圏の賞レースで結果を出していこうというのがありました。助成金を取るための最初の通行手形を手に入れるようなものです。いろんな人に見てもらうっていうところから始まっていました。ーなるほど。普段は京都に審査員は見に来ないから、東京に行ってコンペティションに出て、助成金が取れるようになって、キャリアを積んでいくと、劇場から「創作をしませんか」と声がかかるようになりました。そこに入り込むには、まず賞レースに入り込むしかないと思っていた世代だったんです。今はそんなやり方じゃないかもしれませんね。ー今は賞レースにこだわっている人は、確かに少ないかもしれませんね。私はそういう意味で、最後の世代です。当時は、ダンスショーケースなどがたくさんあったし、次世代の振付家を育てたいという状況にのっかってきたから、20代は活動の場に困らずに乗り切れたって感じですよね。大学在学中から公募でJCDNの「踊りに行くぜ!!」に選考されたり、そのあとも関西の劇場やフェスで共同制作や上演機会をもらうことが多かったです。それでキャリアを積んだ感じはありますね。※、「JCDN(NPO 法人 Japan Contemporary Dance Network)」=より豊かな社会を創り出すために、日本全国においてダンスを普及すること、社会とダンスの接点を作ること、ダンスのアーティスト をサポートすること、を目的とする団体。ー僕は、2008年に「KIKIKIKIKIKI」を札幌で観ました。それまでダンスに興味はなかったんですが、これがとても面白くって。カンパニーはどうやってデザインされたのかお話しを聞けますか?※「KIKIKIKIKIKI」=2003年結成。以後、振付家/きたまりの創作の場として京都を拠点に国内外で多くの作品の上演を行うダンスカンパニー。2008年『踊りに行くぜ!! vol.9 in SAPPORO』にて上演。20代のときっていうのは、もう何の計算もしておりませんよね。なんのデザインもないんですよ。「KIKIKIKIKIKIKI」は学生時代に作ったので。二十歳ですよ。二十歳なんてポヨポヨしていて、やる気しかないみたいな感じでした。別に長く続ける気もなかったんですけど、コンペのことがあったりで、ちょっとカンパニーを続けようかなと。20代はいろいろ悩む時期でした。ー「KIKIKIKIKIKI」がスタートした経緯を教えてください。きたまり/KIKIKIKIKIKI『老花夜想(ノクターン)』(2021)photo by Yoshikazu Inoue最初の動機は私からなんですけど、大学に劇場があるから使わなきゃ!作品を作らなきゃ!みたいな動機でした。カンパニー自体は大学卒業したら、いつでもやめようっていう気持ちではいたんですけど、カンパ二ーに依頼が来たり、学生時代に作った作品がベースになってるものがコンペティションに残ったりしたので、そういう理由で続けていったという感じでした。ちゃんとカンパニーメンバーを固定でやろうとしたのが2008年か2009年ぐらいですかね。やっぱり大学卒業して2,3年は悩みながら泳いでいました(笑)。出演するダンサーは大学の同級生や後輩ではあったんですが、別にみんなダンサーになりたいわけではないので、いろいろと入れ替わったりとかしながら、2009年ぐらいにちょっと落ち着いた感じですかね。そこから3、4年は劇場と共同制作とかがあったので、カンパニーとして活動していました。ーそうだったんですね。その後、2013年から2015年の間は私がカンパニーを休んだんですよね。その後、2016年からアトリエ劇研という劇場からアソシエイトアーティストの話がはいって、また活動を始めました。ただ、そのときが一番金銭的に厳しいときでした。なぜなら、カンパニーを休んでたその時期、私は何してたかというと、自分の作品を作るんじゃなくて、「Dance Fanfare Kyoto」っていう他のアーティストが作品を作る場をディレクションしてたんですよ。でも、そういうディレクションをアーティストがやっても全く評価されないし、活動として認識されない。私自身が作品を作っていないからです。だから「Dance Fanfare Kyoto」を終えて2,3年、全く自身の創作の助成金が取れない時期がきちゃって。そのときが金銭的にしんどかったかな。アソシエイトアーティストに、劇場は広報協力と劇場使用費を安くするっていうような形で協力をしてくれたんだけど、制作予算は全部こっちで確保しなければなりませんでした。一番大変な時期でした。※「アトリエ劇研」=京都市左京区にかつて存在した、京都の小劇場を支える中心的小劇場。2017年8月31日をもって閉館。※「DanceFanfareKyoto」=作品のクリエイションを通じて、関西のダンスシーンの活性化と舞台芸術における身体の可能性の探究をめざす実験の場。「We dance 京都 2012」を契機に、発起人のきたまりを中心とした有志の実行委員会が発足、2013年7月にvol.01、2014年6月にvol.02、2015年5月にvol.03を開催。これまで、総勢100名以上のアーティストがジャンル・バックグラウンド・世代の境界を越えて参加。ー自分で制作面をすべてこなさなければならないですもんね。制作は、公演の際は外注もしました。けど、予算がないので、細々としたことはカンパニーメンバーに分担して活動してました。ただ、その状況は私もカンパニーメンバーにも負担ばっかりかけていく感じがするし、創作することが目的なのに、カンパニーを維持することが目的になる感じもして、アトリエ劇研のアソシエイトアーティストの活動を終えた後にカンパニーメンバーを全員放出して、「KIKIKIKIKIKI」をソロユニットという形にしました。ーユニットになったのはいつからですか?2018年ですね。結局、人が入ったり出たりとかはあったんですけど、15年間カンパニーという形で「KIKIKIKIKIKI」として活動しました。固定メンバーとも7年位やりました。ほぼ最初からずっとやっている人もいるわけです。ー結構長くやってたんですね。はじめは、みんな大学の同級生で、後から大学の後輩や、他で出会ったダンサーにも声かけたりもあったけど長くやってましたね。きたまりさんが考える「働く」ことの意味ーHAUSは労働と創作というテーマでインタビューを続けてきました。きたまりさんにとって、「働く」とはどういうことですか?その質問は難しいですね。10代の時、見に行ったダンス公演の後のアフタートークで、「あなたにとってダンスって何ですか?」という質問に対して、東京から来た著名な振付家が「仕事です」って答えた時にすっごいショックを受けたのよ。ーなるほど。そのことが今もどっかにあって、私は「仕事」とはよう言わんのですよ。創作してることが「仕事」ではあるんですけどね、もちろん。だけどそう言っちゃうと、何かが自分の中で崩壊するような気がして。代わりに言えることが、ちょっとまだ見つからない感じがするんです。ーわかります。例えば、私は、ダンス創作を人に教えることに気が引けるんです。なぜならば、やっぱりどこかで「教わるもんじゃねぇよ」ってことがあるんだと思います。だから、いつもワークショップなんかでファシリテーター的なことはするんですけど、「これをやって」と見本を見せることはほとんどしないんです。そうしたやり方だと、私が思っていたことと全然違うことが起きることがあります。そういう時に、ワークショップやっててよかったって思いますね。そういう時は、私が何かをしたわけじゃなく、受け手側が能動的にやってくれたっていうことだと思うんです。そんなとき、「いい仕事」したなと思うわけですよ。ー「仕事」という日本の言葉を使ったときに、既に言葉の大半を「お金を稼ぐ」という意味が占めている気がします。しかし、「仕事」という言葉の中には、「創作」や「社会的活動」という意味もあるはずなんです。HAUSでは、「仕事」という言葉の使い方自体もアップデートしていきたいという壮大な思いはあるんですけれど。私も最近までは助成金は自分で申請していたし、予算組みなども全部やっていたから、創作活動自体の現実を知りすぎて「仕事」ということに対して何の夢も持ってないわけですよ。だけど、アーティストの「仕事」が「金を稼ぐこと」だけになることは、拒否したいという気持ちはありますね。こういうのは面倒くさいなと思うんですけどね。ー創作における仁義ですかね。そうですね。仁義ですね、これ。私自身、アーティストというものに、今でも夢を持ってるのかもしれない。ー一周回って「仕事」だと言いたくなっちゃう人ももちろんいると思います。そうそう。あと、「仕事」だって言い切れる現場と、言い切れない現場もあるなと感じます。自分が組んだ企画と、他の人にオファーされた企画では少し違うなと思います。オファーされた企画は、どういうことをして欲しくて呼ばれてるかということに、答えようという気持ちが強くなります。最低限これは突破して、あとは自由にさせてもらう、みたいなこともあるし。それに対して、自分が主催する企画は、どんどん貪欲にわがままになってて。やりたいこと、作りたいものを作るぞっていう気持ちを貫き通す形になっているんですよね、実は。この間、20年ぐらい一緒にずっとやってる舞台監督に「どんどん作品作りに、観客へのホスピタリティがなくなってるね」って言われました。でも、それは若干嬉しかったんですよ。ー最高の賛辞ですね。自分が本当にやりたいことが、ここ最近ようやくできるようになってきました。ずっとやりたいことはやっているんだけど、若いときは、誘ってくれる人がみんな自分と年の離れたプロデューサーで、皆、期待をかけて誘ってくれるから、期待に答えようとしすぎた部分もあって。ーそれは、プレッシャーですね。当時はプレッシャーでしたね。でも今は、「この企画はこういう企画ですよね」って、こっちもオファーしてくれる相手のことが理解できます。最低限「私はこれはできる」みたいな範疇もわかっています。最近は地域との仕事が多いので、地域の人の中にどういうふうに入っていくかみたいなことも考えるし、そのコミュニティに、ちゃんとリスペクトを持って関わるっていうことは前提にあるとして、「そこから先の作品作りは私に任せてくれ」っていう感じなんです。ーそういう段階では「仕事」って感じもしますよね。ワークショップもそうですよね。その劇場のコンセプトや、希望されている何かがあるわけです。寄り道をする時もありますけど、そういうことをちゃんと踏まえながらワークショップをします。そういうときは「仕事」の感じがしますね。けど、「仕事」の先に「創作」がある感じはしますね。ー「仕事」と「創作」は地続きで繋がってるってことでしょうかね。やっぱり、「仕事」だけで終わっちゃうことも時々あるわけですよ。場をうまく回せなかったなっていう時は、ちょっと「仕事未遂かな?」みたいなことはありますよね。ー僕は数学教員なんです。ですから、教育現場でも同じようなことありますから、このお話に共感します。子供の発育に対して大切なことは伝えたい。でも、まずは教科書は最低限教えなきゃいけないしみたいなジレンマはあります、最低限のことを伝えたその先に、やりたいことがあるみたいなことは考えます。予想できることは「仕事」って感じなのかも知れないですね。その先にあるのが「創作」かも。ーなるほど。それはわかりやすい表現ですね。今日は貴重な話が聞けました。ありがとうございます。編集後記最近、たくさんの人たちへインタビューする機会が増えたのですが、文字起こしや編集をしながら気がついたことがあります。それは、インタビューの時の言葉(音声)と、おこした言葉(テキスト)の雰囲気には大きな差があると言うこと。きたまりさんのお話しは、音声で聞いている時はとても緩やかで優しい印象を受けましたが、テキストにしてみると、とても力強く、重みを感じます。彼女が纏う不思議な雰囲気の源は、そういうところにあるのかもしれません。複数の拠点で活動する方のお話しを聞いていたら、北海道では今後そういったアーティストが増えていくような気がしました。そんなことを考えていたら、ニューヨークと北海道を行ったり来たりしているピアニストに出会いました。次回のインタビューはこの方です。インタビューその5ジャズピアニスト 野瀬栄進さん(アップされるまで、もう少しお待ちください)今回インタビューされた人 きたまりさん17歳より舞踏家・由良部正美の元で踊り始め、2003年より自身のダンスカンパニーである「KIKIKIKIKIKI」を主宰。2006年京都造形芸術大学 映像・舞台芸術学科卒業。近年はマーラー全交響曲を振付するプロジェクトを開始し、2作目『夜の歌』で文化庁芸術祭新人賞(2016年度)を受賞。また長唄を使用し60分間ソロで見せる木ノ下歌舞伎『娘道成寺』、国指定重要無形文化財・嵯峨大念佛狂言のお囃子との共演『あたご』など、日本の伝統芸能を素材にした創作や、『We dance京都2012』『Dance Fanfare Kyoto』プログラムディレクターなど、ジャンルを越境した多岐にわたる活動を展開している。きたまりさんのアーティストツリー今回インタビューした人 渡辺たけし1971年小樽生まれ。公立中学校数学教員。劇作家、演出家。いろいろな地域の人々を取材し演劇作品などにしている。HAUSでは、アーティストの労働条件や人権について担当。今回インタビューした人 奥村圭二郎2005年〜2014年まで関わった取手アートプロジェクトでは、事務局としてアートプロジェクト全般の運営管理/展覧会・屋外パフォーマンスの企画制作/NPO法人化立ち上げ/資金調達を担当。2015年〜2017年に従事した東京藝術大学美術学部(特任研究員)では、東京都美術館と東京藝術大学の連携事業「とびらプロジェクト」のコーディネーターとして、アクセシビリティ/芸術と社会課題/ワークショップメイキング等に関する講座運営を一般から募ったアート・コミュニケータ(通称:とびラー)を対象に実施した。2018年からはフリーランスとして、東京都内で開催されている芸術文化事業のマネジメントに携わっている。
インタビュー 生活とfloatする美術家 子育てで変遷する制作スタイル インタビューその2 森本めぐみさん #インタビュー インタビューその2美術家 森本めぐみさん生活とfloatする美術家子育てで変遷する制作スタイルText : 渡辺たけし(HAUS)Photograph : 長尾さや香Place:Seesaw Books(札幌市)2022.10.2HAUSアーティストインタビューは、札幌で活動するアーティストを、たくさんの人に知ってもらいたいという思いからスタートしました。第1期は2022年夏から2023年春に取材したさまざまな分野のアーティストを順次掲載します。「・・・子どもと暮らし始めると、今度は、どうしても子育てを中心とした環境にこもりがちになってしまいます。アートのコミュニティや子育てコミュニティとか、いろいろな場所を行き来できると、もっといいのになあと思います・・・」第2回目は「育児」と「芸術」を兼業している人に取材したいと思っていました。数人の方に「育児中アーティストで気になる人を教えてください」と尋ねたところ、「森本めぐみさん」の名前が何度か出てきました。早速インタビューをお願いしました。ぼくは初対面でしたから、ちょっと緊張しながらの取材だったのですが、森本さんは一つ一つの言葉を大切にしながらお話をしてくれた印象です。まずは、森本さんの人生一大転機のお話からお聞きしました。札幌から福井県鯖江市へ変化を求めて移住ー今日は自由にしゃべってください。出身はどちらですか?出身は恵庭市です。ー何年生まれですか?1987年生まれです。今、34歳です。ーお住まいは札幌市南区ですね。そうです。子ども2人と夫、夫の両親、犬と猫で夫の実家に住んでいます。ーお子さんはおいくつですか?2歳と6歳です。ー来年から小学校ですね。お迎えなど大変ですね?そうですね。でも、私が自宅や保育園から少し遠い場所でフルタイムの会社員をやっていて、帰りが遅くなるので、基本的に夫が子どもたちのお迎えに行ってくれています。その後、夫が創作現場に行く感じです。ー森本さんの配偶者もアーティストですか?夫は「キトカイ」という名前で木工をやっています。今、札幌芸術の森工芸館で展示会をやっています(2022.10.2現在)。道内の工芸作家のグループ展をしています。※札幌芸術の森工芸館=工芸にまつわる展覧会が開催される札幌市の展示ホールーこのアーティストインタビューでは、今までどのように生活や作品づくりをしてきたかなどのお話ししていただいています。はい。中学校の時の美術の先生のすすめで札幌市立高等専門学校(現・札幌市立大学)というデザイン系の高専に進学しました。その時から、恵庭の家から札幌に通い続ける生活が始まりました。2011年に卒業した後、3年間ぐらいは札幌の会社に就職して働いていました。ー学校を卒業した後は、アーティストを専門の職業にしていこうと考えていたんですか?あわよくばという気持ちはありました(笑)。それで大学を卒業してすぐは、コールセンターで働いたんです。コールセンター勤務だと持ち帰り仕事がないし、勤務時間がはっきり決まってましたから、仕事の後の時間は美術作品の制作などをしていました。札幌市内だけじゃなく、自分で企画して東京で展示したりといろいろやったんです。でも、それで生計が成り立つ見込みもなかったし、美術館に呼ばれて展示することもありませんでした。「このままこんな感じの生活を続けてくのかな?」と悩んだりもしました。周りにいる美術の仕事を専業してる人の話を聞いても、美術は面白いけど、美術で生計を立てるのは当たり前ながら面白くないこともいろいろあるんだなぁ、と思ったりもして・・・ーその後、福井県に移住したそうですね。きっかけは?札幌で作品作りをしていても、周りの環境があまり変わらなかったことが理由の一つにあります。美術の作品をつくるには、技術に関することだけではなく、いろいろ経験することが必要じゃないかなと思うようになり、それで、ぽっと、福井県に何も考えないで行っちゃったんです。2013年から2018年までの間です。ーなぜ、福井県を選んだんですか?当時から付き合っていた夫が、福井県鯖江市で木工をやっていたからです。鯖江市には漆器の産地があり、夫はそこで住み込みの仕事をしてたんです。それで、時々遊びに行き、面白そうな町だなぁと思っていました。北海道から電車に乗って福井へ行き、帰りに美術館をみたり、ホタルなんか見せられたりして「あ、いいところだな」と(笑)。うちの父方の先祖が富山県にいたみたいなんです。自分でも気になっていて、昔にその辺を電車で回ってみたことはあって、北陸にはなんとなく縁を感じていました。ー福井に移住してみて、生活はどんな風に変わりましたか?移住して何週間かは消極的に求職活動をしながら家の修繕などしていたのですが、近所の人が「お弁当屋さんが仕事探してるよ」とか色々声をかけてくるようになったので「とりあえず仕事しなきゃいけないのかな」と思って、メガネ修理専門の会社に入社しました。鯖江市はメガネの町なので、メガネに関する仕事が細分化されていたんです。メガネ修理もしていましたが、私はちょっとパソコンが使えたので、事務仕事とかエクセルでお店のチラシ作ったりとか、そういうことをしていました。ー福井に住んでいる間も作品づくりはしていたんですか?福井では、全然作っていなかったですね。途中まで作っていたものや、自分の作品じゃなく関わっていた団体や町のイベントのために作っていたものは、いっぱいあったんですけれど。福井に住んでいる時は、メガネ屋で働いてお給料を稼ぐことと、「まちづくり」の活動で手一杯みたいな感じになっていました。それはそれで、楽しかったんですけど。そうしている間に5年ぐらい経っちゃったんです。ーお子さんも生まれて、子育てが始まったら、いよいよ作品の制作が難しくなったんじゃないですか?でも、子どもが生まれてから、ようやく「なんか作り始めなきゃ」と思うようになりました。子どもが生まれる前までは、自分の都合で使える時間が無限にあったんですけれどね。子どもが小さい時にしか作れないものがあるんじゃないかと考えるようになりました。子どもができてから、急に時間が方向性を持って動き始めたような気がします。それまでは、方向性のない時間がずっと続いていました。そんな生活の中に、いきなり成長し続ける子どもが入ってくると「このタイミングで何かしなくちゃいけない」という気持ちになりました。1人目の子どもが生まれた2016年に、またちょっと絵を描き始めました。お正月で札幌に里帰りしたタイミングで作品の展示をしました。ーどんな内容の展示ですか。札幌では、小さい絵を展示しました。自分の部屋にあるベットの横に小さいちゃぶ台を置いて、子ども寝た後に描いていました。ーその小さな絵の写真データなどを拝見することはできますか?それが・・・最近、ハードディスクを子どもにぶん投げられて、消失してしまいました(笑)。ーあらら(笑)。「諦めろ」ってことかなと一瞬思ったりしました(笑)。今住んでいる家でもそうですが、子どもが生まれてからは、「自分専用の制作場所」と呼べる場所を持ったり、そこに行くのも難しく、福井でも子供と一緒に寝る部屋で作品制作をやっていました。気を抜いて、データを保存したハードディスクを見える場所に置いておいたら、二段ベットの上から「えいっ」て投げられちゃいました。ー僕も、むかし子どもたちにいろいろやられました。子どもは、ああいうことって楽しいんでしょうね。ーその後、福井でのどのように生活していたんですか?柿を収穫したり、バーベキューをしたりして、近所の人と猪を捕まえて、解体したりしました(笑)。ー猪の解体!?普通に田舎を楽しんでました。地元の人とも仲良くなりました。でも経済的にも時間的にも余裕がなく、かなり疲弊してもいました。子が生まれて、北海道の親に子どもの顔を見せにいくのもお金がかかります。そんな時に、福井にどかっと雪が降ったんですよね。30年に一度くらいの大雪でした。地元の人たちは子どもの時にこんなのが一回あっただけと言っていました。ー雪は大きなポイントだったんですね。屋根まで積もる雪が降りました。古い家に住んでたんですが、屋根の軒がポキッと折れちゃったんですよね。「修理しないでここに長く住み続けるのは無理だなぁ」って話になりました。腹くくって修理して住み続けるか、北海道に帰るか、どっちかみたいな二択を迫られたんです。結果的に、もうダメだってなって。2018年に、仕事を見つけて北海道に帰ってきました。恵庭市に戻りました。北海道にUターン子育てしながら再び作品制作北海道に戻ってきた2018年から現在まで、札幌市のグラフィック・デザインの会社で昼間は働くようになりました。もうすぐ5年ぐらいになります。それから、北海道に帰って恵庭に住んで1ヶ月後に、いきなり北海道胆振東部地震がきたんです。※北海道胆振東部地震=2018年9月6日に北海道胆振地方中東部を震央として発生した地震。地震の規模はMj6.7。地震の影響で道内全域約295万戸でブラックアウト(停電)が発生した。ー地震の時はどうしていました?私の方は電車で会社に通っていたので、休んでいたんです。でも、夫は当時、内装仕事をしていて、地震の2日後ぐらいから「納期もあるから行かなくちゃいけない」って言って、会社に行ってしまいました。私1人と子どもだけで家にいました。ーやっと電気が復旧した時期ですね。そうです。その地震の後、木工の仕事で独立したかったという話も出て、夫は会社をやめました。「今住んでいる家に家賃払うの無理だね」って話になって、南区の夫の実家に引っ越すことになり、私は夫の実家から仕事に通うようになりました。ー福井から北海道に戻ってすぐ地震で引越し。さらに人生の分岐点がきた感じですね。たまたまそんな感じになりました(笑)。子どもの保育所もずっと待機で、ようやく入れた矢先だったんですが、また、引っ越すことになりました。ー作品の話を聞かせてください。福井の家の庭の柿の木の写真を使った「2013年、庭の柿の木」(2018年)という作品を拝見しました。札幌に戻った2018年に制作しました。(「2013年、庭の柿の木」 撮影:山口誠治)ー制作の経緯を教えてください。北海道胆振東部地震の直後に「Nameless landscape」というグループ展にお誘いいただいて、その展示の一部として制作しました。写真の上に蓄光糸で刺繍のドローイングがしてあります。部屋全体が数分おきに明点と暗転を繰り返していて、それぞれで違うイメージが見えるようになっています。雪害と地震で相次いで引っ越しする中で、何か自分の制作環境や作品に対する意識が変わったように思ったのですが、どう変わったのかわからなかったので、あの作品を作った感じです。ー作ったあとに「なぜ作りたかったのか?」気がついたりするんですか?作っても、よくわからなかったんですよね(笑)。ー(笑)なにかあると思ったんです。福井の家の柿の木が気になっていたんでしょうね。毎年食べきれないぐらい柿がなるんです。枝がしなってしまうくらい。前に住んでた人が植えていたんです。そうすると、柿がいっぱいあるから、山から猿が降りてくるんですよ。ーさるかに合戦!?そうですね(笑)。北海道には柿がないので、最初は福井のその景色に異国情緒を感じました。曇ってる空に真っ赤な柿の実がなっている風景が、すごく印象に残っていました。福井を後にする時、その柿の木もそのまま置いてきちゃったので、ずーっと気になっていたんでしょうね。北海道に戻った途端に地震がきて、古いアパートだったので、壁がワシワシと割れちゃって、それが柿の木の枝みたいに見えたんです。福井の柿の木の写真の上に、北海道のアパートの壁のひび割れを、蓄光素材の糸で刺繍しています。ーこの作品に蓄光素材を使ったのはなぜですか?子どもが寝てから、布団の中でできるものということで蓄光素材を選びました。それから、最初に福井の家を借りたとき、前に住んでいた人が残していった電灯のスイッチ紐の先に蓄光の星がぷらーんとぶら下がってたんです。ー蓄光のスイッチコード、子どもの頃よく見かけました。(福井の家に実際あったスイッチコード 本人撮影)私たちが住み始める前の誰もいない間も、昼はここで光を溜め、夜は光り続けていたんだなと考え、誰もいない場所で、そういう風に光っている蓄光の星が、いろんな場所にあるんだろうなって思いました。今の家にも、子ども用に蓄光の星を壁に貼っていますけれど。ーアイデアは、子育てなどの生活から出てくることが多いんですか?仕事や子育てをしながらできる作品を作っています。「ゴルディロックスを待ちながら」(2019)という作品の土台は、布に糸と針で刺繍したものなんですが、終わったら畳んですぐにしまうことができます。素材の布は、引越で着ている服を処分しなければいけなくなって、それを切ったり、縫ったりして作りました。ユニクロのシャツなどです(笑)。子どもと生活することで、良くも悪くも思ってなかったところに連れて行かれることはありますね。(「ゴルディロックスを待ちながら」 撮影:山口誠治)ー北海道に戻ったその後は、どんな作品を作っていますか?恵庭に住んでいた時は、かろうじて自分の部屋があったんですが、今の家に引っ越してからは作品制作ができる自分の部屋もないので、庭でできるような作品を作ろうと思いました。ー庭で作れる作品というのはどういうものですか?はい。土偶などの作品を作り始めました。ー土偶?!はい。意外と大変でしたけど(笑)。ーたしかに、庭で焼けますね(笑)。計画していないタイミングで自分の住居を移すことが続いたので、どこに自分の作品を保存しようかと困りました。捨てられない。だんだん自分の作品を持って移動するのが、しんどくなってきちゃいました。引越しのたびに、作品の保管をどうしようと悩みました。持ち運ばなくていいので「短歌」を作ってみたりとか、場所を取らない作品づくりを探していました(笑)。ー作品の形態が変遷してきたのは、お子さんがいることや、引越しなどの環境の変化が関わっているということですね。そうですね。まさか、自分が土偶を焼くようになるとは思いませんでした。土偶だったら保存に困ったら、土に埋めればいいよなと(笑)。生活スタイルにあった作品作り土偶づくりにハマるーその後、どんな展示に関わりましたか?その後は「塔を下から組む~北海道百年記念塔に関するドローイング展」(2018年)という展示に関わりました。ーどんな内容の展示ですか?新札幌の「北海道百年記念塔」の解体方針が固まってきた頃に、佐藤拓実くんというアーティストが解体されるにしてもそこに塔があった事実はきちんと残すべきだという思いで始めたプロジェクトです。必ずしも佐藤くんのその方針に同調するメンバーだけではないのですが、そのテーマに関連してドローイングを作ってくれそうなアーティストに声がかかり、私もその一人として声がかかりました。※佐藤拓実=北海道を中心に全国で活動する美術家。近年は北海道の歴史に取材した平面作品を制作、展開している。(「北海道一万年記念塔」 撮影:メタ佐藤)ー百年記念塔ではなく、一万年記念塔なんですね。オリジナルの「北海道百年記念塔」は開基百年で100mの高さの塔なんですけれど、開基一万年で10000mの高さの「北海道一万年記念塔」という架空の塔が完成して、それを100031歳の私が家族と見に行く、というストーリーでドローイングを描きました。ちなみに、この時暫定的に考えた「北海道一万年記念塔」は「北海道百年記念塔」が100個縦につながった形をしています。ー何人のアーティストが参加したんですか?最初は8人だったと思います。今日持ってきたこれは「一万年記念塔」の土印です。2回目の展示「北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(2020年)を小樽文学館でやった時に、博物館風の展示ケースの中に「押したらこうなります」というので、土偶に使ったのと同じ江別の粘土に押した印影も並べて展示しました。そして、この押されたものを焼くと、さらに土偶になります。ー終わらない感じですね。そうです(笑)。埋めたものを将来的に誰かが見つけて「なんだろう?」と興味を持ってくれるかもしれません。誰かが一万年後に見るわけです。現在は、プラスチックを食べる微生物なんかが見つかっています。風化に強い素材はなんだろうと考えた結果、土偶になりました。ーアーカイブで見せてもらったいくつか作品には「物がなくなっていく」とか「終わりがある」という意味の一貫性があるような気がしました。一貫性があるといってもらえて良かったです。自分ではそんな気はないんだけど、「森本はいつも全然違うことばっかりやってる」って言われることが多いんです。私は、いつも、「ギリギリ残っているもの」を作品にしてきたような気がします。「いつか終わりがある」という前提に影響されて作品作りをしていると思います。ーこれから、やってみたいことはありますか?近々、駄菓子屋さんをやってみたいと思っています。夫が使っているアトリエの庭を占拠して、最初はテントでやろうかなと思っています。名前も決めてあるんです。「ふろうと商会」か「ふろうと企画」にしようと思っています。ー「ふろーと」=float(浮く)ですね。ちょっと、浮いてる感じ?はい、(floatの意味は)なじみきらないというか・・・(笑)。テント営業とか屋台みたいな、移動しやすくて、あまりお金がかからない方法でやろうかなと思っています。昔から、そういう人が集まれる中間的な場所を作りたいなと頭の片隅で思っていました。ー実は僕の実家が、子どもの頃、駄菓子屋をやっていたんです。(しばし、駄菓子屋談義で盛り上がる)それから、もう少し土偶を焼きたいです。作ってばら撒かないと、あまり意味がないかなと思いますから。自分で持っていると保管しなければならない状態から逃げられないし。誰かにどんどんあげたり、埋めたりしていこうかなと思っています。このおたまじゃくしも、もらってもらえないかな。いらなければ、畑の隅などに埋めてもらいたいです。ー僕、何匹かもらっていきます。コロナ禍が落ち着いたら、みんなで土偶を焼いて埋めるという企画もやりたいです。この土偶の上にアクリル絵具のような朽ちるスピードが違う素材を塗ってみるのも面白いかなって思っています。ギリギリ残ってるものをみんなで見るみたいな感覚に、土偶はすごく合致してる気がします。家族でバーベキューしながら、焼き台で土偶を焼くこともできますもんね。ーそれも楽しそうですね。生活と作品を作るってことが結びつくんですね。結びつかないことって無理だと思うんですよね。ーHAUSでは、専業アーティストだけではなく、兼業アーティストの皆さんの話も取り上げていこうと思っています。そういう意味で、子育てをしながら作品を作っている森本さんの話は興味深く聞くことができました。アーティストに限らず、家庭と学校だけみたいな、限られたコミュニティーで子どもを育てているとしんどいじゃないですか。だからみんなで集まるコミュニティみたいなものがあってもいいのかなと思います。ーアートが発端のコミュニティが作られてもいいのかもしれませんね。昔は、アートをやっている人だけの集まりから、一旦距離を取りたいと思ったこともあったんです。「同質性の人たちの中ばかりにいちゃだめじゃないか」と思って離れたんです。その反面、アーティストの友達と話したり、誰かが制作している気配に触れたり、誰かの展示を見に行ったりすると、ちょっとホッとする自分がいました。ーはい。子どもと暮らし始めると、今度は、どうしても子育てを中心とした環境にこもりがちになってしまいます。子育てのコミュニティーは自分にとっては新しい出会いだったんですけど。アートのコミュニティや子育てコミュニティとか、いろいろな場所を行き来できると、もっといいのになあと思います。ーいろんな集まりに出入りできるということは、子育てなどをしている人たちの利点かもしれませんね。そうですね。個人的には、アートだけをやってる生活よりは良かったなと思っています。来年の夏で結婚して10年目くらいなので、これを節目に駄菓子屋も実現させたいと思っています。ー今日は、楽しい話をありがとうございました。森本さんのちょっと不思議な雰囲気が楽しくて、余計なお話まで尋ねてしまった今回のインタビューでした。子育ては楽しいことばかりではないわけで、他の人には伝えられない悩みを抱えることもありますよね。アートがあることで、自分自身が支えられるってことも、とてもたくさんあると思います。ところで。インタビューその1、その2と「兼業アーティスト」にお話しを聞いてきました。じつは、HAUSの中でも「北海道の芸術家を知ってもらうなら、兼業とか専業とかにこだわらなくてもいいんじゃない?」という意見もありました。「たしかにとそうかも」と思い直し、次回はド直球で専業アーティストの方からお話が聞いてみたくなりました。ということで、次回はこの方です。インタビューその3専業演出家 鈴木喜三夫さん今回インタビューされた人 森本めぐみ1987年 恵庭市生まれ。美術家。寓話世界のイメージを絵画やパッチワークなどで表現する作品を制作。「塔を下から組む~北海道百年記念塔に関するドローイング展」(ギャラリー門馬 2018年)、「Nameless Landscape」(札幌文化交流センター 2019年)、北海道百年記念塔展 井口健と『塔を下から組む』」(小樽文学館 2020年)などに参加。今回インタビューした人 渡辺たけし1971年小樽生まれ。公立中学校数学教員。劇作家、演出家。いろいろな地域の人々を取材し演劇作品などにしている。HAUSでは、アーティストの労働条件や人権について担当。
ニュース N.MIKAさんとフリーマーケットに挑戦HAUSの活動資金に向けて!! #ニュース HAUSの活動資金に向けて!!N.MIKAさんとフリーマーケットに挑戦2023.6.14text 戸島由浦(HAUS)HAUSの活動資金に向けて!!HAUSは画家のN.MIKAさんと共に、6月27日(火)、フリーマーケットを開きます。ことの発端は5月24日のACFフォーラム「札幌の芸術創造活動の支援のあり方を考える集い Vol.2」での会話。登壇していたHAUSは、昨年度は札幌市の助成金のお陰でサバイバルアワードとアーティストツリーを動かすことができたことを話しました。そして今年も引き続き活動したいけれども資金がないということも。山菜でも取ってきて売ろうかな、なんて、思っていました。そこでアイデアを出してくれたのが、サバイバルアワードに参加して下さっていたN.MIKAさん。会場に来てずっと登壇メンバーの肖像を描いていましたが、終わってから、「HAUSの資金集め、私の作品を売って手伝いたいです、、どうでしょうかね?!」と話してくれたのです。さて、どこで、どんなふうに開こうか。他に誰に関わってもらおうかな。考えながら周りの方々に相談していくと、Seesaw Booksの神さんが、「炊き出しの後にする?」。ありがたい。願ったり叶ったりです。さて、そうして行うフリマは、題して、北海道のアーティストのよろず相談窓口HAUSの活動資金に向けて!!~フリーマーケット編~N.MIKAさんから参加者への案内N.MIKAさんからアーティスト達への参加呼びかけ会場には、中心となってやって下さるN.MIKAさんの作品やポストカード、バッヂに似顔絵ブース。そして他に参加して下さる方々の作品から余り物までいろいろ。HAUSメンバーも、スズメバチのウォッカ漬け(かゆみによく効きます!)や珈琲など、持っていきます。カレーのふるまいもあるかも?!(なくなり次第終了しますのでお早めに☆)当日はアーティストからの相談も受け付けています。平日の午後ですが、夜まで開いていますので、ぜひふらっとお立ち寄りください。<開催概要>北海道のアーティストのよろず相談窓口HAUSの活動資金に向けて~フリーマーケット編~日時:6月27日(火)15:00頃~(”大きな食卓”のあと)場所:Seesaw Books内容:アーティストの作品や私物の本やスズメバチのかゆみ止め、似顔絵ブース、コーヒーなど。※数量限定でカレーのふるまいもあります。そういえば、6月27日はちらし寿司の日らしいですね。ちらし寿司は、質素倹約で「一汁一菜」を命じられた江戸時代の庶民が、魚や野菜をご飯に混ぜ込んで「一菜」だと言い張って生まれたとか。工夫とユーモア!N.MIKA絵を描くのが好きで、洋服も大好きなおばさんです! 🎨 絵画に関するお問い合わせ、購入に関するお問い合わせは、メールから、どうぞm-artmuseum.comInstagram:n.mika6621アーティストツリーページはこちら!
ハウスサバイバルアワード 憲法記念日。民主主義ってなんだ?民主主義ってこれだ!への追憶ポケット企画と伴走リポート#3 #ハウスサバイバルアワード ポケット企画と伴走リポート#3憲法記念日。民主主義ってなんだ?民主主義ってこれだ!への追憶2023.5.3text 羊屋白玉、箱崎慈華、戸島由浦U-29でつながろうぜ!続編ゴールデンウィークの5月3日(水)、西区にあるレッドベリースタジオにて、札幌演劇U29 若手のための意見交流会が開催されました。ポケット企画と伴走リポート#2で取り上げた「ここらで交流会しませんか?ーU-29でつながろうぜ!ー」の続編的イベントです。ファシリテーターは三瓶竜大さん(ポケット企画/劇団清水企画)。この会は、彼と佐久間泉真さん(弦巻楽団)の協力により実現しました。始まりは11時。事前に参加を表明していた10数名を超えて、16名の演劇人たちが集まりました。誰も嫌な気持ちにならないための、会の趣旨やルールについての説明をしたあと、全員の簡単な自己紹介。U29と言っても、高校生、大学生から、社会人まで、年代も活動団体も多様です。「〇〇って呼んでください。」「〇〇〜!(皆の声)」という風にして知り合っていきました。話題に挙がった、3つの悩みごとテーマゲームを交えて緊張をほぐしながら、まず最初に取り組んだのは、演者や技術者、演出家や製作者それぞれにとっての、悩みごとの共有。カラフルな付箋に書き、壁の模造紙にペタペタと貼っていきます。この手法は、いわゆる、壁討論と呼ばれるもの。一通り付箋を貼った後、皆で気になるテーマを選んで話を深めました。特に話したテーマには、以下の内容がありました。「良い役者になるには。そもそも良い役者ってなんだろう。」「ハラスメントについて。防ぐ方法、身を守る方法、もし起こってしまった時には。」「お金について(企画の金銭工面と、生活の金銭工面、それぞれについて。)」4-5人ずつのグループで各テーマについて意見や情報の交換をしたあと、話した内容を全体で共有しました。お昼からの追加テーマそうこうしているうちにあっという間に13時。さすがにお腹が減り、1時間の休憩をすることにしました。ランチを買ってきて会場の玄関前で話しながら食べている様子はまさに「交流会」ならではです。休み時間の間も、壁に貼られた悩みごとについて、解決策を書いたり、改めて見て考えたりする様子がありました。再開後、いつの間にか参加者は30名を超える数に。午前中に引き続いて話すうちに、「企画をしてみたい」「(学生で)今後の進路に悩んでいる」という2つの新たな議題が出てきて、それぞれ興味のある人たちで、また集まって話しました。参加者の事例を集めているうちに、「3人いれば演劇は始められるのではないか」「札幌市内の劇場関係者の交代期にあるため、若手の意見を入れていくチャンスがあるのではないか。」というヒントが出てきました。企画した三瓶さんには初めから、札幌市内の劇場について考えるような意図もあったようです。そんなこんなで、14時からのはずだったフォーラムシアターは、18時くらいからやることに。進行をあせらず、その場の皆の熱量に沿ってじっくり話す時間を設けて下さったためか、途中で離脱することなく1日集中する人が多くいました。「困っている人は誰ですか?」皆で解決策を考えるフォーラムシアター18時からの「フォーラムシアター」では、まず参加者が4つのグループにわかれ、創作現場で自身が経験した「困った出来事」を共有しました。ここで話し合われた実際の出来事を短い劇に落とし込み、上演を行います。今回上演した3グループはそれぞれ、「舞台の集中稽古」「稽古前の発声練習」「ワークショップ、休憩中の過ごし方」といった出来事を元にしており、演劇に関わる方々の誰しもが経験するシチュエーションが取り上げられていました。参加者全員で観劇し、その後「誰が困っていたのか」「問題点は何か」を話し合うのですが、わからないことを出演者へインタビューしていくうち、最初は「演出家のせいで俳優が困っている」という見え方だったことが、「この場にいる全員がそれぞれに困っているのでは」という意見も出てきます。例えば舞台の集中稽古の出来事を上演したグループは、俳優が演出家の漠然とした要求に困るという内容ですが、「具体的な指摘がなく違うパターンを要求される俳優」「うまく言語化できないが時間がなく焦る演出家」「集中稽古が長引くなか待機している別の俳優」皆がそれぞれ嫌な雰囲気を感じ困っている、という状況です。誰が困っているのかを皆で話し合ったのち、同じ劇を改めて上演します。参加者は今度はただ観劇するのでなく、途中で自由に劇を止めることができ、そこで出演者と交代して困りごとを解決に導くような演技をします。俳優と交代して一旦持ち帰っての検討を提案する人や、演出家と交代して伝え方を変える人、様々な解決策が提案されました。それぞれ実際に起こった出来事はその場ではモヤモヤが残る結果となっていたわけですが、今回のフォーラムシアターによって、起こった出来事を様々な角度から捉え直す機会となったようです。それぞれの役割を演じ合うことで、立場による感じ方の違いが改めて理解できたり、誰かが行動を起こすことで状況が変わる可能性があることを再確認していました。どの立場でも、良い創作環境を目指したいという思いは同じです。普段から演劇の創作に身を置かれている参加者の方々には、コミュニケーションのあり方に対して、非常に実践的な取り組みであると感じました。ちなみに同日、苗穂では美術分野の交流会が。実はこの日、苗穂にある0地点という共同アトリエでは、美術系の学生世代を中心とした交流会が開かれていました。同じ日に札幌市で、違う分野ではありますが、若手交流の会が開催されたことに、奇妙な縁を感じます。0地点の方は、18時ごろから始まり、食べ物を片手に自然発生的な交流が見られました。感染症騒ぎも収束しつつある今、改めてつながろうという意識が強まっているように感じます。0地点の交流会HAUSが関係を持っているアーティストには、今回の参加者内外に、29歳以下の方が何人かいらっしゃいます。これから活動を開拓していくだろうU29に注目です。「フォーラムシアター」とは? ポケット企画の三瓶竜大さんによる解説1960〜70年代のアヴァンギャルドな時代が終わって、80年代、90年代になった頃。それまでの反体制的な主張から演劇の手法を社会のために使う応用演劇が作られ始めました。その基礎を作ったのは、ブラジルのアウグスト・ボアールという演出家です。 ボアール自身も60〜70年は、「武器を取れ!という主張を劇を通して叫ぶような、反体制的な作品を作ってきましたが、ある農民との会話から、劇団と民衆が一緒に武器を取って戦うわけではない」と、気付かされました。 そこから貧富の差や貧困層にいる人々の搾取に問題意識を覚え、社会状況を変えるために聴衆を巻き込むような演劇手法を考案しました。搾取されている状況を演劇を通して自覚することで国民の問題意識を高め、社会を変革しようとすることが目的です。今回、意見交換会で取り組むフォーラムシアターは、創作活動の中で経験した解決できないような困難な状況を詳細に思い出し、寸劇として再現してみます。そして、客観的に観たり、主観的に演じることで、みんなで解決策を考えてみましょう。参考書籍 「被抑圧者の演劇」アウグスト・ボアール 晶文社(里見実、佐伯隆幸、三橋修 訳)<開催概要>札幌演劇U29 若手のための意見交流会日時:2023年5月3日(水·祝) 11:00~21:00会場:レッドベリースタジオ料金:U29カンパ 30歳以上(19時以降入場可)1000円ポケット企画2021年まで三瓶竜大(劇団清水企画)のソロユニットでしたが、団体化が決まり、現在までに三瓶竜大・佐藤智子・吉田侑樹・藤川駿佑・さいとうあすか・泰地輝・森大輝の7人が所属しています。 毎週木曜日の定期稽古のほか、戯曲を読む会、事前批評会、ダンスレッスンなどをメンバー全員で企画、運営。他団体の俳優との勉強会や月に一度の観劇会なども精力的に行っています。“今”しかできない表現を大切に、文化全体の反映を願いながら日々創作活動に励んでいます。https://pocket-kikaku.com/https://pocket-kikaku.stage.corich.jp/U29企画「ポケット企画」のtwItter0地点苗穂にある、築96年の古民家を再活用した、共同スタジオ&ギャラリースペース。twitter @0_chiten_Instagram @0chiten《編集後記》2023年憲法記念の日。「札幌の若手のための意見交換会」樹立しました。なぜだかこの会の途中から、SEALD’sのことを思い出していました。確か、SEALD’sの結成も憲法記念日だったな、と。2015年、夏の参院選に向けて、安倍政権の憲法観への危機感が発端となり、「民主主義ってなんだ?民主主義ってこれだ!」のシュプレヒコールに包まれた国会前デモが繰り広げられているのを見ていました。そして、時も場所も変わってレッドベリースタジオでは、集団創作の現場での行き詰まりの瞬間を捉えたシーンが組み立てられているのを間近で見ていました。彼らは、それを、フォーラムシアターと称し、交わされた困りごとが、その声が、フォーラムシアターのテーマとなり、困りごとが起こす行き詰まりを解決する協働を経て、身体へと地肉化され、それは、ハードコア(ど真ん中)で民主主義な演劇への生成でした。かつてハウスも、現場で起きたハラスメントの聞き取りから台本へと落とし込み、リーディングをし、上演のための創作環境の改善に向けて、もしくは「気づき」のような体験の共有を目指したことがありました。「札幌の若手のための意見交換会」は、これからも続いてほしいと思います。でも、あれこれと余計なことをしないように、と、心に留めました。SEALD’sや、この会だけではなく、若い世代の活動に群がる理解あるっぽい大人たちによる擁護とバッシングはもう見たくないし、したくない。と、動揺しながらの帰り道でした。まずは、この場を借りまして、このレポートに協力してくれたU29アーティストのみなさんにお礼を申し上げます。そして、お疲れ様でした。ハウスは、相変わらずかたわらに座っていようと思います。よろしくです。(羊屋白玉)SEALD’s シールズ 自由と民主主義のための学生緊急行動https://www.sealds.com/書いた人の名前も載せてない朝日新聞の記事「隠したい」元SEALDsの過去 若者の声を封じるものは
ハウスサバイバルアワード 演劇とアクションの教室『One_classアクション×演技』プレ開講田中春彦さん(わんわんズ)伴走レポート#1 #ハウスサバイバルアワード 田中春彦さん(わんわんズ)の伴走レポート#1「カッコよく、安全に」わんわんズの『わんクラ』プレ開講へ2022.12.26text 箱崎慈華(HAUS)未経験者歓迎!演劇とアクションの教室ハウス・サバイバル・アワードにご参加いただいた、役者の田中春彦さんが所属する演劇ユニット「わんわんズ」の『One_classアクション×演技』(通称:わんクラ)に参加してまいりました!わんわんズさんは2023年1月から「アクション」「バク転」「演技」「親子向けアクション」の教室を開講する予定です。まずプレ開講として「アクション」「演技」の教室を行うということで、HAUSはプレ講座の運営費の一部を助成しています。演技の回とアクションの回それぞれの第1回教室の参加レポートです。わんクラ「演技」プレ開講 第1回「演技」教室の第1回は田中さんが講師です。参加者は演技経験のある方から、ワークショップに初めて参加する方までさまざま。田中さんはまず参加者全員に円になって隣の人と手を繋ぐよう促します。コロナ禍に関わらず、なかなか初対面の方と直に触れ合う機会はないものです。田中さんが全員の目を瞑らせ、一人の人に隣の人の手をギュッと握るように伝えます。握られた人はその感覚を受けて、今度は別隣の人の手を握るようにします。手の感覚だけを頼りに、握手を渡していくようなやりとりです。ここで田中さんが参加者に教えていたのは、相手の動きをよく感じることと、相手に自分の動きをはっきり伝えること。最初に非言語的なコミュニケーションをしたことによってか、参加者同士で打ち解け合うのが早かったです。その後は参加者全員で与えられたお題を体を使って表現しました。「飛行機」というお題を参加者全員で相談して体で表現します。人によって違うイメージを話し合いで整理していき、いろいろ悩みながらも「機首」を表現することに。写真提供:わんわんズわんクラ「アクション」プレ開講 第1回続いて、わんクラ「アクション」教室の第1回にも参加してまいりました。ここではわんわんズにご所属されている由村鯨太さんが講師です。まずは入念な首のストレッチから入ります。アクション演技では、攻撃をする側と攻撃を受ける側がいますが、例えば殴られたような動きをする時には普段よりも激しく首を動かすので、初心者は特に痛めやすいのだそうです。わんクラでは「カッコよく、安全にアクション」というテーマを大事にされており、ケガをせず安全にアクション演技をする時のポイントを詳しく教えてくださいました。舞台や映像のアクションでは、打撃が当たらないように距離を広くとります。このとき、観客から見てパンチの軌道と殴られる動作が重なると、とてもリアルなアクションに見えるそうです。参加者がグループに分かれて、自分たちで考えた短いアクションを見せ合い、感想を交換することも楽しかったです。蹴られるアクション演技中のHAUS箱崎写真提供:わんわんズ田中春彦(わんわんズ)2008年、大学在籍時に、演劇活動を開始。以降、俳優として舞台を中心として、CM、ドラマへの出演や、ナレーターとしても活動。2013年、演劇ユニットわんわんズを立ち上げ。「アクションと演劇の融合」を目指して作品作りを行う中で、オリジナルのヒーローショー「もじゃキング」を生み出す。劇場での公演にとどまらず、地域のお祭りや小学校、幼稚園・保育園を回っての上演を通して、演劇に触れたことのない人々に、演劇の魅力を伝える活動を広げている。その他、芸能プロダクションや専門学校などで、演技やアクションの講師としても活動している。◆ わんわんズ WEB情報 ◆わんわんズ公式WEBサイト@WanWanzOne · TwitterYouTubeチャンネルFacebookページ
ニュース ポケット企画が「若手のための意見交流会」を開催 #ニュース 三瓶竜大さんと伴走「若手のための意見交流会」をポケット企画が開催2023.4.27text 渡辺たけし(HAUS)2022年ハウスサバイバルアワードに応募いただいた三瓶竜大さんが、札幌で「若手のための意見交換会」を開催するそうです。今回の企画は、30歳未満の舞台関係者に呼びかけ、日頃考えていることや、疑問に思うことなどを話し合うという、ありそうでなかった集まりです。今回は、フォーラムシアターの形で、自分が経験してきたことや考えてきたことなどを、参加者皆で共有しようという試みも行われます。興味のある方は是非、参加してください。日時2023年5月3日(祝・水)11時〜21時(入退場自由)※タイムテーブルや内容は画像を確認してください場所レッドベリースタジオ(北海道札幌市西区八軒2条西1丁目1−26)そのほか※U29はカンパ制 30歳以上の方は1000円※事前申込不要※来場に関する拡散にご協力ください。(〜時に行く!等)※30歳以上の方も19時から来場可。※対象は舞台関係者ポケット企画2021年まで三瓶竜大(劇団清水企画)のソロユニットでしたが、団体化が決まり、現在までに三瓶竜大・佐藤智子・吉田侑樹・藤川駿佑・さいとうあすか・泰地輝・森大輝の7人が所属しています。 毎週木曜日の定期稽古のほか、戯曲を読む会、事前批評会、ダンスレッスンなどをメンバー全員で企画、運営。他団体の俳優との勉強会や月に一度の観劇会なども精力的に行っています。“今”しかできない表現を大切に、文化全体の反映を願いながら日々創作活動に励んでいます。
ハウスサバイバルアワード 若手舞台人が語る悩み 「U-29でつながろうぜ!」報告ポケット企画と伴走リポート#2 #ハウスサバイバルアワード ポケット企画と伴走リポート#2若手舞台人が語る悩み「U-29でつながろうぜ!」を見学しました2023.4.10text 渡辺たけし(HAUS)若手舞台人が企画した、あるようでなかったイベント「ここらで交流会しませんか?ーU-29でつながろうぜ!ー」というイベントが、2023年4月8日(土)あけぼのアート&コミュニティセンターで行われました。この交流会は、ポケット企画(札幌市)三瓶竜大さんと弦巻楽団(札幌市)佐久間泉真さんが企画したものです。29歳以下の舞台関係者を集めて、自分たちが普段考えていることや困っていることなどを、ザックバランに話してみようというディスカッションのイベントです。ハウスサバイバルアワードで三瓶さんがプレゼンした企画ということもあり、HAUSからも2名「取材見学」ということで参加させてもらいました。はらをわって話しやすいように年齢を限定している企画です。ちなみにぼくは51歳。軽く年齢の基準を超えているため「ぼくらが部屋にいることで、話しづらい雰囲気になってしまうのではないかな」と慎重になりつつ、若干緊張気味に見学させてもらいました。話される困りごとに、世代間の違いはあるのか?ぼくが訪れたのは14時くらいから1時間。三瓶さん、佐久間さんの他に5人ほどが参加。ポケット企画、弦巻楽団の劇団関係者の他にも「SNSなどで情報を見て参加した」という人も多数きていました。トピックは様々でしたが、10代や20代が直面する生身の疑問や悩みが話されていました。5月に行われる企画のプレイベントだったにもかかわらず、夕方まで開催された集まりには、のべ10人以上の人たちが参加したそうです。「どうやったら舞台の仕事で収入を得ることができるのだろう」「夜に勤務のある仕事をしながら演劇を続けるにはどうしたらいいのだろう」「とにかく札幌の若手舞台人とつながりたい」「公演資金を捻出するにはどうしたらいいのだろう」確かに20代の皆さんにとって切実な話題ばかりです。しかし、おそらくそれは若い方だけではなく、これはどの世代でも尽きない悩みでもあります。話していても解決するわけではないのですが、同世代の仲間と共有するだけで前向きになれるのかもしれません。ぼくは、20歳以上(フタムカシというのかな?)年齢が離れているわけなのですが、参加者皆さんの切実さと真剣さに襟が正されました。「世代」という言葉があります。今日集まった皆さんはいわゆる「Z世代」。それに対してぼくら1970年代生まれは「団塊ジュニア世代」なんて呼ばれていました。「ジュニア」とつけられると、なんだか添え物感があり、あまり居心地がよくありません。もしかすると、どの世代の皆さんも一括りにされるのは嬉しい話ではないかもしれません。しかし、こんなふうに、同じ年代の舞台人が世の山話をしながら出会う機会は、ぼくらが20代の頃にはなかったように思います。こういう企画を発案する20代に、ぼく自身勝手な頼もしさを感じます。本イベント「若手のための意見交流会」にも期待ですそれから、今回の話の中でも少し触れられていましたが、ポケット企画がとても配慮しながら提示している「ハラスメントのガイドライン」も、ぼくらの年代では考えられなかったことです。舞台芸術の稽古場こそ「ハラスメント行為があってナンボ」みたいなところがあり、ぼく自身もハラスメント行為自体に無自覚だったと振り返ります。もちろん、創作現場における意見の相違や考え方の違いがあるのは当たり前です。しかし、それが「健全な対立」だったかというと自信がありません。*1劇団「地点」のハラスメント問題や、続発する訴訟案件を見ていると、舞台芸術の世界は、集団の在り方や見方をアップデートしなければならないと感じてます。その反面、「ガイドライン」がたくさんなければ成立しないという創作環境にも、少しだけ違和感を感じてしまいます。ぼく自身が持っているこの違和感について「いろんな年齢、地域、立場、職種の皆さんとお話する機会をHAUSでも作れないかな」と個人的には考えています。何はともあれ、ポケット企画、三瓶さん、佐久間さんの活動には、大きな意義を感じます。今回の企画はプレイベントでした。5月3日に、本企画である「若手のための意見交流会」が開催されます。たくさんの人たちが思いを語れる集まりになるといいなぁと願っています。これからも、最大限で応援したいです。「若手のための意見交流会」の詳細はこちら余談になるのですが。1時間ほどの参加後、あけぼのアート&コミュニティセンターを出ようとしたところ、愛車のエンジンがかかりません。いろいろ調べてもらったところ、エンジンモーターの不具合ということで、整備工場がレッカーにきてくれました。中古車ならではの部品不良ということで、修理完了まで10日以上かかってしまいした。まぁ、こんな日もありますよね。*1京都の劇団「地点」の主宰・三浦基氏による元劇団員へのパワーハラスメントを巡る問題ポケット企画2021年まで三瓶竜大(劇団清水企画)のソロユニットでしたが、団体化が決まり、現在までに三瓶竜大・佐藤智子・吉田侑樹・藤川駿佑・さいとうあすか・泰地輝・森大輝の7人が所属しています。 毎週木曜日の定期稽古のほか、戯曲を読む会、事前批評会、ダンスレッスンなどをメンバー全員で企画、運営。他団体の俳優との勉強会や月に一度の観劇会なども精力的に行っています。“今”しかできない表現を大切に、文化全体の反映を願いながら日々創作活動に励んでいます。
ハウスサバイバルアワード ポケット企画「おきて」大阪・札幌公演ハラスメント対策にも配慮ポケット企画と伴走リポート#1 #ハウスサバイバルアワード ポケット企画と伴走リポート#1ポケット企画「おきて」大阪・札幌公演ハラスメント対策にも配慮2023.1.31text 渡辺たけし(HAUS)ポケット企画、大阪公演を成功させたい2022HAUSサバイバルアワードに、大学生の三瓶竜大さんが参加してくれました。三瓶さんは、HAUSの賞金を自らが主催する劇団「ポケット企画」が行う大阪公演の資金としたいと話してくれました。北海道を飛び出しいろいろな場所でパフォーマンスを行ってみたいというアーティストは多いはず。しかし、誰も知らない土地で公演を成功させると言うことは、簡単なことではありません。学生であるならば、資金繰りやコロナ対応を含めて、さらにリスクが高くなります。そんな中、ポケット企画は自分たちで大阪公演を行い、大きな反響と手応えを得てきたようです。劇団でハラスメントガイドライン作成ポケット企画が行なっている興味深い活動は「ハラスメントガイドライン」作成の取り組みです。ワークショップなどを行う時にも、参加者が不安なく参加できるよう「ハラスメント防止にむけた取り組み」を提示しています。2022年12月、ぼくも「ポケット企画『身体と演技』ワークショップ」に参加しました。ワークショップを進行する三瓶さんから「ハラスメント防止にむけた取り組み」が書かれたレジュメの説明がありました。ワークショップの内容自体も参加者の主体性に重きが置かれており、参加者との関係性にもこの「取り組み」の精神がいかされていると感じました。2022.12.17『身体と演技』ワークショップ演劇業界のハラスメント問題は後を立たず、ニュースなどでも内容を聞くたびに暗澹たる気持ちになります。20代中心で構成される「ポケット企画」が、率先してこの問題にとりくんでいることは、ぼくには心強く思えました。劇団内での「ハラスメントガイドライン」の策定についてもHAUSに相談をいただきました。HAUSアドバイザーの方にも参加してもらい、数度のミーティングを行いました。今後、なんらかの形がつくられていくことを期待しています。ポケット企画2021年まで三瓶竜大(劇団清水企画)のソロユニットでしたが、団体化が決まり、現在までに三瓶竜大・佐藤智子・吉田侑樹・藤川駿佑の4人が所属しています。 毎週木曜日の定期稽古のほか、戯曲を読む会、事前批評会、ダンスレッスンなどをメンバー全員で企画、運営。他団体の俳優との勉強会や月に一度の観劇会なども精力的に行っています。“今”しかできない表現を大切に、文化全体の反映を願いながら日々創作活動に励んでいます。
ニュース 「シアターzooを5日間で黒く塗りながらお芝居を考える会」参加者募集! 米沢春花さんと伴走#5 #ニュース 米沢春花さんと伴走#5劇場を黒くしながらお芝居のことを考えたい!2023.4.17text 渡辺たけし(HAUS)サバイバルアワードに参加してくれた米沢春花さんの企画「演劇のことだけを考える2日間」は、盛況で幕を閉じました。新たな企画として、米沢さんが次のような企画を行うそうです。過去の記事は、こちらです。「演劇のことだけを考える2日間」が/終わりました。「演劇のことだけを考える2日間」ZOOM打ち合わせしました。米沢春花さんと「演劇のことだけを考える2日間」というイベント企画を練る「シアターzooを5日間で黒く塗りながらお芝居を考える会」の詳細この企画は劇場の塗装や修繕作業を行いつつ、稽古から発表までを5日間で行います。参加者は役者又はテクニカルとして共にお芝居を作ります。作業を一緒に行うと参加費がどんどん安くなります。「一つの作品を作りあげる」というよりは、参加してくれた方と一緒にお芝居について考える時間を作る。「結果」よりもその「過程」を大事にする企画です。〇内容戯曲を使用した演劇の創作。戯曲:夏の夜の夢(作:シェイクスピア 訳:松岡和子)サポート:清水友陽(劇団清水企画)米沢春花(劇団fireworks)〇日程5月24日(水)14:00〜17:00(塗装)19:00〜22:00(稽古) 25日(木)13:00〜17:00(塗装) 19:00〜22:00(稽古)26日(金)13:00〜17:00(塗装)19:00〜22:00(稽古)27日(土)17:00〜22:00(稽古)28日(日)10:00〜16:00 (稽古)(13:00〜14:00お昼ご飯)発表会 5月28日16:30(その後振返り)〇場所シアターZOO〇参加対象・18歳以上の心身共に健康な方。・この企画に賛同し協力体制であること。・演劇経験者。・稽古に3/5以上参加し、本番に参加できる方。・コロナ感染対策にご協力いただける方。〇応募フォームこちらからお申し込みください。応募締め切り:2023年5月10日当日中申し込み〇料金大人:2500円学生:1600円見学1回 500円塗装のみ:無料※塗装作業に参加すると1日あたり400円参加費が割引されて行きます。※日曜はお昼ご飯、塗装作業の際はおやつが出ます。〇サポート清水友陽(しみずともあき)演出家・劇作家。札幌で活動する劇団清水企画代表。2022年より、札幌座のディレクターに就任。北海道演劇財団常務理事・芸術監督。米沢春花(よねざわはるか)札幌で活動する劇団fireworks代表。自団体では脚本・演出・舞台装置・舞台監督演等を行う。〇主催扇谷記念スタジオ シアターZOO 米沢春花(劇団fireworks) 協力 HAUS
ハウスサバイバルアワード 演劇のことだけを考える2日間ワークショップ計画進行中米沢春花さんと伴走#1 #ハウスサバイバルアワード 米沢春花さんと伴走#1米沢春花さんと「演劇のことだけを考える2日間」というイベント企画を練る 2022.12.14text 渡辺たけし(HAUS)今回、HAUSのサバイバルアワードに参加してくれた米沢春花さんが企画しているのは「演劇のことだけを考える2日間」という1泊2日の演劇ワークショップイベントです。米沢さん曰く、「子どもが小さいから参加できない・・・」とか、「仕事終わりが遅すぎて参加しずらい・・・」など、個人個人の皆さんの小さな困りごとにも目を向けて解消のお手伝いをしつつ、「演劇のことだけを考える」数日を作りたいと動き出しています。最近は、コロナ禍ということもあり、演劇関係者が新たに出会う場所が少なくなりました。いろいろな人が「演劇」を通して顔を合わせ、同じ釜の飯を食い、作品作りに関してあーだこーだとがっつり話し合う。そんな1日を作りたいということがコンセプトです。ただ、ワークショップを行うだけでなく、自分達を取り巻く環境のお話しや困りごと、忌憚なく話せる場所が欲しいと、米沢さんは話しています。もうすぐ募集フライヤーができそうですので、HAUSからもご案内したいと思っています。HAUSは、困りごと解消を中心に、応援してきたいと思っています。米沢さんの次の記事「演劇のことだけを考える2日間」演劇ワークショップを行います米沢春花脚本・演出・舞台装置・舞台監督。札幌生まれ。高校の頃から舞台に関わり、主に舞台装置作りなどを始める。2010年劇団fireworksを旗揚げ。以降、劇団の本公演全ての脚本・演出を手がける。
ハウスサバイバルアワード 「演劇のことだけを考える2日間」演劇ワークショップを行います米沢春花さんと伴走#2 #ハウスサバイバルアワード 米沢春花さんと伴走#2「演劇のことだけを考える2日間」演劇ワークショップを行います2023.1.31text 渡辺たけし(HAUS)企画者より「札幌で演劇活動をしている劇団 fireworks の代表の米沢春花と申します。今回「HAUS」さんの力をお借りして参加者のみなさんと、1日中演劇の作品づくりを通して話し合い、どっぷり演劇に浸かりながら「同じ釜の飯を食う」というのを行いたいと思ってます。そういうワークショップをやりたいです。ワークショップに参加する前の悩み、例えば、「参加したいけど〇〇が心配」などWSに参加する前の悩みなどもご相談ください。そういったことも一緒に模索しながら演劇作りができれば嬉しいです。」「演劇のことだけを考える2日間」がいよいよ動き出しました。ハウスサバイバルアワードに参加してくれた米沢さんが今回は函館を会場に1泊2日、参加者が戯曲を選び、簡単な発表に向け、あーだこーだと演劇を作ります。残念ながら今回は、定員に達したため参加は締め切られています。HAUSメンバーも数人ファシリテーターとして参加していますので、ワークショップの経過や内容はお伝えしていきたいと思っています。米沢さんの前の記事「演劇のことだけを考える1泊2日」というイベント企画を練る米沢春花脚本・演出・舞台装置・舞台監督。札幌生まれ。高校の頃から舞台に関わり、主に舞台装置作りなどを始める。2010年劇団fireworksを旗揚げ。以降、劇団の本公演全ての脚本・演出を手がける。
ハウスサバイバルアワード 「演劇のことだけを考える2日間」が終わりました。 米沢春花さんと伴走#4 #ハウスサバイバルアワード 米沢春花さんと伴走#4函館で演劇を作る2日間時間を共有して同じ釜の飯を食う2023.3.15text 渡辺たけし(HAUS)サバイバルアワードに参加してくれた米沢春花さんの企画「演劇のことだけを考える2日間」が、2月26日(土)、27日(日)の両日、函館市で行われました。過去の記事は、こちらです。「演劇のことだけを考える2日間」ZOOM打ち合わせしました。米沢春花さんと「演劇のことだけを考える2日間」というイベント企画を練る「同じ釜の飯」「子連れ歓迎」こんなワークショップでした会場は、函館にある古民家を改装したゲストハウス「大正館」。参加者は全部で15人。札幌、函館、稚内など道内だけにとどまらず、青森県、宮城県など道外からの参加もありました。コロナ禍で、人が集まりづらくなっていた昨今ですが、同じ釜の飯を食いながら、お芝居作りのワークショップを行うというのが今回のメインコンセプトです。米沢さんは、HAUSサバイバルアワードの賞金をこのワークショップ運営の一部に使ってくれました。この呼びかけに賛同した15人が函館に集結。2グループに分かれて「ただいま」というテーマで、2日間演劇作りを行いました。子育てと演劇今回のワークショップのもう一つの特徴は、子連れ参加がOKということでした。HAUSメンバーも託児要員として参加。この記事を書いているわたし(渡辺)も、なれない託児を行った訳ですが、泣いている子どもたちをあやそうと努力しても簡単には行かず、逆に涙目となっていました。子連れで参加者の中には「最初は、子どもを連れてきたことで、周りにも、子どもにも負担をかけている気持ちになり、参加したことを後悔した。でも、後になって考えると、子ども自身も新しい体験ができて成長につながった気がする」という感想を話してくれた人もいました。子どもを連れて参加できる表現活動は少ないのが現状です。今回のワークショップの形式が今後共有され、子育て世代も作品作りや学習ができる場が増えていけばいいなと願っています。「ただいま」と日本語と方言今回のワークショップの、もう一つの大きな特徴は、参加者がさまざまな場所から集まっているということです。普段の生活環境も違う上に、芝居づくりの方法も様々です。今回は作品を作る方法の共有からスタートしました。さらに、地域ごとの言葉の違いにも話題となり、自然と札幌、函館、東北の方言が作品づくりのなかに盛り込まれました。また、スペイン語が公用語であるエクアドル出身の参加者もおり、演劇作りの一つのテーマとして「言語」が立ち上がったことも興味深かったです。スペイン語には「ただいま」にあたる言葉がないのだそうです。言語がもつ、そもそもの成り立ちや、社会性に寄り添えたことも面白い点でした。人とつながること=同じ釜の飯を食う主催した米沢さんが最初からこだわったのは「同じ釜の飯を食う」ということでした。まだ、コロナ感染予防対策は怠れないものの、仲間と飯を食い、宿泊し、額を寄せ合い話しながら作品作りに向かう。そんな当たり前のことの重要性を再確認する場となりました。2日間を終えた参加者はさまざまな思いを持ちながら帰路についたようで、前向きな感想を多くもらいました。「育ちも環境も違うほぼ初めましての演劇人と、土日の二日間でオリジナル演劇を創作し発表するという経験はとても刺激的でしたし、これから道南を中心に演劇やイベントを開催するという心のスイッチを切り替える為にはとても有意義な時間でした。」「ただ集まって話をするだけでは到達できない、身体的応答を含んだ関係の深まり。普段は舞台を一緒に作る事でそんな関係を作り上げるのだけれど、合宿という方法もアリなんですね。青森でもやりたいな〜。」今回HAUSはファシリテーターとして参加今回の企画で、HAUSのオーダーされたことの一つは「ファシリテーターをしてもらえないか」という内容でした。作品作りが硬直しないよう、ワークショップを俯瞰する視線で参加し、2日間一緒に皆さんと時間をすごしました。ぼくらは中間支援をする立場なのにもかかわらず、「ファシリテーターなどのように、作品作りの内部に入り込むことは是か否か?」という論議が、HAUS内でもありました。もしかすると、HAUSが、企画運営の人たちとファシリテーターに適任な人をつなぐ・・・というほうがベストだったのかもしれません。思い返すと、反省点は尽きないところ。まだまだ、ぼくらの組織には未熟な部分もあることは否めません。ぼくたち自身も支援活動は未だ手探りなのですが、今後も迷いながら、人と人とが出会える場所を作る支援を続けていきたいと考えています。米沢春花脚本・演出・舞台装置・舞台監督。札幌生まれ。高校の頃から舞台に関わり、主に舞台装置作りなどを始める。2010年劇団fireworksを旗揚げ。以降、劇団の本公演全ての脚本・演出を手がける。
ハウスサバイバルアワード 「演劇のことだけを考える2日間」ZOOM打ち合わせしました米沢春花さんと伴走#3 #ハウスサバイバルアワード 米沢春花さんと伴走#3「演劇のことだけを考える2日間」ZOOM打ち合わせしました。2023.2.19text 渡辺たけし(HAUS)HAUSの支援とサバイバルアワードについてHAUSサバイバルアワード参加者・米沢春花さんによる演劇ワークショップ「演劇のことだけを考える2日間」の開催に向けて、1回目のZOOM会議が行われました。今回のワークショップには、札幌、函館、東北などからいろいろな人たちが参加しています。生活環境も様々、芝居に対する考え方もいろいろなようです。ZOOM打ち合わせでは、お互いの自己紹介や、どんなことをしてみたいかなどが話されました。また、どんな戯曲に触れてみたいか、演者をやりたいのか、演出に挑戦したいのかなど・・・何もないところから積み上げていく話し合いは、なかなかスリリングでした。言い出しっぺの米沢さんは、「主催者がパワーを持たないようにしたい」という考えから、ファシリテーターにHAUSメンバーを指名しています。なるべく、主催者と参加者が同じ目線でワークショップを行いたいという考え方自体が、今回の企画の趣旨でもあります。初めてづくしの企画のため、なかなか一筋縄では行かなそうですが、その分、興味深いワークショップになりそうな予感がします。米沢さんの前の記事「演劇のことだけを考える1泊2日」演劇ワークショップを行います米沢春花脚本・演出・舞台装置・舞台監督。札幌生まれ。高校の頃から舞台に関わり、主に舞台装置作りなどを始める。2010年劇団fireworksを旗揚げ。以降、劇団の本公演全ての脚本・演出を手がける。
HAUSのまわりの人々 活力が生まれる場所 Seesaw books #HAUSのまわりの人々 活力が生まれる場所 Seesaw books2023.3.15 text 奥村圭二郎(HAUS)今年のHAUSの活動にとって、とても大事な場所である書店「Seesaw books」。この記事では、ここがHAUSにとってどんな場所かお伝えしようと思います。東京で出版社に勤められていたオーナーの神輝哉さんは、2014年に札幌へUターンしゲストハウス「UNTAPPED HOSTEL」をオープンしました。事業を進められてきましたが、2020年に発生した新型コロナウイルスの影響により事業継続の岐路に立たされていたある日、ネットカフェ難民記事を見て「北海道の労働と福祉を考える会」へ連絡し、「UNTAPPED HOSTEL」の別館を使ってシェルターを始めることになったそうです。そして翌年2021年8月には、本格的に困窮者支援をやろうと決意をされて、クラウドファンディング『札幌に、カルチャーと公共の境界線を溶かす「書店+シェルターをつくりたい!」』をスタートしました。コロナの影響で宿泊業も大変な時期になぜ始めたのか・・・?疑問に思い伺いましたが、「自分でも理由はうまく説明出来ない」と神さんは仰っていました。HAUSでもサポートさせて頂いている株式会社トーチの佐野和哉さんと協力してクラウドファンディング(達成率488%)を行いました。神さんのメッセージが丁寧に綴られています。HAUSが行ってきた「ハウス・サバイバルアワード」(以下、アワード)はSeesawbooksの2Fの一室を借りて進めてきました。2022年9月13日〜9月22日には、アワードに応募してくれた人たちから応募動機を聞く「オープンマイク(個別編)」を行い、9月19日には公開形式でも行いました。オープンマイク(交流編)の様子。当日は多くのアーティストがプレゼンテーションを行った。オープンマイクの後、いよいよ活動への伴走が始まってからもシェルターの1室をお借りしていました。この場所ではアーティストにインタビューをしたり、相談事を聞いたり、勉強会のオンライン配信を行いました。建物の雰囲気が醸し出す居心地の良さが妙にしっくりきて、和室で車座になって話を聞くと、ゴールの見えない話もだんだんと溶けていくような気がします。「働くことと創作」についてアーティストの藤田冴子さんにインタビューを行なっている様子3部屋という決して大きくはないシェルターですが、だからこそ制度から漏れてしまった人たちのために柔軟に対応する事ができる特徴がこの場所にはあると神さんは仰います。シェルター、本屋、ゲストハウスの三つの関係をどんな場所にしたいか伺うと「活力が生まれる場所にしたい」と神さんは仰います。経営は順調にはいかない部分も多そうですか、色んな役割が詰め込まれて、色んな目的を持った人たちが絶えず流動しているこの場所は何か新しい文化が生まれそうな予感がします。参考URLUNTAPPED HOSTELSeesaw Books
ハウスサバイバルアワード 喫茶こんは作品だ!徳山まり奈さん伴走レポート #ハウスサバイバルアワード 徳山まり奈さん伴走レポート喫茶こんは作品だ!2022.12.text 羊屋白玉喫茶こんでお仕事中の徳山さんHAUSの伴走日記のひとこまです(でもなんだか伴走って言葉はしっくりこない。HAUSとアーティストの関係は伴走で良いんだろうか。新しい言葉をつくりたい。もしくは意義が拡張したらいい。)9/29木曜日、喫茶こんはドーナツの日。昼休みにドーナツ買って職場へ。夕方再訪。HAUSのサバイバルアワードの結果を伝えにゆく。内容はこんなだ。まず、「HAUSからのアプローチはいつでも断ってよいのです。」という前置きをして、喫茶こんさんの店主、徳山まり奈さんに伝えました。「”喫茶店と作家たちの’’寮‘’になる場所をつくりたい”これは、まり奈さん課題というか、背中合わせの夢ってゆか、壮大な作品作りだとおもいました。HAUSのわたしは、この作品に関わりたいです。」まり奈さんは微笑んでいる。わたしはさらに、「でも今年度でなんとかなるような課題じゃないと思いました。来月〜再来月〜にお金入用な差し迫ってるアーティストにはお金を渡すことにしたのだけど、まり奈さんとはゼロ円から始めたいです、作品ができるまで。」と。彼女は微笑んでる。「寮なんて言葉久しぶりに聞いたし、寮をつくるなんていう人は初めてだし。」彼女はまだ微笑んでる。北斗高校の隣に空いてる物件を見つけたという。どういう状態かわからない。わたしならその空き家の壁に「連絡ください!!」って張り紙をはってくるとおもうけど、まずは、懇意な不動産屋さんに聞いてみよう。電話。北33西9に空いている物件があるという。早い!でもあらためて理想の物件をまり奈さんに聞く。「喫茶店と図工室みたいなアトリエみたいなところが1階にあって、2階にはアーティストが短期間でも住む寮をつくりたい。住みながら作れたらな。」と。「どうしてそんなこと思いついちゃったの?」と聞くと、まり奈さんは語る。「喫茶こんに訪れる同じ世代の作り手たちから、就職してからは、職場と家を行ったり来たりで日々が過ぎていってしまうのって聞くの。学生の時みたいに作品作りたいけど時間も場所もない。仕事も忙しいし毎日ざわざわする。そんな人たちに用意したい場所。生活の中でなにか作る時間があることで安心するひとたちがいる。職場と家の往復から逃れて、バケーション?リハビリ?サバティカル(充電)なんだろ?」喫茶店に訪れる人たちとの会話から、滞在して作り出せる寮が必要だと、作る場所と時間が必要だとまり奈さんが言うならきっとそうなのだ。喫茶店には、フリーパフェチケット買ってくれたりするお客さんがいたらいいな。それは、アトリエでつくっているアーティストにわたされるチケット。甘味の時間。まり奈さんは、来週から新しく移転したレストラン「のや」に修行にゆくと微笑んでいる。北12東5。毎週金曜日。「のや」も、わたしの家の近くにあるのも嬉しい。続きます。
大仏造立プロジェクト無事会期を終えました 風間天心さん伴走レポート#1大仏造立プロジェクト 無事会期を終えました2023.2.22text 戸島由浦(HAUS)1/7-22、2/1-19、German Suplex Airlinesがモエレ沼公園にて、大仏造立プロジェクトの展示とワークショップを行い、無事会期が終わりました。HAUSは彼らに伴走していて、ミニ大仏づくりや設営スタッフの協力をしています。2020年5月よりスタートした「大仏造立プロジェクト BIG BUDDHA PROJECT」は、47都道府県をまわる「勧進キャラバン」を2年3ヶ月の時間をかけて、なんとか完了しました。ついにお披露目となった約6mの「令和の大仏」は、木と鉄で制作された「大仏棚」に、全国各地で作ってもらった1000体を超える「ミニ大仏」が並べられる姿をしています。全国の方々の思いを込めた小さな「ミニ大仏」たちが、まさに血となり肉となっているのが、この大仏なのです。会期中も、親子がそりで走り回るモエレ沼公園で、ガラスのピラミッド内「令和の大仏」へ、たくさんの人々が集っていました。大仏はとても大きいので、制作や設営、場所探しなど大変な労力が伴うようです。会期中、風間さんからHAUSへは、「突然取材が決まりました!」「設営の人手が欲しいです!」など、差し迫ったお誘いやSOSが来ました。だからこそきっと、関わる人が増え、よりたくさんの人の想いがこもっていくのではないでしょうか。実は、大きいというだけでなく、宗教由来のものであるということによっても、今回のような公共空間で、来場する方々と共に大仏を作り飾ることには、様々な制約と交渉が伴っています。これを受けて、風間さんとは、芸術と宗教について考える会を設けられたら良いですねと話しているところです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■German Suplex Airlines Exhibition「Big Buddha Project – 令和の大仏造立 –」展覧会概要会場:モエレ沼公園ガラスのピラミッド(北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1)時間:9:00-17:00入場:無料主催/German Suplex Airlines共催/公益財団法人札幌市公園緑化協会後援/札幌市、札幌市教育委員会(予定)助成/Sapporo Art Index(令和4年度札幌市文化芸術創造活動支援事業)、HAUS(Hokkaido Artists Union Studies)(令和4年度札幌市文化芸術創造活動支援事業)協力/一般社団法人 四方僧伽、インターネット寺院 彼岸寺、株式会社タダカラボタモチ、齊藤社寺設計室、さっぽろ天神山アートスタジオ、CAI現代芸術研究所、他力本願寺、天平令和の発願祭、なえぼのアートスタジオ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■風間天心美術家、僧侶。1979年、北海道東川町生まれ。2006年、第9回岡本太郎現代芸術賞に入選。2010年、大本山永平寺での修行を経て禅宗の僧侶になる。2011年、武蔵野美術大学パリ賞によりパリ市「Cité Internationale des Arts」に滞在。現代における「宗教と芸術」の相互作用を求めながら、国内外で多様な活動を続けている。
ニュース 株式会社トーチがクラウドファンディングはじめました #ニュース ニュース株式会社トーチがクラウドファンディングをはじめました2023.2.10text 戸島由浦(HAUS)ウェブメディア「トーチライト」の書籍化へ向けて、クラウドファンディングが始まりました!ぜひまずは、内容と、トーチからのメッセージを見てみてください。今回、HAUSサバイバルアワードに参加した株式会社トーチの佐野和哉さん。「どこにいても、つくってゆかいに暮らす」をテーマに、メディアづくりから場所づくりまで、精力的に幅広く活動なさっています。HAUSもいつも様子を伺いながらエールを送ってます。株式会社トーチからクラウドファンディングのお知らせ佐野和哉1991年生まれ、北海道遠軽町出身。株式会社博報堂、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)、株式会社quantum、フリーランスを経て、2020年に北海道札幌市にて株式会社トーチを設立。札幌市と故郷のオホーツクエリアを行き来しながら、「北海道でやりたい仕事をつくる」という目標を掲げ、メディアやコミュニティを絡めた事業開発・ブランド開発を行っている。札幌クリエイティブコンベンション「NoMaps」実行委員、札幌国際芸術祭2024プロジェクトマネージャー。
インタビュー 札幌で初の専門劇団をつくる 戦後北海道と歩んだ演出家 インタビューその3 演出家・鈴木喜三夫さん #インタビュー インタビューその3演出家・鈴木喜三夫さん札幌で初の専門劇団をつくる戦後北海道と歩んだ演出家Text : 渡辺たけし(HAUS)Photograph : 長尾さや香Place : 演劇集団「座・れら」事務所(札幌市)2022.11.27HAUSアーティストインタビューは、札幌で活動するアーティストを、たくさんの人に知ってもらいたいという思いからスタートしました。第1期は2022年夏から2023年春に取材したさまざまな分野のアーティストを順次掲載します。インタビューその1、その2は、兼業アーティストを取り上げてきたのですが、今回は1950年代から専業で活動されている札幌演劇界のレジェンドアーティストを紹介したいと思います。「・・・専門にお芝居をやるってことがどういうことか、札幌の人には理解してもらえなかったようです。よく「劇団」ではなく「楽団」に間違われていました(笑)・・・」札幌でアーティストとして食べていくことの大変さは、今も昔も変わらないようです。さて、まずは劇団設立時の苦労からお聞きしました。札幌で初めての専門劇団を旗揚げーお生まれは何年ですか。1931年ですから昭和6年です。91歳です。ー90代の方に取材させていただくのは初めてです。よろしくお願いします。2017年で演出は、高齢のため辞めていたんですけれど、去年(2021年)90歳で久しぶりに劇団「座・れら」の演出に引っ張り出されました。昨年の『アンネの日記』を、「れら」の団員が初めて演出するということになり、私が演出を薦めたもんですから、どうしても応援しないとなんなくなりました。それで共同演出というかたちで関わりました。※座・れら=2009年春、演劇制作体「鈴木喜三夫+芝居の仲間」の常連4名で発足した劇団。座長は鈴木喜三夫さん。※『アンネの日記』=ナチスに迫害を受けたユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランク作『アンネの日記』を、ハケット夫妻が戯曲化したもの。ー今まで何本くらいの作品を作られたんですか?中学生から演劇を始めたので、れらで最後に演出した2017年『アンネの日記』まで数えると133本のお芝居(脚本含む)をつくりました。昨年の番外編の『アンネの日記』共同演出で134本になりました。ーまずは、劇団「さっぽろ」の話を聞かせてください。1959年の結成当時から職業的な専門劇団を目指していたとお聞きしました。※劇団「さっぽろ」=北海道を基点に学校公演や一般公演と数々の上演を行っている専門劇団。最初から「専門劇団」ということを銘打っていました。だから、稽古は全部昼間です(笑)。1957年NHK東京で脚本の仕事をしていた頃の鈴木さんー1959年というと、まだ札幌の文化的は黎明期だったと思うのですが、その時代から専門劇団を目指したのはどういう理由だったんでしょう?私は戦争が終わってすぐ、演劇がしたくて東京の大学に行き、舞台美術の仕事をしたり、当時始まったばかりのTVドラマの台本を書いていました。しかし、東京の生活もなかなか大変で札幌に戻ってきました。当時、札幌には児童劇団「こりす」というところがあり、そこで何度か演出を頼まれました。その児童劇団の何人かと専門劇団を旗揚げをしました。※児童劇団「こりす」=1957年に札幌で旗揚げされた児童劇団。「札幌子供の友会」でお芝居を学んだ人々により結成された。1958年 劇団こりす『うぬぼれ兎』ー札幌で旗揚げしようと考えた一番の理由はなんだったんですか?まだその頃は、北海道に専門劇団がなかったんです。戦後すぐに、専門劇団を目指して旗揚げしたところはあったんですが、長続きしないで潰れちゃっていたんです。その時、僕は28歳でした。30歳前にしてこれから人生を何に賭けようかって考えていた時期だったんです。北海道で最初に専門劇団を作ろうというのが、劇団「さっぽろ」の発足のきっかけです。ー結成を最初に言い出したのは鈴木さんですか?そうです。発足当時、劇団「さっぽろ」に集まってきた人たちは、実家暮らしで仕事しなくてもいい奴か、仕事をやめてきた奴らでした。「『3ヶ月で潰れるだろう』ってみんなが言ってたことが、まさしくそんな風になっちゃったんです。」ー最初の劇団員は何人くらいだったんですか?15か16人くらいかな。その他に協力してくれた人はいろいろいましたから、実際に活動を始めたときは20人ぐらいです。ー結成された1959年当時、札幌に劇場はあったんですか?その頃、札幌市民会館と札幌商工会議所ホールなど2つか3つの劇場ありました。公民館もあったけれど、それは劇場といえるものではありませんでした。ー機材や道具などはどうしていましたか?劇団員みんなで、全部手づくりで作りました。1960年、劇団「さっぽろ」がやっと一人前になるきっかけになる公演が『アンネの日記』なんです。その時は中島児童会館で活動していました。そこに100人入るくらいのあんまり広くない舞台ホールがあったんです。そのときの館長が理解してくれて、劇団「さっぽろ」に使わせてくれていたんですよ。ー1960年当時、専門劇団で食べていくっていこうということを、札幌の人たちはどう思ってたんでしょうね。「3ヶ月で潰れるだろう」と言われてました(笑)。専門にお芝居をやるってことがどういうことか、札幌の人には理解してもらえなかったようです。よく「劇団」ではなく「楽団」に間違われていました(笑)ー旗揚げした劇団員たちも「これ一本で食べていけるんだ」っていう確信はあったんですか?ないです。劇団「さっぽろ」旗揚げ当時、北海道に児童向けの劇を上演する旅回り専門の劇団「どら」というところがあったんです。自分たちに専門劇団の経験ないから、力を借りたいと思って、その劇団「どら」の2人を劇団「さっぽろ」に招き入れたんです。ところが、それは成功しなかった。半年もしないうちに、うちの若い連中を何人か連れて抜けていった。ー旗揚げ早々の大ピンチですね。「3ヶ月で潰れるだろう」ってみんなが言ってたことが、まさしくそんな風になっちゃったんです。劇団「どら」が出て行ってしまった後すぐに、北海タイムスという新聞に「北海道には専門劇団は育たない」という記事を書かれたりして、私達は悔しかったです。ならば、「自分たちが何としても専門劇団を作ってみせる!」っていうのが、劇団「さっぽろ」を続けた一番根源になったんですよね。ー劇団「さっぽろ」は、早くから給料制を取り入れたと聞きました。株式会社にしていました。何とか芝居で生活したいっていうことがあったんで、そのためには給料制が一番よかったかなと思っています。学校巡回公演を取り入れ給料制劇団へー劇団「さっぽろ」の給料制は、最初からうまく行っていたんでしょうか?旗揚げしてから3年くらいは、劇団の収入が1ヶ月1万ぐらいでした。みんなに割り振るするような金額ではないです。『アンネの日記』を上演したとき、初めて一人に1000円ずつ配って、皆で大喜びしたことがありました(笑)。1960年 劇団さっぽろ『アンネの日記』初演ーそこから少しずつ収入が増えていたんですね。最初は、劇団の普及活動(営業活動)する人たちと、事務所に勤める一部の人たちに手当を払いました。あとはみんなアルバイトで生活していました。昼に稽古ですから、働かないとならない連中は、夜に新聞配達やバーなどいろんなとこでアルバイトしていました。その後は、手当を払える人を段々と増やしました。ー劇団員皆に給料を払えるようになったのは、いつくらいでしたか?宮の沢の稽古場ができたのが、劇団「さっぽろ」設立から20周年のちょっと前ですから、その頃だと思いますね。当時で月10万ぐらいの給料を払いました。そうすると夫婦でやってる人は月20万ですからね。何とかギリギリやっていけました。ー劇団「さっぽろ」の最初の目標は、給料制の導入と稽古場の設立だったとお聞きしました。目標を「劇団が所有する稽古場をもつこと」に置いたんです。宮の沢に現在もある稽古場を1976年に作りました。でも、今考えると、「稽古場」ではなく「劇場」を目標にするべきだったと思っています。だから、その辺はちょっと反省をしてる。「一番多いときで年間400ステージぐらい上演しました。」ーその後、旅回りの学校公演が増えたとお聞きします。「自分たちはこんなに朝から晩まで頑張っているのに、芝居だけではなんで生活できないんだろう?」っていう疑問がありました。旅回りの学校公演を積極的に行うことにした理由の一つは、「食えるようにする」ということでした。しかし、旅回りをするかどうか、劇団内でずいぶん議論しました。ー旅回り学校公演に反対の団員もいたんですか?「旅回りをすると演技や芝居が荒れる。だから、旅回りをすべきじゃない」っていう意見と「北海道の劇団なんだから、北海道中を回るべきだ」という意見に分かれました。芸術至上主義的な考え方だと前者なんですが、だけど、新劇的な運動的な立場でいくと後者なんですよ。ずいぶん論議しましたけど、最終的には旅回り学校公演(巡演劇場)をしようということになりました。※新劇=明治時代以降、歌舞伎や新派に対して、ヨーロッパ翻訳劇を中心として上演した新しい演劇のムーブメント。戦後は、自分達の思想を演劇の形で表現し社会運動とも結びついた。ー劇団の経営を安定させるために学校公演が多くなったんですね。もちろん、一般の人たち向けの公演もやりましたよ。ですが、主体は小中高の学校の子どもたちに見せるお芝居をすることが、劇団「さっぽろ」の中心になり、ある程度成功したと言えるでしょう。一番多いときで年間400ステージぐらい上演しました。ーどのようなシステムで劇団は運営されていたんですか?一番多いときには3班体制。1班目は5人くらいの団員で幼稚園などをまわり、2班目は10人くらいの大型班で小中学校をまわりました。他のメンバーは高校や一般向けの公演っていうことで3班体制です。だから、劇団員が当時30~40人近くいました。最初の頃は、旅館はお金がかかるので劇団員は、体育館にマットを出したり宿直室など、学校に泊めてもらう。昔はそういうことは緩やかだったんです。ーいろんな学校に行くと、劇団「さっぽろ」の色紙が残っていますよね。僕の世代(40〜50代)には懐かしい風景です。今でも時々「子ども時代に劇団「さっぽろ」のお芝居を観た」という人に出逢いますよ。古巣の劇団を離れフリー演出家としての道へーその後、鈴木さんは劇団札幌を退団して、フリーの演出家になるという選択をされました。それはどういう考えからだったんでしょうか。一番大きいかった理由は、3班体制で学校巡回公演をすると、どうしても年間で「これだけのお金が要る」ということになります。ーお金を稼ぐことが目的になるということですね。舞台の創造的な質なども考えているんですけれど、作品の選び方なども「お金を稼げること」に集中しちゃいますね。それは仕方がないことだと思うんだけども、やっぱり創造集団の一番の要はいい作品を作るっていうことなんですよ。そこのところの意見が、劇団「さっぽろ」と僕とで合わなくなってしまいました。劇団「さっぽろ」を離れたのは、そういう理由が大きいかな。「自分のやりたい作品をやろう」というのが、フリーとして独立した大きなきっかけでした。それからもう一つは、北海道の演劇史を書きたいってことでした。ー経済的なことを考えながら劇団を経営していくことは、とても難しい問題ですね。難しいです。しかし、劇団を維持してくために、とても必要なことなんだけど。ー劇団「さっぽろ」設立の時代からすでに50年以上経ってるんですけど、僕らが抱えてる問題はあまり変わっていません。札幌で芸術で食べていくことは難しいです。社会的もあまり変わってないですね。日本の場合は演劇に対して厳しいですね。音楽などは、どちらかというと上手くやっているように見えます。オーケストラなどは国や自治体から支援を受けているところが多いです。お芝居が一番支援を受けてないっていうふうに思います。ーそうかもしれませんね。外国でも、国からの支援をもらってやってるってことろが多いですよね。芸術そのものの需要と供給がバランスを維持できるような状況ではありません。そのことの理解が、非常に日本は弱いですね。ー国や自治体からの支援の状況も、50年経っても変わらないですか?変わらないですね。札幌は一時期よりちょっと後退してますね。過去、「座・れら」が稽古場を維持するための補助として、予算をもらっことがありました。そういうことも今あんまりないようですね。ー今回HAUSは、札幌市の札幌市文化芸術創造活動支援事業の助成をうけて活動していますが、来年も続くという保障はありません。根本的な問題を解決するために、これからどうなってったらいいとお考えですか?北海道では、お芝居の演技を教えて月謝を取る「教室」のようなものは少ないですよね。ところが、踊りや音楽は必ずそういうシステムありますよね。バレエなどでも、月謝を払って教えてもらい、それを発表するということが一つの流れになってますよね。演劇はそれが少ないんですよね。ー趣味でピアノを習いに行くということはあるけれど、「演劇を習いに行ってます」という人は少ないですね。だから、地方自治体なんかも、演劇などの養成所を作ってくれるといいんだけど。最近は逆に、自治体が関わるイベントが減っていく方向ですよね。ー北海道で初めての専門劇団を作りったり、学校巡回劇を始めたりと鈴木さんは新しいことにどんどん挑戦されましたが、北海道でフリーの演出家の仕事はすぐに軌道にのったんでしょうか?劇団「さっぽろ」を設立したときのことに比べると、全然すぐにうまくいきました(笑)。ーなるほど(笑)「鈴木喜三夫+芝居の仲間」を経てアマチュア劇団「座・れら」へ劇団「さっぽろ」で全道を回ってましたので、いろんな人たちと交流がありました。人形劇や音楽劇を創る方達とのつながりもできていました。劇団「さっぽろ」時代のいろんな実績が繋ながった成果でした。そういう意味では、自分がやりたいことが自由にできるという解放感は大きかった気がします。また、フリーで仕事を受けながら、それとは別に演劇を制作する集まりとして「鈴木喜三夫+芝居の仲間」というプロデュースシステムのグループを作ったんです。自分で作りたい作品も作るという両車輪を持ったんです。これがうまくいったんだと思います。ー「鈴木喜三夫+芝居の仲間」というプロデュース集団は、10年ほど続けられたとお聞きしました。「鈴木喜三夫+芝居の仲間」は、僕が制作と演出をしていたので大変でした。経済的な負担は、僕が全部個人で背負わないといけなかった。本当は制作体制を確立したかったんですけど、残念ながらそれはちょっとできなかったんですよね。それで結局「鈴木喜三夫+芝居の仲間」は15回公演で解散して、「この先はアマチュア劇団でやるしかないだろう」と考えました。アマチュア劇団を作るにあたっては、どこかの劇団に所属する人たちを引っ張るわけにいきませんから、フリーの人たち4人を中心に、現在の劇団「座・れら」を作ったんです。ー鈴木さんは、すでにいろいろなことをやり尽くしてる感じですが、これからやってみたいことなどはあるんですか?あります。「アンネ・フランク」に関わる作品を、さらにもっと創りたいという思いはあります。ー北海道の演劇の歴史と鈴木さんの歴史が重なっていて、刺激をいただいたお話しがたくさんありました。また、ぜひ、お話しの続きをを聞かせてください。はい、よろしくお願いします。いつでも呼び出してください。喫茶店になら、いつでも行きますよ。子どもの頃から、劇団さっぽろのお芝居を観てきたぼくとしては、胸がキュンとするようなお話が聞けて濃厚な時間でした。取材後は、鈴木さんオススメの蕎麦屋にも伺いました。「兼業アーティスト」「専業アーティスト」それぞれに創作にまつわる苦労や変遷があるものだなと感じました。札幌でサバイバルしてきた鈴木さんの言葉一つ一つに重さを感じましたよ。「兼業」の人中心にお話を聞いてみようかなと思いスタートしたHAUSアーティストインタビューなのですが、「専業」で活動してきた(している)芸術家のお話も興味深いなと感じました。そんなことを考えていたら、最近、京都で活躍する振付家が札幌に移り住んだと聞きました。京都と北海道の2都市で創作するのって、どのような感じなのか。興味が湧いてしまいました。次回のインタビューはこの方です。インタビューその4振付家 きたまりさん(アップされるまで、もう少しお待ちください)今回インタビューされた人 鈴木喜三夫1931年、札幌市生まれ。1953年東京の玉川学園大学教育学部入学。1956年同大学中退。イタリアオペラの裏方やNHKテレビライターとして活躍。1959年28歳で専門劇団さっぽろ創設。代表・演劇研究所長を歴任。1986年劇団さっぽろを退団、フリー演出家となる。劇団時代から演劇教育に携わり、北星幼稚園教諭保母養成所、教育大旭川・同釧路校などで表現の授業を担当。2004年に『北海道演劇 1945‐2000』を刊行今回インタビューした人 渡辺たけし1971年小樽生まれ。公立中学校数学教員。劇作家、演出家。いろいろな地域の人々を取材し演劇作品などにしている。HAUSでは、アーティストの労働条件や人権について担当。
ハウスサバイバルアワード HAUS studies vol2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」を開催しました #ハウスサバイバルアワード サバイバルアワードHAUS studies vol2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」を開催しました2023.2.22text 戸島由浦(HAUS)https://www.youtube.com/watch?v=BA6X4-6FinQ アーカイブ映像1月22日(日)、HAUS studies vol2/「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」を開催しました。契約や話し合いの切り出し方、本番前に確認しておくべきこと、幅広く教えていただきました。アドバイザーとして来ていただいた弁護士の田島佑規さんは、2月末に札幌で開催される、onpamによる「関係づくりを学ぶ!現場で使える契約講座」にも講師としていらっしゃいます。俳優のリンノスケさんがHAUSに相談してくれたことから始まったこの勉強会。契約というと耳障りが固いですが、企画を制作するときに、依頼側も出演側も、互いの認識を対話の中で確認しておくことが大事ということだと思います。立場の違う者同士がどんな話し合いをできるかということについても、参加者の実際の経験を元に話しました。◆目次◆00:01:40アーティスト支援事業、ハウスサバイバルアワードの仕組み00:02:22アーティストからの相談を聞いたことがこの勉強会の始まり ※アーカイブは出演者の了承を得て公開しています。00:02:33 相談者 リンノスケさん 自己紹介00:04:00 弁護士 田島佑規さん 自己紹介00:08:13 インフォメーション00:12:25 HAUSメンバー自己紹介(櫻井ヒロ 羊屋白玉 箱崎慈華 戸島由浦 渡辺たけし 奥村圭二郎)00:15:15 本題「出演依頼受けてもギャラを伝えられないことが多いし、自分から聞きずらい」(櫻井)00:14:17 ハウスがサバイバルアワードのアーティストと交わしている覚書について(羊屋、戸島)00:21:30 アーティスト契約書を作ってゆこうという気運が立ち上がっていった世の中の流れなど(戸島)00:23:21 田島さんが考える契約書を作って良い環境にしてゆこうという気運のきっかけ ①コロナで上演がキャンセルになった時、それまでの経費どっちが払う? 契約書があったら話し合いができたのに、、、 ②主催者側からは、世界的に上演配信が広がったときに、日本の現場では、配信に対する契約関係が作られていなかったため、遅れをとった。③芸術分野のハラスメント問題への対策 ④フリーランス保護法 ⑥文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン しかし、契約書が作られても、アーティスト側には不利かもしれない場合、一つ一つ読み込んでゆかないといけない。00:29:46 田島さんへの質問タイムに入ります。Q1.サブタイトルにもある「契約とは対話」とは誰と誰のどんな対話なんでしょうか?A1.対話によって、お互いの落とし所を見つけるため。とはいえ、両者ハッピーとは限らない。バランスが大事である。そのためにも対話が必要。00:32:40 Q2.プロジェクトや企画が始まろうとしている時に、遅くともここまでに契約書を交わすべき、そのデッドラインはいつなんでしょう?A2. 理想としては、企画が始まろうとしている時に、契約内容の会話が始まっているべきです。間に合わない場合は、契約書の内容を決めてゆくスケジュールを立てる。今決められない内容は、いつ頃までに決めるのか、など。00:34:21 契約に関する悲しい事例オンパレードなどQ3. ノーギャラも契約は成立するんですか?A3. 合意があれば原則成立。契約はギャラのこのだけではないし、権利関係の契約もある。契約書はよく読んで、内容を納得してからサインをすること。家に持ち帰って読んできますと言っても良い。00:40:00 出演者だけど契約書を作ってみた(櫻井)主催者側は今まで一度も、出演者たちと契約書などを交わしたことがなかったので、出演者の一人である自分が、何を主張して良いかわからなかったけど、他の出演者の聞き取りをしながら、主催者側との契約書を作ってゆこうと思った。契約書作りのやりとりはまだ続いている。舞台初日は2月4日、本日1月19日。00:50:00 リンノスケさんの実感や気づき大学生の頃から、表現活動をしてきたけど、今は自分の生活のこともあるし、契約書を作らなければと思った。でも、今まで付き合いのある方達に改めて契約書の話はしにくい。制作側と仲良くならない方がいいのかなと思う時もある。00:54:45 Q4. 契約の話の切り出し方って、難しいです。A4.言いにくい時は人のせいにする。確定申告があるとか。勉強会とかに参加したら、弁護士さんが契約書は必要ですと言っていたから、とか。HAUSがうるさいから、とかでもいい。最終的には、切実に伝えてゆく心づもりも必要。00:57:35 Q5. 契約に記載するとよい項目はなんでしょうか?A5.文化庁のガイドラインが参考になる。ひな形が役に立つ。自分の場合にふさわしい雛形を選ぶこと。チェック項目として役に立つ。◆文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインの概要https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/93744101_02.pdf◆ひな形は31ページからhttp://onpam.net/wp-content/uploads/2023/02/on-pam_keiyakuguidebook.pdf01:01:24これらは元々ある労基法から文化芸術用にカスタマイズしてる。具体的にアーティスト用にカスタマイズしたいから、ハウスもワークルールも勉強したいなと思っている。(羊屋)01:02:11 そろそろ後半、契約書を具体的にどう作るべきか。onpamによる「関係づくりを学ぶ!現場で使える契約講座」開催 ぜひお越しを札幌会場 2023年2月28日(火)北海道教育大学札幌駅前サテライト時間:19時~21時 定員:各回40名(先着順)受講料:無料 申し込み:https://sites.google.com/onpam.net/keiyaku/01:04:57 Q6. 契約書を自分で作るときは何から始めるのが良いのでしょう?A6.自分にとって納得のゆく内容が一番良い。そして専門家に見てもらう。専門家に相談するとお金はかかるので、取引としての見積書がおすすめ。自分にとって、発注者に守って欲しい内容、条件を箇条書きにしてメモに残しておく。簡易バージョンでもいい。そして、その見積書にサインをもらう。01:11:42 事前にきている質問で多かったもの。Q7.ギャラ交渉の前に、そもそも自分の適正な価格がわからない。A7.ワンステージいくらとか相場で決めることができる。著作権に絡む配信の二次利用の相場は今作っている。兼業に関しては、社会的意味として、兼業だからといって安く受けすぎると、他のフルタイムアーティストの人たちに迷惑になる。広く業界の人たちのためにも基準を作っているのがいいと思う。自分にも相手にも社会にもいいラインを見つけてゆかなくては。01:17:00予算を聞かせてもらって、自分のギャラはそのうちの何%払って欲しいと交渉する時もある(羊屋)01:19:42 兼業アーティストですけど、もう一つの仕事の方を補填できるかどうかも目安で。とはいえ言い出しにくい。脳内契約書で色々予測する。(櫻井)札幌は、ワンステージ1万円かな。参加費みたいなチケット何枚買取ですってのもある。(リンノスケさん)興行リスクまで出演者側が負わされてしまうのはひどい。(田島さん)01:23:40 ある美術家から契約書を交わすことはほとんどない。口約束が多い。メールの時もある。ギャラは仕事の依頼が来た時に、決まっていたり決まっていなかったり。先方に交渉するのはハードルが高いです。など。約束されたギャラが支払われない問題。弁護士料とか考えると費用倒れになる。メールや紙で残す。悩ましいです。日本美術家連盟。イラストレーター連盟。に相談する。(田島さん)01:29:30 あるクラシックの音楽家から。契約の文面も残していたのだけど、表沙汰にすると業界に干されてしまうリスクを考えると怖い。01:30:36 あるミュージシャンからの感想クラシックは確立された世界。自分の師匠の人脈などでキャリアも決まる。パワーバランスなど独特の業界。風穴を開けてゆくのは難しい。01:33:01 ある俳優からQ8.知り合いの人からこのCMナレーションの話があるけど、ギャラこれくらいだけど、って紹介がありました。もうちょっとギャラあげてくださいって言いたい場合は、誰との契約になりますか?A8. お金が事務所側から出るのなら事務所と話をする。場合によっては、三者間で話す場合もある。契約のポイントは、契約の相手は誰なのか?誰との契約なのか?を確認すること。01:39:00 先ほどのあるミュージシャンからの事務所中抜き事件20年くらい前、いわゆるモンキービジネスでしたが、事務所が間に入る場合は、元の値段を知ることはタブーでした。でも、元がいくらか教えてもらえたことがあって、その時は、事務所から僕に払われたのは3万で、元は60万だった!01:42:35 公務員労働組合を経て(渡辺たけし)Q9.労働組合をやってきた頃は、集まって何かを要求するってことはしてきたんだけど、アーティストたちの場合、事業主の場合も多いし、どういう集まり方の形態が良いのか、どうお考えですか?A9.文化芸術の業界団体で同じ職能で集まって要求していることはありますね 劇作家協会とか 団体名義で出してゆくってことはあるハウスがそういうことを肩代わりできるんでしょうか?(渡辺)個人的には、むしろハウスがそういうことをすることが社会的な役割として期待されているのでは? アーティストからギャラの話をしたらダメなんじゃないかとか、言い出せない孤独感があると思うんですけど、そんなことないよって言える、「対話」をしてゆく、北海道内での空気づくり、風土を作ってゆくことがハウスができると良いですね。(田島さん)発注する立場になる場合もある 発注する側も孤独 興行リスクもあるし、そういうのをどう汲み取るか、そういう話ができるところもあるといい。(渡辺)01:52:45札幌での2/28のonpam講座は、スタッフや出演者に仕事を発注するときの、いずれの立場にも双方向な、模擬交渉的なワークショップです。01:54:24 先ほどの、あるミュージシャンから、「お金をもらって作品を作るのは良いこと」って話。お金もらわないでも作ってた時もあったけど、お金をもらうようになってからクオリティが変わってきてるんです、確実に。お金をもらうようになってから、曲を作り、演奏し、録音し、世間に出してゆくように変わっていった。その変化は、人との繋がりもできるし、社会的なことでもあるし。お金が儲かるからいいんじゃなくて、人が稼いだものが僕に支払われる。これは、いいことだと思う。◆勉強会概要◆HAUS studies vol.2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」~契約とは、対話なのです~主催:リンノスケ(俳優) × Hokkaido Artists Union Studies助成:令和4年度札幌市文化芸術創造活動支援事業公演が決まったけれど、いくらもらえるか分からず、あえて突っ込もうとも思わない。展示が決まったけれど、制作費も交通費もないぞ。契約書、ありがたいような気がするけれど、内容はよく分からない。確定申告って、インボイスってなんなのだ。あの作品を使いたいけれども誰にご相談すればよいのか。疑問はつきません。今回は、弁護士の田島佑規さんをお迎えし、活動にまつわる実際のトラブル事例やその対策を取り上げながら、北海道のアート活動において出演交渉等にどう向き合っていくべきか、依頼される側、する側それぞれの立場を踏まえながら考えてゆきます。些細なことでも、ワークルールに関するお悩みあれば、ぜひご参加を。オールジャンルのアーティスト、マネージャー、デザイナー、お待ちしております。アドバイザー:田島佑規(たじまゆうき)「骨塩通り法律事務所」弁護士。その他、文化庁EPAD事菜 権利処理チーフ、緊急事態舞台芸術ネットワーク車務高、京都大学法科大学、芸術文化製光市門職大学 非常野菜市等を務め、アー下、満時、映像、出版、音楽などの分野にて法務サポートを行う。2019年より、「デザイナー法)小他の企画・運営を行っている。聞き手:リンノスケ俳優。北海道出身。札幌市立大学デザイン学部卒。在学時の2015年より俳優・舞踏を始め、2016年に旗揚げしたきっとろんどんを共同主宰。また劇団千年王國に出演した際は「贋作者」では鴈次郎役、「ロミオとジュリエット」ではロミオ役でそれぞれ主演を演じた他、micell、モノクロームサーカス、東野祥子、伊藤千枝、田仲ハル、Sapporo Dance Collectiveなどのダンス・舞踏作品にも出演。2022年からは活動拠点を東京と北海道の2拠点に広げた。
ハウスサバイバルアワード 子育て中のアーティストが すすきのの台湾料理屋に 集まりました #ハウスサバイバルアワード HAUS交流会子育て中のアーティストがすすきのの台湾料理屋に集まりました2023.2.8text 羊屋白玉(HAUS)お父さんで お母さんで アーティストで 子供がいるわたしたち と その隣人たちの集いすすきのの台湾料理ごとう さんに集まりました〜 美味しかった ごちそうさまでした〜ハウスのサバイバルアワードなアーティストたちは40人 その中には お父さんでお母さんで子供がいるアーティストたちがいます 子育てと創作と仕事 両立鼎立は嵐のような毎日だと察します でもそれが特別だっていうわけではなくて その隣人としてのアーティストたちとテーブルを囲み どんな話に花が咲いたのか忘れましたが あっという間に終電でしたなんとなく相談も始まり 宿題として持ち帰ってきましたが 逆にいろんなアイデアをいただき 立春🍡 って感じでした〜また話しましょう〜 次回は他の面々もお誘いします〜
ニュース THE ICEMANS寒波とともに北海道を縦横無尽に波乗りしてます #ニュース ニュースTHE ICEMANS寒波とともに北海道を縦横無尽に波乗りしてます2023.2.13text 羊屋白玉(HAUS)寒波とともに北海道を縦横無尽に波乗りしてますアイスマンズをトラッキングするのは至難の業現在 サッポロアートキャンプ@芸森で作品を展示し 西の方へでかけた模様SAPPOROARTCAMP 19日までです!
ハウスサバイバルアワード RED KING CRAB 「遭難」本番中高生にナマの演劇を観て欲しい #ハウスサバイバルアワード 竹原圭一さんと伴走リポートRED KING CRAB 「遭難」中高生にナマの演劇を観て欲しい2022.12.17text 渡辺たけし(HAUS)RED KING CRAB「遭難」に中高生を無料招待RED KING CRAB「遭難」の公演が、2022年12月15日〜18日、生活支援型文化施設コンカリーニョ(札幌市)で行われました。主宰の竹原圭一さんは、HAUSサバイバルアワードに参加し、HAUSからの賞金の一部を、コロナ禍で活動制限がかかる学生支援に使いたいと言ってくれました。今回の公演の中で「RED KING CRAB」は学生170人の無料招待を行いました。実際に観劇した生徒さんからも多数観劇の声が届いているそうです。下記は、札幌市内の高校1年生の感想です。「・・・2人の本音を言いあうシーンでは、追い込まれた時に垣間見える人間「欲」が演技に見え隠れしていて、遭難することの恐怖や1人で山小屋に留まることがどれだけ本人にとって孤独なことだということが伝わってきました。・・・私もいつか、今回見させていただいた「遭難」のような巧妙に作られたセットと美しい音響・演出の中で自分の演技をしてみたいと思いました。・・・」また、竹原さんは学生が公演するときの機材提供などの費用として、HAUS からの支援金の一部を使ってくれています。極寒のTHE ICEMANSアジトで稽古THE ICEMANSのアジトで稽古をするRED KING CRABの皆さんまた、HAUSサバイバルアワードで知り合った美術制作集団THE ICEMANSとも意気投合。今回の「遭難」は雪山が舞台ということもあり、恵庭市にあるTHE ICEMANSの広大な庭で、外稽古を行なったそうです。以下、極寒稽古を体験した竹原さんの感想です。「HAUSの活動を通じて、アーティスト同士のつながりができています。外での稽古は、五感で感じる大切さを痛感しました。例えば夜になって、暗く、冷えて来た時に感じる火の暖かさと灯り。暗闇の怖さ。火の付け方一つにしても、芝居の中では些細な仕草の一つでも、それら一つ一つに確かな意味があって、稽古場での稽古よりも遥かに雄弁だったように思います。」竹原 圭一2013年6月22日RED KING CRAB発足後に居酒屋やbar、音楽ライブ、ショーパブ等の幕間等でパプォーマンスを一年間行い、現在は劇場での演劇公演を主に活動中。RED KING CRABの代表。既成台本を除くこれまでの作品の脚本、演出を勤める。演劇活動の旁で、小学生、中学生、高校生の学生向けのワークショップや地域のお祭り、福祉施設等で演目を披露している。2023年なんでも屋を開業。THE ICEMANS タケナカヒロヒコ(造形作家・思想家)、Alidad Kashani(芸術家)、上野かな子(デザイナー)、を中心メンバーとして活動。 2006〜2019年 ニセコを中心に冬のアートイベントを企画運営。 2017〜2020年 知床流氷フェスティバル会場にて氷の建造物を制作。 2020年以降コロナ禍では、自然と人間の繋がりに主眼をおき、道内の様々な場所で巨大なバルーンを使った氷のドームを制作。個人宅の庭先に一晩でアートを出現させるプロジェクト、”THE ICEMANSキノコのように降臨”をスタート。 活動を記録した映像作品はYoutubeチャンネルTHE ICEMANS DANCEで公開中。 冬の楽しみを通して自然との調和を提唱している。
ニュース RED KING CRAB竹原圭一さん除雪の仕事を始めました #ニュース ニュースRED KING CRAB竹原圭一さん除雪の仕事を始めました2023.1.31text 戸島由浦(HAUS)HAUSサバイバルアワードに参加してくれたRED KING CRABの竹原さんが、除雪の仕事を始めました。アートと労働を考えるハウスとしては、応援いていきたいと思っています。大雪で除雪の問題を抱える札幌の皆さん。除雪のご用命は竹原さんまで!それから、併せて、いろいろな場所での演劇ワークショップのご用命も承っています!竹原 圭一2013年6月22日RED KING CRAB発足後に居酒屋やbar、音楽ライブ、ショーパブ等の幕間等でパプォーマンスを一年間行い、現在は劇場での演劇公演を主に活動中。RED KING CRABの代表。既成台本を除くこれまでの作品の脚本、演出を勤める。演劇活動の旁で、小学生、中学生、高校生の学生向けのワークショップや地域のお祭り、福祉施設等で演目を披露している。2023年なんでも屋を開業。
ハウスサバイバルアワード HAUS studies vol1「LGBTQ+と演劇の今」 #ハウスサバイバルアワード ニュースHAUS studies vol1「LGBTQ+と演劇の今」2022.11.23HAUS studies vol1「LGBTQ+と演劇の今」HAUSは、ハウス・サバイバル・アワードにてアーティストの困りごとや課題を広く募りました。劇団「千年王國」主宰の櫻井幸絵さんから新作上演に向けての相談を受け、今回の勉強会を企画しました。劇団「千年王國」の新作は、「ロミオとジュリエット」の世界を、男性たちの同性愛の物語に書きかえ、セクシャリティと社会の摩擦を、二人の恋の障害として描くロック・ミュージカルです。勉強会には、ジャーナリストの北丸雄二さんを講師として迎え、アート作品の中でLGBTQ+に触れるときの態度や知識、グローバルスタンダードを学びます。稽古場にて演出家・俳優たちと共有すべきこと、当事者と非当事者の対話の方法を一緒に考える機会になります●講師:北丸雄二(ジャーナリスト、作家)●聞き手:櫻井幸絵(劇団「千年王國」主宰)●日時:2022年11月23日(祝・水)19:00〜21:30●会場:後日連絡(札幌市内)●参加費:無料●定員:会場15名+オンライン 定員になり次第締め切りとさせて頂きます。●主催:HAUS http://haus.pink ●助成:令和4年度札幌市文化芸術創造活動支援事業●プロフィール、講師:北丸雄二(きたまるゆうじ)ジャーナリスト、作家東京新聞(中日新聞)ニューヨーク支局長を経て1996年に独立。在米25年の2018年に帰国し、現在はTBS、文化放送、J-WAVEなどのラジオおよび「デモクラシー・タイムズ」などのネット番組などでニュース解説も。毎週金曜日に東京新聞で「本音のコラム」連載。近著「愛と差別と友情とLGBTQ+」(人々舎)で、「紀伊國屋じんぶん大賞2022」2位。聞き手:櫻井幸絵(劇団「千年王國」主宰)劇作家・演出家・俳優。1999年劇団「千年王國」設立。愛と暴力と死の普遍的な物語を、お母さんのまろやかさで表現する。音楽、ダンス、美術家との共同制作も多数。札幌を拠点に、道外・海外公演も行う。2013年、BSプレミアムドラマ「神様の赤ん坊」脚本担当。2005年、演出家協会主催・若手演出家コンクール最優秀賞・観客賞ダブル受賞。2009・2011・2013年TGR 札幌劇場祭演劇大賞受賞。二児の母。
ハウスサバイバルアワード HAUSの支援とサバイバルアワード #ハウスサバイバルアワード サバイバルアワードHAUSの支援とサバイバルアワード2022.9札幌市から助成を受けて、2022年9月に募集したハウス・サバイバル・アワードでは、40組のアーティストからの応募があり、全てのアーティストたちのサポートをすることに決定しました。 審査はHAUSの各メンバーが定めた審査基準に対して、どのアーティストへ重点的に支援を行うかHAUS内で議論をしました。結果としてご応募頂いた全ての方に対して資金面に限らず何かしらのサポートを行いHAUSが伴走することにしました。今回のハウス・サバイバル・アワードは、HAUSが目指しているアーティスト同士の関係を作り出すための実験的な取り組みです。40組のアーティストたちにHAUSメンバーが伴走している様子をこのHPで報告していきます。
ニュース 小林大賀さん絵本原画展 TO OV cafe galleryにて #ニュース ニュース小林大賀さん絵本原画展(TO OV cafe / galleryにて)2023.2.22text 戸島由浦(HAUS)美術家の小林大賀さんが、個展を開いています。2月26日まで、絵本の原画19点のほか、絵画6点、制作過程の資料などを展示しています。会場の中心に設置された机のようなものは、映像美術として制作したものだそうです。会場で絵本も販売中。定価2000円(税込)内容は大人向けです。絵本の購入を希望する方には銀行振込み、郵送での対応も可能です。気になる方は、taiga.kob■gmail.com(■→@)までご連絡くださいとのことです。【小林大賀絵本原画展ー謝肉祭ー】詳細はこちら〇会期2023年2月14日(火)〜2月26日(日)※会期中無休〇営業時間10:30-20:00〈ラストオーダー19:30〉〇会場TO OV cafe / gallery ト・オン・カフェ/ギャラリー札幌市中央区南9条西3丁目2-1マジソンハイツ1階(地下鉄「中島公園駅」より徒歩1.5分)【HAUSコメント】筆者の戸島(HAUS)も伺ってきました。実は前日に、知り合い2人から「行ってきたよ」と言われ、先を越された…と思いながら、美術をしている知り合いを誘っていきました。しっとりとした色合いで、物語の一言一言も味わい深く、何度も繰り返して見返したくなる原画展だなと思います。北海道新聞にも取り上げられたようです。会場は、土日ということもあってか、静かではありつつも来客は多く、にぎわっていました。カフェなので、一通り見て、座って、ゆっくり過ごしました。HAUSでは、小林さんのリサーチに伴走しています。この半年くらい、彼は、制作している人の精神的なことについて、話を聞きに行っているのです。人によって違う角度から深い話が聞けるようで、こういうやり取りができること自体が興味深いことではないでしょうか。私たちも、相談先や似たテーマを持つ作家とつないだりしながら、彼を追っています。
ニュース ポケット企画 第8回公演「おきて」札幌公演がはじまります #ニュース ニュースポケット企画 第8回公演「おきて」札幌公演がはじまります2023.2.13text 渡辺たけし(HAUS)HAUSで支援している劇団ポケット企画の本番が近づいています。ぜひ、劇場に足をお運びください。これからも、繰り返されます。また、ここで。 爺ちゃんが亡くなった。はじめて人の死に触れた。身体をどこかへ返す時、生きていて幸せだったのか想像がつかない。 爺ちゃんも幸せだったのかなって、時代を作ったことも、時代に生きたことも、僕の記憶だけではわからない。 こんな時だからこそ、家族の話を聞いてみよう。 ポケット企画第8回公演は過去のインタビューと現在の想いを綴った追悼のお話。 これまで背負っていたものとこれから背負っていくものを詳らかにするために、劇場へ向かう。 作・演出:三瓶竜大(ポケット企画/劇団清水企画) 出演:三瓶竜大 さとうともこ(ポケット企画/トランク機械シアター) 河野千晶(micelle) 平尾拓也(極北会) 宮ノ森しゅん(クラアク芸術堂) ポケット企画 「ポケットに入れて持ち運べる演劇」をテーマに札幌で活動中の劇団。2018年の旗揚げ以降、TGR札幌演劇祭2019「新人賞」、第6回全国学生演劇祭「最優秀賞」(2021年)、おうさか学生演劇祭vol.15「最優秀劇団賞」(2022年)を受賞。ポケット企画 第8回公演「おきて」開催期間2023年02月24日~2023年02月26日2月24日(金)19:00開演18:30開場2月25日(土)15:00開演14:30開場/19:00開演18:30開場2月26日(日)13:00開演12:30開場/17:00開演16:30開場開催場所扇谷記念スタジオ・シアターZOO札幌市中央区南11条西1丁目3-17ファミール中島公園B1F主催者ポケット企画料金全席自由一般 前売2500円/当日3000円U-25 前売1500円/当日2000円高校生以下 前売1000円/当日1500円※U-25は、25歳以下のお客様を対象とした割引チケットです。お問合せポケット企画電話080-6177-2131公式サイトhttps://pocket-kikaku.com/
ニュース 劇団fireworks 『畳の上のシーラカンス』公演がはじまりました #ニュース ニュース劇団fireworks 『畳の上のシーラカンス』公演がはじまりました2023.2.10text 渡辺たけし(HAUS)HAUSサバイバルアワードに参加してくれている米沢春花さんが主催する劇団の公演が今週末からはじまります。お時間あるかたは是非!札幌演劇シーズン2023‐冬 参加作品劇団fireworks 『畳の上のシーラカンス』偉い人が「平成」の額を上げた頃。ひよどり荘の301号室は昼はたまり場、夜は酒場の様相を呈する、無法地帯であった。また、この301号室は時折「この部屋で昔起きたこと」をビデオテープのように映し出してくるのであった。そんな部屋とはつゆ知らず、小説家になる夢を抱え青年が入居してきた。人間と部屋に翻弄されながら彼は、未来に何かを残せるか。昭和、平成、令和と駆け抜けるはちゃめちゃノスタルジックコメディ。【脚本・演出・舞台美術】米沢春花(劇団fireworks)【日時】 2023年2月11日(土祝)18:00 ♪ 12日(日)14:00 ★ 13日(月)20:00 14日(火)20:00 15日(水)20:00 16日(木)20:00 17日(金)20:00 ★ 18日(土)14:00 ★/18:00 ※♪=終演後アフターライブあり(約15分) ※★=終演後アフターコントあり(約15分) ※開場は各開演の40分前です【会場】演劇専用小劇場BLOCH(札幌市中央区北3条東5丁目5 岩佐ビル1F)【チケット】一般3000円/学生1500円(前売り・当日共通)ローソンチケット:Lコード 18294チケットぴあ:Pコード 516-267道新プレイガイド:TEL 0570-00-3871/https://doshin-playguide.jp/市民交流プラザチケットセンター店頭 https://sapporo-cp-members.jp/Nチケ:https://ticket.aserv.jp/nt/PassMarket:passmarket.yahoo.co.jpcorich:https://ticket.corich.jp/apply/206411/【出演】和泉諒(劇団fireworks)井上嵩之(→GyozaNoKai→)小川しおり(劇団fireworks)木村歩未(劇団fireworks)きゃめ(ハッピーポコロンパーク・劇団コヨーテ)桐原直幸(劇団fireworks/二度寝で死にたいズ)高橋雲(ヒュー妄)棚田満(劇団怪獣無法地帯)恒本礼透橋田恵利香(劇団fireworks)むらかみ智大山崎耕佑(劇団fireworks)【音楽】山崎耕佑(劇団fireworks)【音響】高橋智信(劇団fireworks)【照明】竹屋光浩(ヘリウムスリー)【演出助手】佐藤優将(劇団米騒動)【衣装】大坂友里絵【小道具】神田花緒【相談役】鎌塚慎平(劇団・木製ボイジャー14号)【お問い合わせ】ticket.fireworks@gamil.com劇団fireworks公式Twitter(@fireworks)にて最新情報を更新中! #畳の上のシーラカンス で検索! 札幌演劇シーズン公式HPも併せてご参照ください。
ニュース 小林大賀さん2月14日からト・オン・カフェギャラリーで個展 #ニュース ニュース小林大賀さん2月14日からト・オン・カフェギャラリーで個展2023.1.31text 戸島由浦(HAUS)HAUSが応援している小林大賀さん、2月14日から、中島公園近くのト・オン・カフェギャラリーで個展です。ぜひ。お見逃しなきよう。2月中旬より自作の絵本「謝肉祭」の原画を中心とした個展を開催します。会場にて本の販売もいたします。足元の悪い季節ですが、お越しいただければ幸いです。小林大賀 個展会場:TOOV cafe /gallery ト・オン・カフェ / ギャラリー会期:2023年2月14日(火)〜2月26日(日)会期中無休時間:10:30~20:00札幌市中央区南9条西3丁目2-1 マジソンハイツ1階 (地下鉄南北線「中島公園駅」より徒歩2分)TEL 011(299)63802月14,18,19,25,26日は在廊予定です。(18,19日は13:30〜)
ニュース HAUS studies “LGBTQ+と演劇の今” の講師北丸雄二さんの配信あります。 #ニュース ニュースHAUS studies "LGBTQ+と演劇の今" の講師北丸雄二さんの配信あります。2023.2.13text 羊屋白玉(HAUS)11月に、HAUS のstudies"LGBTQ+と演劇の今"の講師として札幌まで足を運んでくれた北丸雄二さん。北丸さんのツイッターはこちらです。今宵はこちらでお話を聞けるのですね!タイトルが続編みたいで楽しみ✨↓2月13日21時からダースレイダー x 北丸雄二、尾辻かな子″LGBTQと日本の社会と政治″ 配信があります。こちら
ニュース HAUS studies vol2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」 #ニュース ニュースHAUS studies vol2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」2023.1.22HAUS studies vol2「アーティストと、ギャラと、働くことと、生活と。」〜契約とは、対話なのです〜公演が決まったけれど、いくらもらえるか分からず、あえて突っ込もうとも思わない。展示が決まったけれど、制作費も交通費もないぞ。契約書、ありがたいような気がするけれど、内容はよく分からない。確定申告って、インボイスってなんなのだ、あの作品を使いたいけれども誰にご相談すればよいのか。疑問はつきません。今回は、弁護士の田島佑規さんをお迎えし、活動にまつわる実際のトラブル事例やその対策を取り上げながら、北海道のアート活動において出演交渉等にどう向さ合っていくべきか、依頼される側、する側それぞれの立場を踏まえながら考えてゆきます。些細なことでも、ワークルールに関するお悩みあればぜひご参加を。オールジャンルのアーティスト、マネージャー、デザイナー、お待ちしております。●アドバイザー:田島佑規(弁護士)●聞き手:リンノスケ(俳優)●日時:2023年1月22日(日)17:30〜19:30●参加費:無料●主催:HAUS http://haus.pink ●助成:令和4年度札幌市文化芸術創造活動支援事業アドバイザー:田島佑規(たじまゆうき)「骨塩通り法律事務所」弁護士。その他、文化庁EPAD事菜 権利処理チーフ、緊急事態舞台芸術ネットワーク車務高、京都大学法科大学、芸術文化製光市門職大学 非常野菜市等を務め、アー下、満時、映像、出版、音楽などの分野にて法務サポートを行う。2019年より、「デザイナー法)小他の企画・運営を行っている。聞き手:リンノスケ俳優。北海道出身。札幌市立大学デザイン学部卒。在学時の2015年より俳優・舞踏を始め、2016年に旗揚げしたきっとろんどんを共同主宰。また劇団千年王國に出演した際は「贋作者」では鴈次郎役、「ロミオとジュリエット」ではロミオ役でそれぞれ主演を演じた他、micell、モノクロームサーカス、東野祥子、伊藤千枝、田仲ハル、Sapporo Dance Collectiveなどのダンス・舞踏作品にも出演。2022年からは活動拠点を東京と北海道の2拠点に広げた。
インタビュー 演技と生活をリンクする 日々を見つめて「深化」する俳優 インタビューその1 大川敬介さん #インタビュー インタビューその1 林業と俳優 大川敬介さん演技と生活をリンクする日々を見つめて「深化」する俳優Text : 渡辺たけし(HAUS)Photograph : 長尾さや香Place : The Icemans工房裏庭(恵庭市)2022.8.28HAUSアーティストインタビューは、札幌で活動するアーティストを、たくさんの人に知ってもらいたいという思いからスタートしました。第1期は2022年夏から2023年春に取材したさまざまな分野のアーティストを順次掲載します。今回がその第1回目です。札幌や北海道を見渡すと、芸術とは違う分野のお仕事をしながら作品をつくり続ける人たちが多いことがわかります。いわゆる「兼業アーティスト」です。俳優の大川敬介さんは、「林業」への就業を目指しながら俳優業を続けています。「そういえば、ぼく自身も『林業』についてはよく知らないな」という興味が一番にありました。それとあわせて「林業と創作って、もしかすると、どこかでつながってるのかもしれないぞ」という勝手な仮説への好奇心がふくらみ、取材をお願いしてみました。まずは、大川さんがどうして俳優を志すに至ったかを尋ねてみました。ジャン・レノに憧れて俳優業へ東京で芝居の基礎に出会うーよろしくお願いします。まず名前と生年月日をお願いします。大川敬介です。1979年生まれ。ー生まれはどこですか?札幌市清田区です。今は札幌市北区に住んでいます。ー大川さんは、俳優などのほかにもいろんなお仕事をしてると思うんですが、現在、生活を支えるためにどんな仕事をしていますか?電化製品のサポートを電話で行なうという仕事をやっています。元々は長く東京でお芝居をしていたんですが、納得できるような芝居の活動ができなくなり、北海道に戻ってきました。その後は、北海道の劇団に入って、演劇の講師をしたり、CMや映像のお仕事をしたり、俳優関係の仕事だけで生活していました。でも、それだけだと、どうしても貯金を切り崩していくしかなくて。その後、劇団を辞めてフリーになり、何もなくなっちゃったので、じゃあ、ちゃんと仕事しようかと。それがコールセンターの仕事を始めたきっかけです。ーコールセンターのお仕事って、今一番大変な仕事って言われてますよね。研修はちゃんとありましたけど、もともと芝居のことしか知識がないし、電話かけてくる人と商品知識は同じレベルだから最初は大変でした(笑)。やっと最近、なにも見なくても応対できるようになりました。コールセンターの仕事を選んだのは、時間の融通がきき、芝居するのに都合が良いからです。ー俳優の仕事をしようと思ったのは、どういう経緯ですか?10代の頃、何もしたいことがなくて、映画ばっかり見てて。ーどういう俳優に憧れましたか?当時は、もうとにかくジャン・レノが好きでした。フランス映画もですね。流行ってたってのもあるし。リュック・ベッソン監督でジャン・レノ主演で最初に撮った「最後の戦い」とか。とにかく映画が好きだったんです。漠然と俳優になりたいと思いましたが、映画にはあまり関わりがなくて、結局、舞台ばっかりでした。ー東京ではどこで演劇をしていたのですか?専門学校を出た後に、最初は、秦建日子(はた たけひこ)さんという脚本家の養成所で、がっつりお芝居の勉強をしました。その養成所で講師をしていた「富良野塾」出身の築山万有美さんという女優の方に俳優としてのイロハを教えてもらいました。それは今でも自分の演技の根底にありますね。最近、改めてそれが大事だなって思っています。※ 秦建日子=小説家、劇作家、演出家、脚本家、映画監督。2003年から2013年まで演劇ワークショップ「TAKE1」を主宰。2006年ドラマ化ヒットした「アンフェア」の原作者としても有名※富良野塾=北海道富良野市にあった脚本家と俳優の志望者たちのため養成所。「北の国から」の脚本家 倉本聰が塾長だった。※ 築山万有美=富良野塾出身の俳優。京都府出身。ー稽古場はどこにあったの?事務所は麻布十番にありました。当時は麻布十番のカフェ・ラ・ボエムっていうレストランで夜中働いて、昼にそのまま稽古場に通ってました。そこの養成所には2〜3年くらいいました。食えずに札幌Iターン兼業俳優という選択ー秦建日子さんの養成所をやめた後は?フリーでの活動を模索してたんですけど、俳優として東京で生活していく事に、次第に限界を感じるようになりました。30歳前後でしたので、今後の人生とか考えて、北海道に帰ってきました。ー東京での生活は何年続いたのですか?結局、12年で東京を出ました。ただ、20代の時に東京で知り合った友達は、自分にとっては大き存在でした。自分の成長過程を知っている友達だったので、それを捨てて東京を後にする感覚だったので、当時はかなり悩みました。それと比較しても、俳優を続けたいっていう気持ちが勝ったので、札幌に戻り、札幌の劇団で俳優を続けることを選択しました。ーそのあと、札幌の演劇ユニット「イレブンナイン」に入団したんですね。このカンパニーに入ったきっかけは?※イレブンナイン=札幌を中心に活躍する演劇カンパニー。まだ東京在住の時、秦さんからのすすめで、一度、納谷真大さん(「イレブンナイン」主宰)演出の舞台に出させてもらったことがありました。それが、その劇団を選んだ理由の一つです。札幌の俳優に混じって、僕だけが東京から参加していました。北海道舞台塾の企画「正しい餃子の作り方」(2008.3札幌にて上演)というお芝居でした。ー北海道が新しいステップだったんですね。やはり、また東京に戻りたい?「また東京に戻りたい」という気持ちは、若干変化してます。今は日本じゃなくてもいいのかなということをボンヤリと思っています。精神的にもそうですけど、役作りのプロセスに関しては、東京でやってる人と、世界でやってる人とあまり変わりはない気がします。東京でやっていても、札幌でやってても、札幌以外の地方でやってても、例えば森の中でやってたとしても、すごい人たちはたくさんいることを知りましたし。でも、やってる以上はたくさんの人に観てもらいたいなっていうのはあります。単純に稼ぐお金の問題もありますし(笑)。ーわかります。お金も重要です(笑)。札幌は俳優だけで食えてる人ってほとんどいないと思います。俳優業だけで生活している人のことだけを「プロ」とは呼ぶわけではないなと、改めて今は強く思ってます。ーHAUS(Hokkaido Artists Union Studies)のスタンスでいうと、専業のアーティストだけが、アーティストではないと考えています。札幌は、圧倒的に兼業アーティストが多いですよね。特に俳優業に関していうと、この職業自体に「プロフェッショナル」という言葉が当てはまるのかという疑問を感じています。流暢な演技をする人が「プロフェショナル」というイメージがあると思うんですが、それはちょっと違うと思っています。どれだけ演技をしないかっていうことが、重要だと僕は思っています。ですから、俳優の「演技力」と「生業として成立しているか」ということは、直結していないと思うんです。北海道にも、専業俳優ではなくても凄い芝居するなって人が沢山います。舞台人との出会いそして、林業との出会いーなるほど。ほかに影響を受けた方はいますか。「イレブンナイン」の活動のなかで、劇作家・演出家の山下澄人さんに出会えたことは、かなり衝撃的な出来事でした。※山下澄人=小説家、劇作家、演出家、俳優。2017年、『しんせかい』で第156回芥川賞受賞ー劇団「FICTION」主宰の方ですね。山下さんとの作品づくりの中で、経験も肉体も精神もフルに使い果たさないと、本当に面白いと思うものはできないっていうことを、まざまざと感じさせられました。体の生皮を全部はがされた気がしました。実際にそう言われたわけではないですが、「お前は、本当にこの世界を捉えているのか?」「お前の真剣は本当に真剣なのか?」いうことを常に問われるような日々でした。今まで台本に書かれた役しか見えてなかったものが、全方位対して開いたような感覚は、ものすごくあるんですよね。人間を演じるヒントは、日常の中にたくさん隠れていると思います。最近は人じゃないものばっかり演じてますけど(笑)。羊屋白玉さん演出の指輪ホテル「ポトラッチ」(2021.12白老にて上演)で自分が演じたのは、山の精霊みたいなものだと思っています(笑)。※羊屋白玉=指輪ホテル芸術監督・演出家・劇作家・俳優。HAUSメンバー。指輪ホテル「ポトラッチ」撮影: yixtapeーその他は、最近どんな芝居に出演していましたか?最近だと、櫻井幸絵さん演出の劇団千年王國「からだの贈りもの」(2021.12札幌にて上演)です。もうすぐ、再演もあります。もともといろんな演出家のもとでやりたいっていう希望がありました。福岡に行って韓国のコンテンポラリーダンサーの振り付けの作品にださせてもらったり。あとは、コンドルのスズキ拓朗さんや、山海塾の石井則仁さんの作品に出演しました。※櫻井幸絵=札幌を代表する劇団「千年王國」を主宰。けれん味溢れる舞台には定評あり。※コンドルズ=コンテンポラリー・ダンスカンパニー。男性のみ学ラン姿でダンス・映像・コントなどを展開。世界20ヶ国以上で公演。※スズキ拓朗=ダンサー振付家・演出家チャイロイプリン主宰、コンドルズ所属。Eテレで振り付けなども。※山海塾=1975年に設立された天児牛大主宰の舞踏グループ。世界43ヶ国のべ700都市以上で公演を行っている。※石井則仁=舞踏家、振付家。キュレーションカンパニーDEVIATE.CO芸術監督、山海塾所属。ー身体表現が多いですね。「こんな表現をしたい」という目標はあるんですか?到達点ってあるんでしょうかね?演技の正解もその都度あるんでしょうけど、本番の舞台が終わった数年後、なにかしらの日常生活をしてる時に、「あ、これだ!」って気づくことがあります。目標は果てしなく遠くにある気がします。演技というものがなにかわからないから続けている気がします。ーお話を聞いていると。道を求める侍っぽいですね(笑)侍っぽいというのは、昔からよく言われます(笑)。ーこうやって俳優の仕事をしながら、今は林業にも興味があるとききました。林業と出会った経緯をお話ししてもらっていいですか?2020年にアーティストの竹中博彦さんに、話の流れで「大川くん、キコリをやってみない?面白いよ」と教えてもらいました。恥ずかしい話ですが、林業という職業があるっていう事もその時まで知らなかったので、「何ですかそれ?」ってなったんですけど。多分、瞬間的に「面白そう!」って自分のセンサーが反応したんですよね。※竹中博彦=北海道を中心に氷と雪を使った美術作品を作り続ける「The Icemans」の主要メンバー。今回の取材場所は、竹中さんの自宅庭を拝借した。林業に惹かれる理由不安定な足場思い返すと、2018年の飛生芸術祭(白老町)で、石井則仁(山海塾)さんの作品に出たことがあったんです。クリエイションの過程で、飛生の森に集まる動物の神様をモチーフに、出演者がそれぞれ自分で振り付けを考えるという宿題がありました。自分は馬の神様をモチーフとして選びました。その本番の中で、石井さんから、舞踏の技の一つに「伐倒(ばっとう)」という技術があるということを教えてもらいました。木を切り倒した時のように、自分の体を、そのまま後ろ向きにバタンと垂直に倒すという技なんです。石井則仁振付「神景」 撮影:yixtapeー何もない地面に垂直に倒れるんですか!?森で後ろ向きのまま、受身を取らずバタンと倒れるんです。それを見た時に衝撃を受けました。多分その記憶もあって、林業に繋がったんだと思います。結局、今、ライスワーク(ご飯を食べるための労働)として働いているコールセンターの仕事は、芝居に直結するわけではないので、それを変えたいなって思ったんです。林業と俳優の二つをライスワークとライフワークにしたいと思うようになりました。2021年から林業研修として白老町の林業の会社で研修を受けています。今すぐ始めてしまうと、どうしても賃金が下がってしまうので、まだ転職したわけではないんですけど、今は準備段階です。月に何回か勉強に行っています。ーどのくらいの期間、林業の勉強するのですか?3年後ぐらいに転職できたらいいなと思っています。今は、いろんな人の話を聞いて、情報を仕入れてる段階です。けれども、舞台と同じように、国や自治体からの補助金をもらわないと、林業も厳しそうだということがわかりました。特に自分がやろうとしている自伐型林業っていうのは、特に厳しいそうでして。たくさんのネットワーク必要だと思っています。去年は、月に1回の研修を半年間やりました。研修が終わった人は、自分ではじめるなり、どこかの会社に入るなりしていると聞きました。人それぞれなんです。今、やっている仕事もあるので、ガラッと生活を変えることができないのが、もどかしいんですけど、三年後にスタートできればいいなと思っています。今はガッツリ「林業やってます!」って胸張って言えるわけじゃないですけど、準備はしています。歩みは遅いかもしれないですけど。※ 自伐型林業=一気に伐採するのではなく長期的な視野で森を育てていく林業ー林業のどこに惹かれたんだろうね。林業の研修で、初めて自分が立木を切った時、ものすごい音を立てて木が倒れていくんですが、その音がものすごく美しかったんです。鳥肌がたったのを覚えています。もちろん命懸けで舞台はやってますけど。舞台をしてても実際に死ぬことは、ほとんどないわけですよね。でも、林業に関していうと、一歩間違えると本当に死んでしまうわけです。ー命がけですね。実際に自分もチェーンソーで失敗して、ちょっと危ない目にもあってますし。重機にぶつかってしまった人も実際見てますし。そうなってくると、木を切る時の準備段階として、「どこを切ったらいいのか?」、「どの方向に倒したらいいのか?」、「この切り方で合ってるのか?」っていう感じで、頭も身体もフル回転させないといけなくて。山の中って平らじゃないですよね。安定できないことですごく鍛えられる気がしています。役者をしているときの不安定な感覚にも似ていると思います。ー不安定というのは、体幹的にっていう意味だけではなく、精神的にという意味もですね?林業している時の感覚は、精神的にも敏感になります。舞台上で芝居している時の感覚とあまり変わらない気がします。なので、森で働くっていうことと、舞台上で芝居しているっていう感覚がものすごく近いっていうことを体感したんです。それで、林業も面白いなって思い、始めたいなと思ったんです。祖父が大工をしていたというのも、何かしら自身のルーツとしてあるのかもしれません。祖父も材を取りに山に入っていたというのも聞いたことがありました。でも、仕事としてやるには経験も全然足りないですし、林業を自分の仕事にするのは、まだまだ一人では怖くてできたもんじゃない。俳優と林業は兼業できるのか?木の皮剥きの密かな悦楽ー俳優と林業の兼業を希望ですか?俳優とも兼業していきたいと思っています。お金をかせぐことが目的の労働の中だけにいると、俳優としてのセンサーが閉じてしまう気がしています。生活として働いてる時も、舞台の感覚は錆び付かせたくないんです。俳優としての感覚を研ぎ澄ますためにも、林業が自分にとっては適してるんじゃないかなって思っています。他に俳優の感覚を磨ける職業がありそうだったら教えてください(笑)ー兼業のアーティストって、お金を稼ぐ仕事(labor)と作品作り(work)をどう使い分けているんだろうね。それはArtis Ttreeのテーマでもあるんです。たぶんその人なりに、そういった感覚をリンクさせながら生活してるんだと思います。今までは芝居が第一優先としてありましたけど、今は家族もいますので、芝居をしてるっていう時点で迷惑かけてるなという思いもありますが、パートナーもパフォーマンスの仕事をしているので、わかってくれていますけれど。夫婦で、お金のことや今後の仕事について話し合うこともあります。そのことは、しつこいぐらい話すようにしてます。自分一人だけの生活ではないので、そこもあくまでチームとしてお互いにやりたいことができればいいなと思っています。ー話は変わるのだけれど、最近、木の皮を剥くワークショップなどをしていると聞きました。「木の皮を剥く」活動って?木の皮をひたすら剥きますね。ーやってみると、面白いですよね。面白いですね。自分の癖で、何に関しても芝居の役作りとか、演技の感覚に絡めちゃうんですよ。一般的に「役者は、役の仮面を付ける」と言われますが、僕の感覚としては「仮面を外す」ってほうが近いんです。この木の皮を剥くっていう作業が、演技の感覚とリンクすることが多くて。木の皮を剥くと、想像していなかった木の姿が現れます。普段では見れない姿が見れるわけです。剥いてみたら、その中に虫が蠢いていたりとか、木の中が腐っていたりとか。木の内部の本当の色は、こういう色なんだと分かったり。すごい美しいなって単純に思うんです。伐採したばかりの木の皮は水分を含んでるから、ものすごくスルスル剥けるので単純に気持ちいいです。剥け方は木の種類によっても違います。面白いから、勝手にやってる感じです(笑)。ー勝手にやってる感じね(笑)。この間、発見したことがありました。伐採してしばらくたった乾燥した木を貰って剥いでいたんです。一回濡らして水分を含ませると、剥きやすくなるんですよ。木の中にも微生物なんかもいるんだろうね、濡らして剥くと木の匂いが変わってくるんです。そのときは、海の匂いに似てるなって思いました。ー不思議ですね。多分、木の中にいる微生物が腐ったような匂いだと思うんです。海の匂いなんかも、生物が腐った匂いなのかもしれませんね。自分の記憶の中でのドリームビーチの匂いでした(笑)。海の匂いも、本質的には、生き物の死骸が堆積した匂いなんでしょうね。「死」の匂いだと思うんですよね。すごく面白いと思います。こういうふうに勝手に想像していることが、俳優としての役づくりにつながればいいなぁと思ってます。ー木の皮剥きのワークショップはどんな感じでした?参加人数は少なかったんですけれど(笑)。でも、ワークショップをしたことで、多分、僕自身はすごく癒されたんですよね。木の皮剥きって、やってみると好きな人はたくさんいると思うんですよね。ーぼくも、先日挑戦しましたが、これは創作の時の感覚に似てるなと思いました。思いますよね!木の皮を剥いている時って、脳がすごく動くんですよね。ここで木の節に引っかかるようだったら、どの方向に、どういう力を入れて剥けばいいかとか。ーわかります。攻略的な目線ですね。では、将来的には、林業しながら俳優やっていこうと?そうですね。俳優は体が動かなくなるまでやりたいっていう気持ちはあります。しかし、俳優という仕事が生業になるかどうかも分からない。でも、俳優業も労働の一つと捉えているので、死ぬまで続けるという目標だけは二十年以上変わってません。ー仕事の概念が「お金を稼ぐこと」となったのは、わりと近代になってからなんですって。自己実現だったり、「それをしていきたい」という欲求が仕事であるはずだと、労働を専門に研究している人たちは言いますね。そうかもしれないですね。俳優としてのモチベーションさらに深くまで潜りたいー将来的に、演技指導の仕事などしてみたいという気持ちはありますか。CrackWorks「undercurrent」 撮影:クスミエリカhttps://youtu.be/MXNatAhx1Mcもちろん頼まれればやりたいですね。演技指導される側の人に対して、それこそ皮を剥いてしまうかもしれないから、指導される側も大変なんじゃないないかと思いますが(笑)。ただ、基礎を教えてくれた築山さんがそういった指導だったので、そこは受け継いでいるかもしれません。山下さんの作り方も物凄く影響を受けていますし、実際自分が講師をしていた時もひたすら学生たちの演技の固定概念を外すような指導をしました。演劇ではないけれど、最近、「CrackWorks」っていう集まりを作って、YouTubeに映像作品をあげています。ただ、自分で作品をつくってみてわかりましたが、自分自身は、作り手よりも、役者=プレイヤーを続けたいという思考が強いんだなっていうのは再認識しましたね。でも、特にこの札幌では、プレーヤーだけでやっていくのはどうしても難しいので、自分から作品を作っていた方がいいのかなとは思っています。ー大川さんが、作品を作り続けるモチベーションってなんなんだろうね。僕は、今生きている人に対して演劇をしてない気がします。むしろ、死者に対してなのかな。僕の中には、常に世の中に関する絶望があるような気がします。芸術のシステムや社会にも、政治にも。僕がやってる演劇の根底に何があるのかなって改めて思った時に、まず絶望があって、その上に怒りと祈りがあると思います。2020年にサッポロ・ダンス・コレクティヴで上演した「さっぽろ文庫101巻 『声』」に参加したときも、コロナで苦しんでいる人たちに対して、何もしていないように感じられる政治に対しての怒りが、僕の演技の根底にはありました。※ サッポロ・ダンス・コレクティヴ=札幌を中心としたクリエイターが集い、提案、実験、対話し、ダンスを創造する集団。2018年から作品を世に送り出している。HAUSの母体。ーあの作品では、台本の一部も書きましたよね。当時は、コロナで苦しんでいる人たちの声をサンプリングしてるっていう感じでした。実際にコロナに罹患した方の声と、札幌に点在しているホームレスの方たちの声と、自分がやっているこの俳優としての声、劇場の現状などをいろいろサンプリングしてテキストを書きました。ー俳優の仕事、自分の生活、社会に対する思い、いろんなものの距離が近くなっているんですね。全部がリンクしてるような感じがありますね。リンクすることで、さらにそれぞれが「深化」していくイメージもあります。このインタビューの最初の話題にでた監督リュック・ベッソンの映画「グラン・ブルー」も、ダイバーがフリーダイビングで、海に深く潜るって話でした。潜り過ぎると戻ってこれなくなっちゃうってのも演技と一緒かな。ー次の本番はいつですか?次の本番は、劇団千年王國 「からだの贈りもの」再演です。HIVエイズに感染した末期患者の役を演じます。ーまた、激しく体重を落とすのですか?初演では12キロ落としたと聞きました。レベッカ・ブラウンの原作の一行目は「今度の人は見た目に一番不気味だった。本当に病そのものに見えた。」という体の描写から入ってるので、「じゃあそれはそういう体にならなきゃいけない」と思っています。映画「グラン・ブルー」ではないですけれど、ギリギリまで潜りたい気持ちはあります。ー今日はいろいろお話し聞けてよかったです。話がいろいろと、とっ散らかって、すみません。ーそんなことないですよ。ありがとうございました。興味深かったです。※残念ながら、この後、劇団千年王國 「からだの贈りもの」は、新型コロナウィルス感染対策のため中止になりました。この時期の様子もアーカイブしたいという考えから、この注意書きを付記したうえで、あえて記事はこのままにさせてもらいました。林業に従事することを目標にしながら俳優活動をする大川さん。やはり、「木に触れること」と「演じること」に共通点はあるようですね。とても興味深いお話でした。こんな感じで、兼業で創作活動している人にインタビューをしてみようかなと思っています。このインタビュー企画が持ち上がった時から、ずっと考えていたことがあります。札幌には子育てをしながらアーティスト活動している人たちがたくさんいます。「育児」と「アーティスト活動」を兼業している人のお話も聞いてみたいなと思います。ということで、2回目は「育児中アーティスト」にインタビューしてみたいと思っています。インタビューその2美術家 森本めぐみさん今回インタビューされた人 大川敬介1979年 札幌市生まれ。俳優。秦建日子氏に2年間師事後、様々な劇団やダンス作品に参加。2021年よりCrack Worksを主宰し、演劇に捉われない作品や企画を発表。最近の俳優としての出演は、指輪ホテル「ポトラッチ」(しらおい創造空間『蔵』2021年)、劇団千年王國「からだの贈りもの」(2021年初演、2023年再演予定)今回インタビューした人 渡辺たけし1971年小樽生まれ。公立中学校数学教員。劇作家、演出家。いろいろな地域の人々を取材し演劇作品などにしている。HAUSでは、アーティストの労働条件や人権について担当。
ハウスサバイバルアワード 毛皮族「セクシードライバー」 #ハウスサバイバルアワード 伴走リポート札幌のリサーチに向けて・・・2022.12.20text 奥村圭二郎(HAUS)江本純子さんの舞台「セクシードライバー」を観に行ってきました。HAUSでは、江本さんが2020年以降に取り組んでいる映像演劇を北海道で実現するため、会場さがしのお手伝いをしています。そういう意味で今回の公演を観に行っておいて本当に良かったと思いました。会場となっている北千住BUoYへはJR北千住駅から10分程歩いて向かいます。北千住は駅の東側は東京電機大学のキャンパスが出来て整備されましたが、西側は昭和感の漂う飲み屋さんやクラブ、お洒落な飲食店が入り混じっているユニークな場所です。BUoYにはそんなエリアと閑静な住宅街を越えて行きました。BUoYの地下に降りると、aka劇団ひとり・江本純子さんのマイクパフォーマンス(?)が開演前から既に始まっていました。キャンプチェアが観客席として使われていて、その雰囲気はリラックスして鑑賞してもらうためのものだと分かりました。映像を鑑賞しつつ、実際の出演者がライブパフォーマンスとしてセリフを映像に合わせて発していて、映像と演劇の両方を掛け合わせたような臨場感のある舞台が設られていて、四角いスクリーンに投影される映像に熱中しつつ、会場中央からセリフを発している俳優たちの方も気を取られる刺激的な体験でした。スクリーンから飛び出してくるはずの声が、別の角度から聞こえることは不思議な体験でした。長回しで撮影された映像は編集が入らないという意味で迫力感がある一方で、余計な部分を削ぎ落としたくなることがありますが、それがあまり感じられませんでした。こう感じたのは、コロナ禍以降、家で映像を見る機会が多くなり慣れてしまっていたからでしょうか?明らかに、映像に出てくる俳優と、舞台上で演技する俳優から受け取る感覚はこれほど違うものなのかと強い印象を持ちました。江本純子1978年千葉県生まれ。00年、21歳の時に劇団「毛皮族」を旗揚げ。09年より「財団、江本純子」を開始。09年『セクシードライバー』、10年『小さな恋のエロジー』は岸田國士戯曲賞最終候補作。08年~13年、セゾン文化財団ジュニアフェロー。16年に初監督作品である映画『過激派オペラ』が公開。16年より開始したプロジェクト「できごと」にて、同年夏に小豆島・大部地区に滞在し、野外演劇を製作・上演。システムや既存の慣例に沿わない独自の演劇作りの方法を提示している。19年よりセゾン文化財団シニアフェロー。
ハウスサバイバルアワード ライブハウスmole16周年イベント #ハウスサバイバルアワード 佐藤遥さんの伴走リポートライブハウスmole16周年イベント踊りながらの人つなぎとリサーチ2022.11.12text 戸島(HAUS)佐藤遥さんと、ライブハウスmoleに行きました。彼女は音楽ライターで、自身の注目する札幌の音楽シーンを記録しまとめたいということで、HAUSサバイバルアワードに応募してくださいました。注目しているのは特に、今回伺ったmoleなどのクラブハウスで行われるダンスミュージックです。今回、16周年イベントがあるとのことで、一緒に行って様子を見てきました。夜の11時に始まります。喫茶店で軽くお茶をしてから、会場へ向かいました。彼女は元々はイギリスのダンスミュージックが好きで、将来的にはその界隈も記事にしていきたいと話していました。会場内での彼女と周りとの交流がとても印象的でした。知り合いのDJに挨拶をしたり、見かけたことのある方に話しかけたりと、人脈を作っている様子がうかがえました。さすが音楽ライターですね。私のように初めて来た方と友人をつなげることもあり、札幌のクラブハウス文化を盛り上げたい気持ちや、周囲に慕われる彼女の人間性を感じました。熱気と人の渦に半分飲み込まれながら踊り、明け方イベントが終わった後には、当日出会った方たち数人と朝ご飯へ。DJやmoleに通う方たちと共に、眠い目をこすりながら、音楽機材の話や、佐藤さんがこれからインタビューをする相手候補の相談も話に出ました。佐藤さんの注目するものを中心としつつ、クラブハウスの経営者や出演するDJたちに相談しながら、音楽ムーヴメントが書き起こされていくことになりそうです。札幌では、いくつかの拠点それぞれの盛り上がりがあるという背景も交えながら、シーン形成期から今までの中心DJたちからかかる音楽ジャンルの様子など、少しずつ書き起こして残す予定です。Sound Lab mole 16th anniversary PARTYhttp://mole-sapporo.jp/sound-lab-mole-16th-anniversary-party/
ハウスサバイバルアワード Gallery Slideがプレオープンしました #ハウスサバイバルアワード 株式会社トーチ伴走リポートGallery Slideがプレオープンしました2022.12.15text 戸島(HAUS)Gallery Slideが、北18条のSeesaw Booksの隣に完成しました。プレオープン企画では3名のアーティストの作品を迎えています。元々は車庫だったスペースが、小さなギャラリーに生まれ変わりました。佐野和哉さんという方が、メディア表現を学んだ後、株式会社トーチを立ち上げ、メディアを活用した事業を中心に活動なさっています。今回、Gallery Slideというギャラリーを作るということで、HAUSは資金の一部を助成しました。Gallery Slideの構想は、札幌にギャラリーや展示スペースが少ない、これでは札幌の若手作家の展示機会が限られてしまう、道外の最先端のアートも呼び込みにくい、という問題意識から始まりました。創作活動に取り込む方のモチベーション向上や活動発展に活かせればと考えています。10月に予定地を見せてもらった時には軽量鉄骨と板で形にしていっている途中でした。元々車庫の場所なので天井が低いのですが、それを活かしながら面白い場にできたらと話しておりました。完成した今、考えているのは今後の運営についてです。作品を売ったり、場所として貸したり、様子を見ながら進めていくそうです。興味のある方はぜひ!彼はこのギャラリー以外でも、広告代理店で働いていた経験を活かして、経済的な領域から、アーティスト活動を支える仕組みを作りたいと思っているとのことです。例えば、表現と生活を両立していくのに、時期を選んで働けたり、自由に淡々と作業ができたり、働きやすい場所があるといいというアイデア。実際に事業は進行していて、高齢化して事業を売りたい会社の事業承継をしようかと話が動いているそうです。アーティストの相談にのるHAUS、ビジネス領域につなげる佐野さん、お互いに協力できたらよいなと考えています。2022年12月19日(月)Gallery Slideプレオープン展示『sandbox』トークイベントhttps://torch-galleryslide-1.peatix.com/"札幌でつくっている人たちとの接点をつくるための小規模ギャラリー「Gallery Slide」"プレ展示「sandbox」
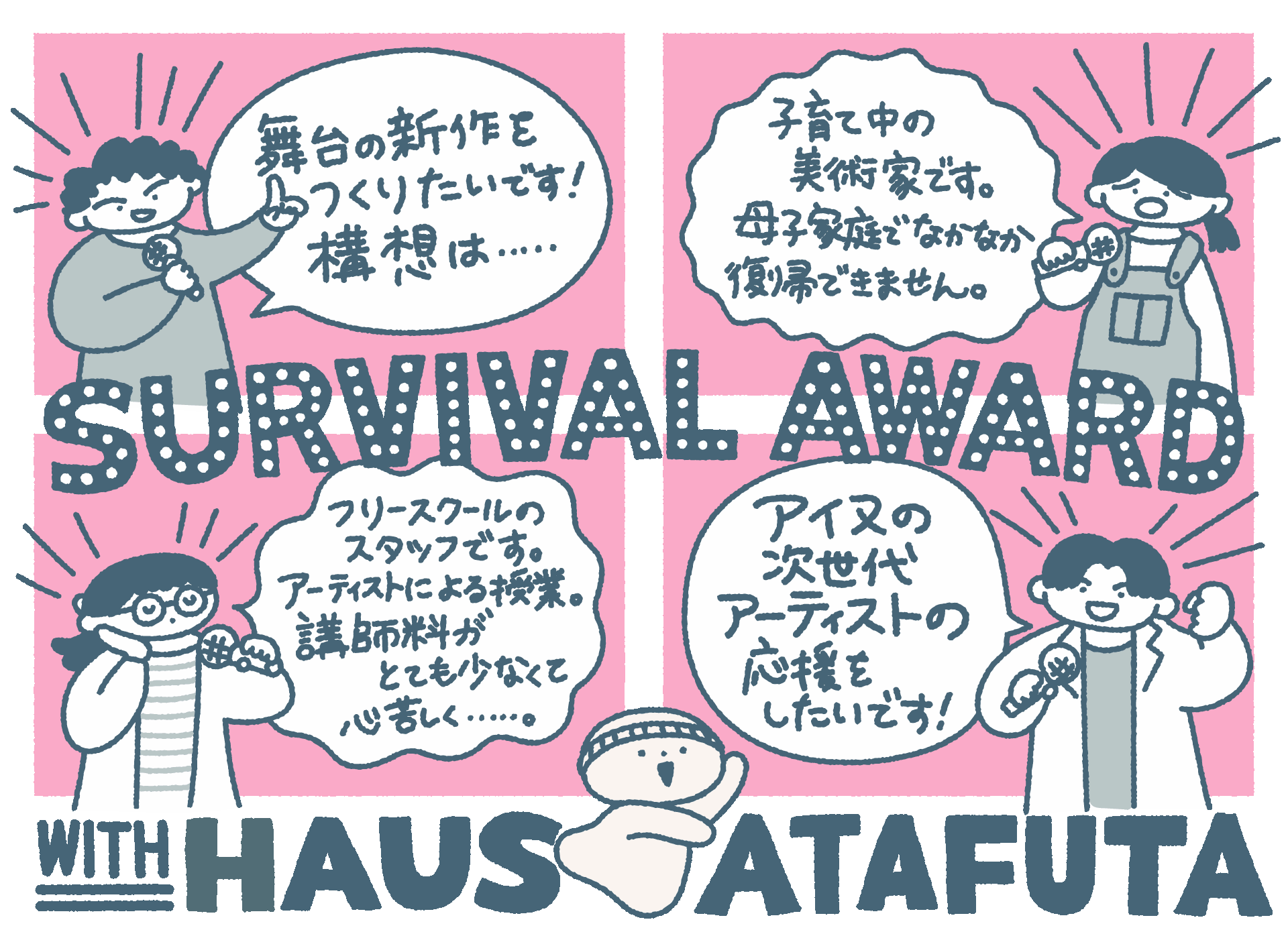
支援とアワード
2022年9月に募集したハウス・サバイバル・アワードでは、40組のアーティストからの応募があり、全てのアーティストたちのサポートをすることに決定しました。
審査はHAUSの各メンバーが定めた審査基準に対して、どのアーティストへ重点的に支援を行うかHAUS内で議論をしました。結果としてご応募頂いた全ての方に対して資金面に限らず何かしらのサポートを行いHAUSが伴走することにしました。
今回のハウス・サバイバル・アワードは、HAUSが目指しているアーティスト同士の関係を作り出すための実験的な取り組みです。40組のアーティストたちにHAUSメンバーが伴走している様子をどうか見守ってください。
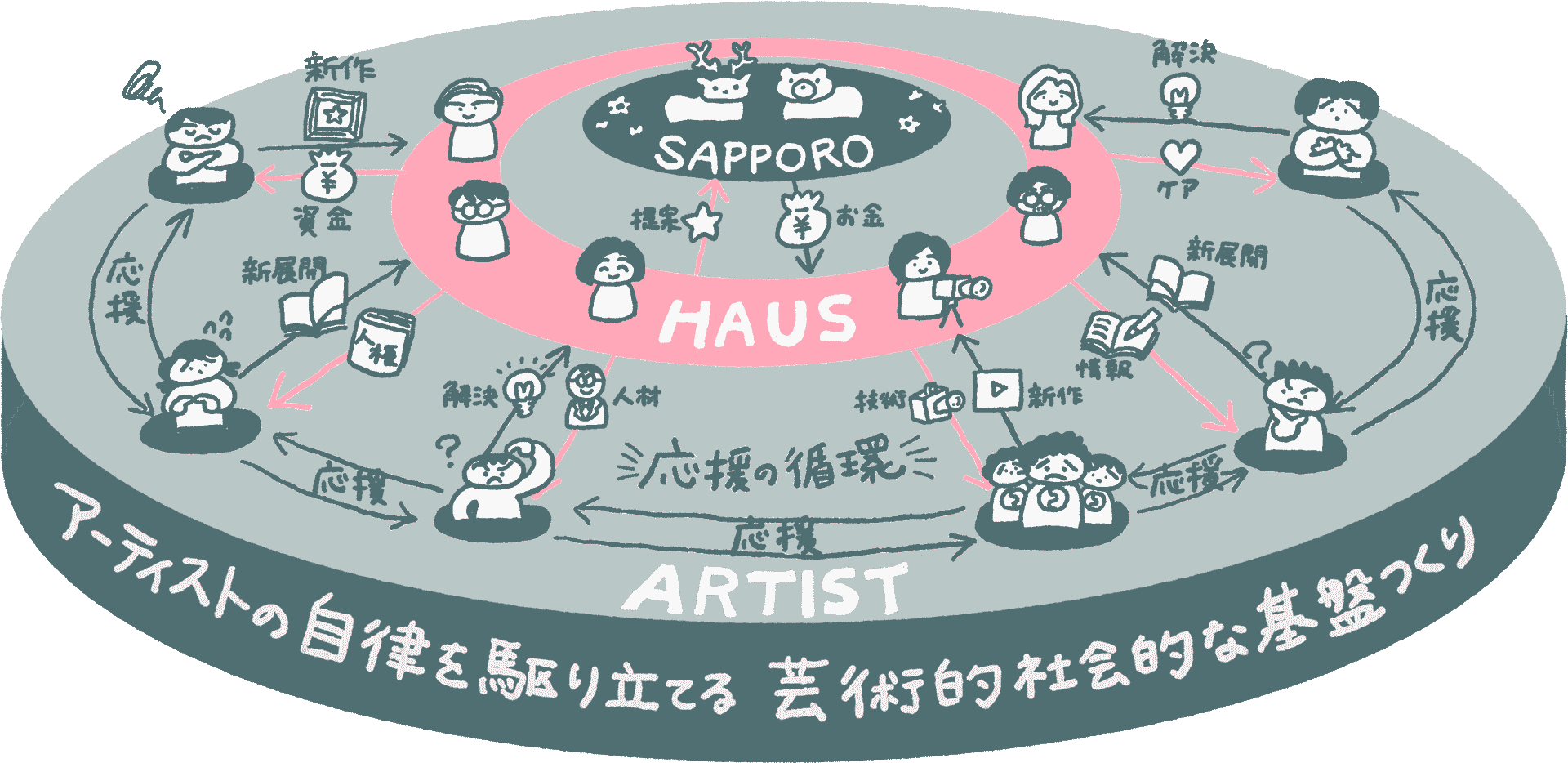
HAUSについて
北海道のあらゆるアーティストの活動環境問題にただただ心を痛めている場合ではないと、2019年秋に設立。
アーティストの自律を駆り立てる芸術的社会的な基盤を目指す中間支援団体です。
以来、創造の現場における様々な”声”を掬い取り、舞台作品上演や、現場のハラスメント実態からつくられたリーディングなど”声”の可視化に取り組んでいます。
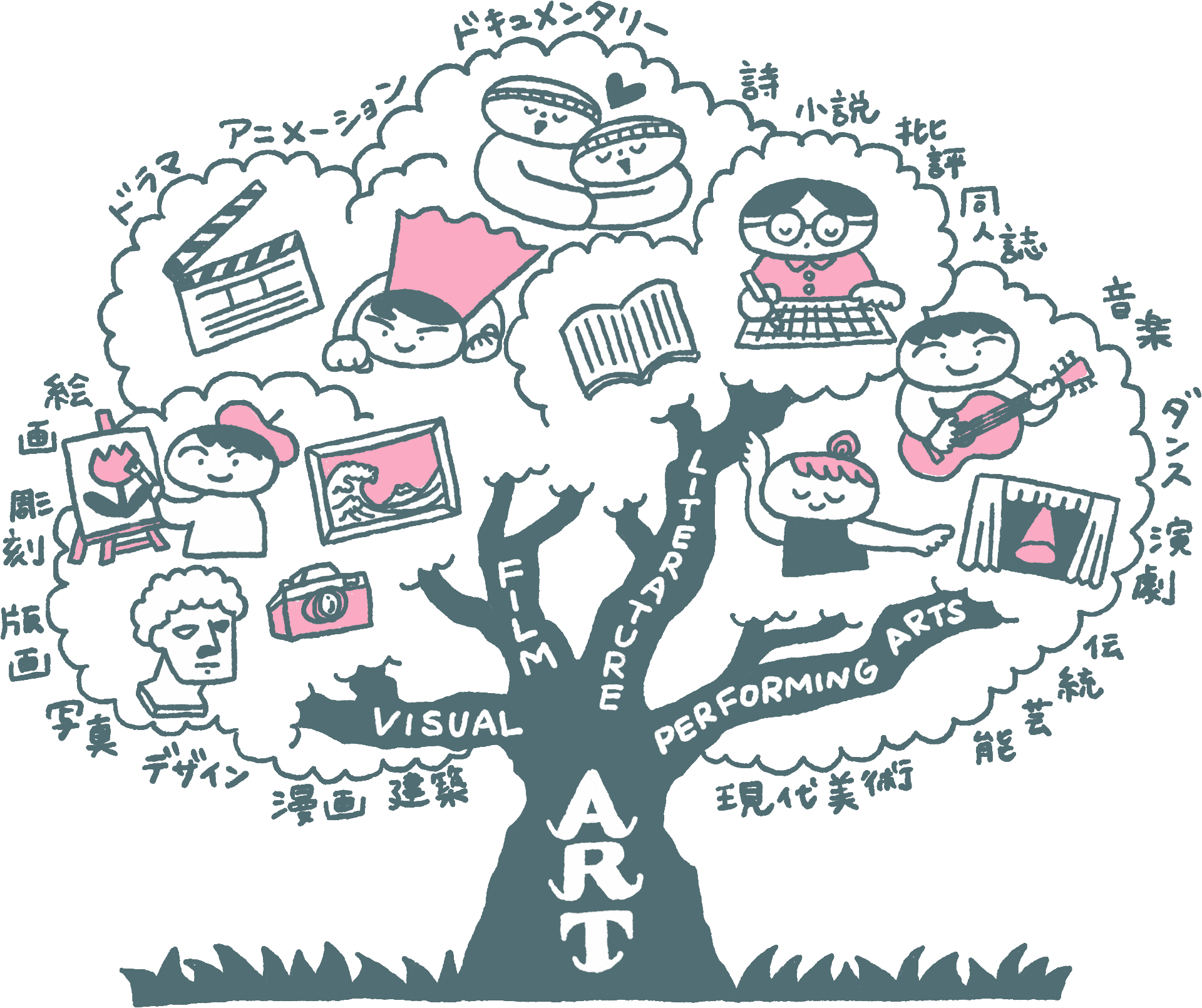
Artist Tree
HAUSはアーティストが出会える場所を作りたいと考えています。
できれば、やっている活動にこだわらず、いろいろな人たちが。
普段やっていることを宣伝したり、思っていることを伝えあったり、
ちょっとした困りごとを交換しあえるスペース。
そんなふうに「Artist Tree」を使っていってください。
アーティスト以外の皆さんもみることできますので、
札幌近郊ににどんなアーティストがいるのか
たくさんの人にお知らせするのも、このサイトの目的の一つです。